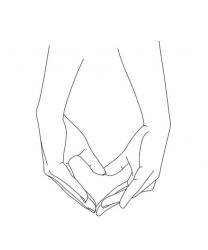この重大な秘密を、Nに隠し続けてきた。
隠しつつ、それでも本当の私をさらけ出しているかのように見せ続けてきた。
誰かに、
「聞きたいことがあるんだけど」
そう言われるたび、
「どっかで見たことあるんだよなあ」
そう言われるたび、私は怯えて生きていかなければいけない。
死ぬまでこの恐怖と共存していかなければならない。
この苦しみに大切な誰かを巻き込むなんて、できるわけがなかった。
Nは、自分の友達に私を紹介することが多くあった。
友達と食事をしに行くのにも私を誘う。
それは、ずっとNを知っている私が隣にいることへの安堵感を求めているのか。
はたまた仲のいい女の子がいることを回りに自慢したい彼の見栄なのか。
どちらかなのかは分からなかった。
隠しつつ、それでも本当の私をさらけ出しているかのように見せ続けてきた。
誰かに、
「聞きたいことがあるんだけど」
そう言われるたび、
「どっかで見たことあるんだよなあ」
そう言われるたび、私は怯えて生きていかなければいけない。
死ぬまでこの恐怖と共存していかなければならない。
この苦しみに大切な誰かを巻き込むなんて、できるわけがなかった。
Nは、自分の友達に私を紹介することが多くあった。
友達と食事をしに行くのにも私を誘う。
それは、ずっとNを知っている私が隣にいることへの安堵感を求めているのか。
はたまた仲のいい女の子がいることを回りに自慢したい彼の見栄なのか。
どちらかなのかは分からなかった。