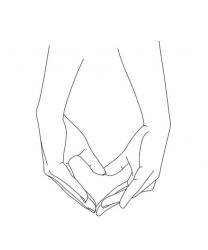「嫌われたくなくて今まで黙ってたんだけど……」
彼がそう前置きしたことで、余計に真剣な雰囲気が漂っている。
逃げ出したい気持ちを抱える私とは対照的に、
彼は何か覚悟を決めたようだった。
「正直に言うと、今までユキと少し距離置いてた」
あの時の激白と同様、私の目を見てくれないNの言葉が、本心から来ているものなのだと。
「俺さ、結構単純なところあるし女の子に免疫ないから、ちょっとのことですぐ好きになっちゃうんだよね。
ユキは自分でも言ってる様に八方美人だし、
それは俺にも向けられてる訳で。
優しいのも助けてくれるのも傍にいてくれるのも、
嘘なのかもなって思ってた。
嘘って思いたかった。
そうじゃないとユキのこと……好きになりそうだった。
なりそうというか、ごめん、好きだった」
高校生の時だけど、と苦し紛れに小さく呟いた。
告白と同時に謝罪なんて、残酷だ。
その残酷な結果に導いたのは紛れもなく私で。
"好きになられたらバイバイかな"
彼がそう前置きしたことで、余計に真剣な雰囲気が漂っている。
逃げ出したい気持ちを抱える私とは対照的に、
彼は何か覚悟を決めたようだった。
「正直に言うと、今までユキと少し距離置いてた」
あの時の激白と同様、私の目を見てくれないNの言葉が、本心から来ているものなのだと。
「俺さ、結構単純なところあるし女の子に免疫ないから、ちょっとのことですぐ好きになっちゃうんだよね。
ユキは自分でも言ってる様に八方美人だし、
それは俺にも向けられてる訳で。
優しいのも助けてくれるのも傍にいてくれるのも、
嘘なのかもなって思ってた。
嘘って思いたかった。
そうじゃないとユキのこと……好きになりそうだった。
なりそうというか、ごめん、好きだった」
高校生の時だけど、と苦し紛れに小さく呟いた。
告白と同時に謝罪なんて、残酷だ。
その残酷な結果に導いたのは紛れもなく私で。
"好きになられたらバイバイかな"