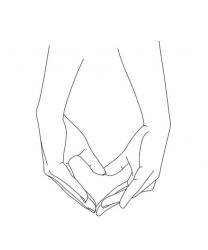「思ってないんだ」
Nの突っ込みを、私は笑って誤魔化した。
ごめんね、おめでとうだなんて思えないよ。
本音を言えば、ちょっとショックだったのかもしれない。
統計的に見ると女は、自分の話に共感してもらうと喜ぶ生き物らしい。
でも私は異常な生活を彼に話しながらも、共感して欲しいなんて思ったことがなかった。
むしろ私の気持ちが分かる日なんて、永遠に訪れないでほしかった。
Nには綺麗なままでいて欲しかった。
なんて、穢れた私が言えることじゃない。
「もう私の話しない方がいい?」
「どうして?」
「だって、そういう系の話多いから嫌なこと思い出させちゃうかなって」
「何言ってんの。そんなこと考えないで。
俺のせいで話したいこと話せなくなるなんてだめだよ。
今までと何も変わらないで。
別にユキの話聞いたからって嫌な思いとかしないから」
そんなはずないのに…。
Nの突っ込みを、私は笑って誤魔化した。
ごめんね、おめでとうだなんて思えないよ。
本音を言えば、ちょっとショックだったのかもしれない。
統計的に見ると女は、自分の話に共感してもらうと喜ぶ生き物らしい。
でも私は異常な生活を彼に話しながらも、共感して欲しいなんて思ったことがなかった。
むしろ私の気持ちが分かる日なんて、永遠に訪れないでほしかった。
Nには綺麗なままでいて欲しかった。
なんて、穢れた私が言えることじゃない。
「もう私の話しない方がいい?」
「どうして?」
「だって、そういう系の話多いから嫌なこと思い出させちゃうかなって」
「何言ってんの。そんなこと考えないで。
俺のせいで話したいこと話せなくなるなんてだめだよ。
今までと何も変わらないで。
別にユキの話聞いたからって嫌な思いとかしないから」
そんなはずないのに…。