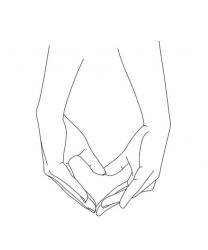父への嫌悪感が体に現れるようになったのは、9歳の時だった。
平日の朝、目が覚めると時計の針は午前10時を指していた。
飛び起きた私の体を落ち着かせるようにして母は優しく言う。
「今日は病院に行く日だから、学校はお休みだよ」
頭の中でハテナマークを浮かべながら、朝ごはんを食べ両親と共に車に乗った。
持病の喘息のせいで通いすぎた小児医院とは別の方向に向かって走る車の中は、異様な空気感だった。
私の心の内もまた、異様な空気感に影響されていた。
学校を休めて嬉しい気持ちと、どこへ行くのか分からない不安な気持ちの二重奏。
ただ、人の顔色を伺う癖のある私は後者の気持ちを外に出さずにいた。
連れていかれた場所は、オレンジ色の三角屋根に肌色の壁面。
それはまるで協会のようで、病院を感じさせない見た目をしていた。
状況を理解できない私を置き去りに、両親は素早く手続きを済ませた。
可愛らしいお姉さんに呼ばれて、何故か私だけが別室に連れていかれた。
その別室でいくつかのテストを受けた。
平日の朝、目が覚めると時計の針は午前10時を指していた。
飛び起きた私の体を落ち着かせるようにして母は優しく言う。
「今日は病院に行く日だから、学校はお休みだよ」
頭の中でハテナマークを浮かべながら、朝ごはんを食べ両親と共に車に乗った。
持病の喘息のせいで通いすぎた小児医院とは別の方向に向かって走る車の中は、異様な空気感だった。
私の心の内もまた、異様な空気感に影響されていた。
学校を休めて嬉しい気持ちと、どこへ行くのか分からない不安な気持ちの二重奏。
ただ、人の顔色を伺う癖のある私は後者の気持ちを外に出さずにいた。
連れていかれた場所は、オレンジ色の三角屋根に肌色の壁面。
それはまるで協会のようで、病院を感じさせない見た目をしていた。
状況を理解できない私を置き去りに、両親は素早く手続きを済ませた。
可愛らしいお姉さんに呼ばれて、何故か私だけが別室に連れていかれた。
その別室でいくつかのテストを受けた。