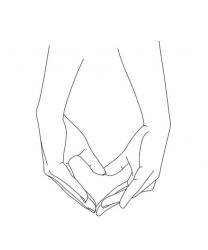そう言っていつだって私を満たす。
これだから、彼と話すのは好きなんだ。
Nだけは全てを受け入れてくれる。
Nだけは何をしても傍にいてくれる。
安易に私を抱きしめる人たちとは違う安心感を感じていた。
Nがいなければ、私の精神はとうに限界を迎えていただろう。
それでも彼は突然、
「そんなこと続けてたらきっと、好きになった人には振り向いて貰えないよ。
それでもいいの?」
何の前触れもなく、優しい声で私の心を刺してくる。
「……なにいってんの。そんなわけないじゃん」
無理して笑った私に、彼は気づいただろうか。
「ごめんな」
悪くないのにそう謝って、いつもの彼に戻った。
そう、それでいいの。
私を傷つけないで。
これだから、彼と話すのは好きなんだ。
Nだけは全てを受け入れてくれる。
Nだけは何をしても傍にいてくれる。
安易に私を抱きしめる人たちとは違う安心感を感じていた。
Nがいなければ、私の精神はとうに限界を迎えていただろう。
それでも彼は突然、
「そんなこと続けてたらきっと、好きになった人には振り向いて貰えないよ。
それでもいいの?」
何の前触れもなく、優しい声で私の心を刺してくる。
「……なにいってんの。そんなわけないじゃん」
無理して笑った私に、彼は気づいただろうか。
「ごめんな」
悪くないのにそう謝って、いつもの彼に戻った。
そう、それでいいの。
私を傷つけないで。