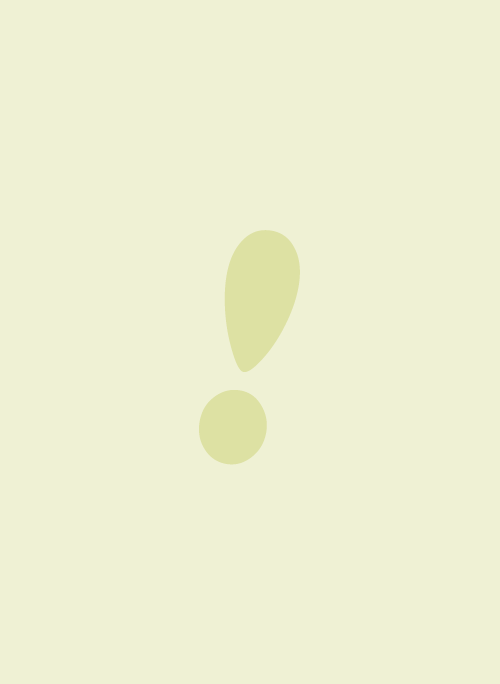あたしの心の叫びが通じたのか、高明くんが口を開いた。
「れん、この子、由紀。俺らと同じ学部だかられんも知ってるかな?」
知らないと言えるわけもなく、なんて言おうか考えていると、すぐに由紀が口を開いた。
「高明、私が一方的に知ってるだけだよ。れんちゃん、金髪で目立つから。私、由紀。よろしくね。」
「あ、ああ、よろしくね。」
あたしの名前も知っていた。
だから、特に自己紹介しなくてもよいと思い、一言返事をするとタバコの煙を吸い込んだ。
高明くんのこと、呼び捨てだし・・・。
それにしても、しばらく話をしない間にこんなに親しい人ができたのか。
高明くんの背中についていく姿はまるで、ちょっと前のあたしみたいだ。
そこのポジションはあたしだったのに。
彼女がいると聞かされた時以上のショックを受けた。
そして、そのショックはだんだんと嫉妬へと変わっていく。