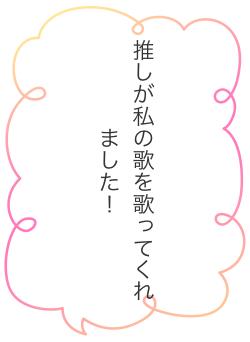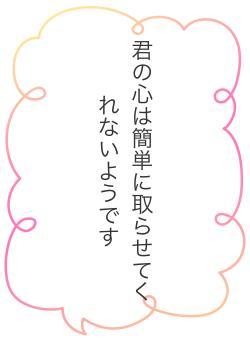次の日、いつものようにつまらない学校から帰ってきて京子のお見舞いに行こうと服を着替えている時、
京子のお母さんから電話がかかってきた。
「はい、健司です」
『健司くん……たった今、京子がっ……』
「……は?」
その後は、よく覚えていない。
覚えているのは、真っ白で動かなくなった京子を見て、俺はずっと涙が枯れるまでずっと泣いていたこと。
そして、そんな俺の背中を母さんがずっとさすっていてくれたことだけだった。
京子のお母さんから電話がかかってきた。
「はい、健司です」
『健司くん……たった今、京子がっ……』
「……は?」
その後は、よく覚えていない。
覚えているのは、真っ白で動かなくなった京子を見て、俺はずっと涙が枯れるまでずっと泣いていたこと。
そして、そんな俺の背中を母さんがずっとさすっていてくれたことだけだった。