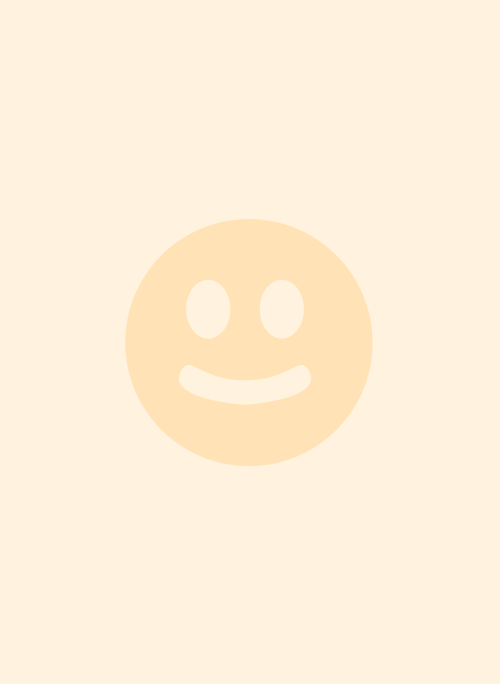やっぱりおかしい。
ランだったらあんなことは言わない。
きっと不安がって、涙ぐんで、動揺するだろう。
それとも、もう麻生君のことはなんとも思ってないだけなの?
二人の会話が遠ざかっていった。
そして、私一人が昇降口に残されていた。
bbbbbbbb…。
携帯が震える。
メールだ。
いったい誰だろう。
「嘘…」
携帯を開いた私は血の気を失った。
メールの相手は、麻生マコトだった。
ランだったらあんなことは言わない。
きっと不安がって、涙ぐんで、動揺するだろう。
それとも、もう麻生君のことはなんとも思ってないだけなの?
二人の会話が遠ざかっていった。
そして、私一人が昇降口に残されていた。
bbbbbbbb…。
携帯が震える。
メールだ。
いったい誰だろう。
「嘘…」
携帯を開いた私は血の気を失った。
メールの相手は、麻生マコトだった。