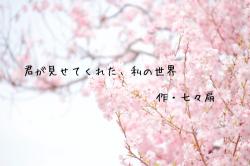「…俺の女が綺麗で見惚れる気持ちは分かるが、惚れてみろ。殺すからな。」
「め、滅相もございません!
俺はただの下働きみたいなもんで…。」
男の子も、自分と大して年齢が変わらないであろう女が偉そうに藤雅の隣にいるから。
気になったのか、ちらちらと伺うようにわたしを見ているのに気がついた。
そうだよね。
面白くないよね、自分は頭下げる側で。
こんな小娘に頭下げなきゃいけないなんて。
…なんて、また卑屈になってる。
ああ、嫌だなあ。
こういう風に思っちゃうの、よくないのに。
「良いよ、藤雅。
減るものじゃないし。」
「あ?良くねえだろ。」
「気になっただけだよ、きっと。」
「それが気に食わねえんだよ。」
「…そう。」
藤雅に八つ当たりしても意味無いのに。
分かってるのに、止まらなかった。
不機嫌になった藤雅を見て、オロオロし始めたからすごく申し訳ない。
人を寄せつけないくらいには、イライラし始めてるからわたしも触れないでおく。
わたしの前で不機嫌になることは少ないけど、こういう事では直ぐに機嫌悪くなる。
困った人だ。
「あ、電話だ。
藤雅ちょっと出てくるね、すぐ戻るから。」
「ああ。 なるべく早く来いよ。」
なんだ、柊か。
後から掛け直しても良かったけど、今度のライブの事だろうからなるべく早く済ませておきたい。
「め、滅相もございません!
俺はただの下働きみたいなもんで…。」
男の子も、自分と大して年齢が変わらないであろう女が偉そうに藤雅の隣にいるから。
気になったのか、ちらちらと伺うようにわたしを見ているのに気がついた。
そうだよね。
面白くないよね、自分は頭下げる側で。
こんな小娘に頭下げなきゃいけないなんて。
…なんて、また卑屈になってる。
ああ、嫌だなあ。
こういう風に思っちゃうの、よくないのに。
「良いよ、藤雅。
減るものじゃないし。」
「あ?良くねえだろ。」
「気になっただけだよ、きっと。」
「それが気に食わねえんだよ。」
「…そう。」
藤雅に八つ当たりしても意味無いのに。
分かってるのに、止まらなかった。
不機嫌になった藤雅を見て、オロオロし始めたからすごく申し訳ない。
人を寄せつけないくらいには、イライラし始めてるからわたしも触れないでおく。
わたしの前で不機嫌になることは少ないけど、こういう事では直ぐに機嫌悪くなる。
困った人だ。
「あ、電話だ。
藤雅ちょっと出てくるね、すぐ戻るから。」
「ああ。 なるべく早く来いよ。」
なんだ、柊か。
後から掛け直しても良かったけど、今度のライブの事だろうからなるべく早く済ませておきたい。