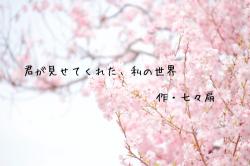「戻ってくるの早くない?」
「お前がいないから、寂しかった。」
「もう、大丈夫だよ。ここにいるから」
藤雅がわたしの肩に頭を押し付けてくるから。
お風呂上りのさらさらした髪を撫でると、わたしと違う香りがした。
そりゃそうだ。
藤雅はアメニティのものを使っただろうし、わたしは持ってきたいつものやつ。
もちろん、こんなに良いホテルなんだからわたしが持ってきたシャンプーよりもアメニティの方が高級だろう。
だけど、ただでさえ環境が変わると眠れないから纏う香りくらいは同じにしたい。
そうじゃないと、落ち着かなくて変にそわそわして不安な気持ちになるのは分かりきっていたから。
なのに。
藤雅から、いつもと違う香りが…わたしと違う香りがすることに気が遠くなる感じがする。
「芽来?」
なにこれ、なにこの感じ。気持ち悪い。
足元が安定しない、今立っているのかも分からない。
頭もぐらぐらして眩暈までしてきた。
靄がかかったみたいに、思考がはっきりしなくて酸素が薄い。
ぱくぱくと口を開けて精一杯呼吸をしようとするけど出来ていないのか、息苦しさまで覚え始める。
「と、とうがっ…香り、いつもと、ちがう…。」
「…少し待ってろ、すぐ戻る。」
「お前がいないから、寂しかった。」
「もう、大丈夫だよ。ここにいるから」
藤雅がわたしの肩に頭を押し付けてくるから。
お風呂上りのさらさらした髪を撫でると、わたしと違う香りがした。
そりゃそうだ。
藤雅はアメニティのものを使っただろうし、わたしは持ってきたいつものやつ。
もちろん、こんなに良いホテルなんだからわたしが持ってきたシャンプーよりもアメニティの方が高級だろう。
だけど、ただでさえ環境が変わると眠れないから纏う香りくらいは同じにしたい。
そうじゃないと、落ち着かなくて変にそわそわして不安な気持ちになるのは分かりきっていたから。
なのに。
藤雅から、いつもと違う香りが…わたしと違う香りがすることに気が遠くなる感じがする。
「芽来?」
なにこれ、なにこの感じ。気持ち悪い。
足元が安定しない、今立っているのかも分からない。
頭もぐらぐらして眩暈までしてきた。
靄がかかったみたいに、思考がはっきりしなくて酸素が薄い。
ぱくぱくと口を開けて精一杯呼吸をしようとするけど出来ていないのか、息苦しさまで覚え始める。
「と、とうがっ…香り、いつもと、ちがう…。」
「…少し待ってろ、すぐ戻る。」