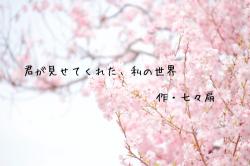「藤雅はさ。」
「ん?」
「人の上に立つのって緊張しないの?」
「緊張か…。
俺にとったら昔から当たり前のことだったから考えたこともねえな。
あの家に生まれた時点でほとんど決まった未来だから。」
「そっか。
藤雅もわたしも…規模は違うけど、お互い守らなければならないものがあるよね。」
「そうだな。
それに…俺は組よりも何よりも先にお前を守る。
お前が望むなら組だって、この地位だって簡単に捨てられる。」
風呂の湿気と暑さで少しだけ赤くなっている芽来の肩。
噛みつくように、痕が残るように。
強くキスを落とした。
わ、と声を上げて身じろぐのも許さない。
今にも折れてしまいそうな両腕を片手で掴んで、そのまま持ち上げる。
「藤雅っ…!」
「少し黙ってろ。」
芽来の表情が見えないのが残念だが。
きっと、恥ずかしそうに視線を彷徨わせているんだろう。
お前に守られているやつが羨ましいよ。
いっそ、何も守れないような女だったら良かったのに。
「ん?」
「人の上に立つのって緊張しないの?」
「緊張か…。
俺にとったら昔から当たり前のことだったから考えたこともねえな。
あの家に生まれた時点でほとんど決まった未来だから。」
「そっか。
藤雅もわたしも…規模は違うけど、お互い守らなければならないものがあるよね。」
「そうだな。
それに…俺は組よりも何よりも先にお前を守る。
お前が望むなら組だって、この地位だって簡単に捨てられる。」
風呂の湿気と暑さで少しだけ赤くなっている芽来の肩。
噛みつくように、痕が残るように。
強くキスを落とした。
わ、と声を上げて身じろぐのも許さない。
今にも折れてしまいそうな両腕を片手で掴んで、そのまま持ち上げる。
「藤雅っ…!」
「少し黙ってろ。」
芽来の表情が見えないのが残念だが。
きっと、恥ずかしそうに視線を彷徨わせているんだろう。
お前に守られているやつが羨ましいよ。
いっそ、何も守れないような女だったら良かったのに。