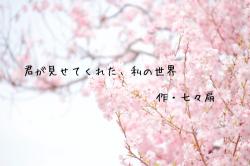「そんな顔しないでください。
俺の母親、一条に借金して飛んだんで。
天涯孤独だった俺を若が拾ってくれたんです。」
「…そうだったんですか…。」
「まだ中学生でしたから。
あの時、若に拾って頂かなければ…俺はどうなっていたか…。」
「…昔のことだ。」
わたしを肩に寄りかからせてくれている藤雅の顔は。
そう言いながらも、少し照れたようだった。
可愛い。
ちょっと照れくさかったのかな。
そんなことを呑気に思っていたら、わたしの携帯が鳴っていることに気がついた。
「わ、やば…。」
「どうした?」
「お母さんから…。
ごめん、1回出るね。…もしもし?」
『芽来!?やっと繋がった!
何してたのよあんた!』
「ご、ごめん…。」
家を出たのがお昼前。
気づけば、外は真っ暗だ。
ちらりとスマホの時計を見れば、夜の8時を回ったところだった。
色々ありすぎて、てっきり忘れてた…。
電話を出る時に、履歴を見るとお母さんから沢山の着信とメッセージが来てた。
俺の母親、一条に借金して飛んだんで。
天涯孤独だった俺を若が拾ってくれたんです。」
「…そうだったんですか…。」
「まだ中学生でしたから。
あの時、若に拾って頂かなければ…俺はどうなっていたか…。」
「…昔のことだ。」
わたしを肩に寄りかからせてくれている藤雅の顔は。
そう言いながらも、少し照れたようだった。
可愛い。
ちょっと照れくさかったのかな。
そんなことを呑気に思っていたら、わたしの携帯が鳴っていることに気がついた。
「わ、やば…。」
「どうした?」
「お母さんから…。
ごめん、1回出るね。…もしもし?」
『芽来!?やっと繋がった!
何してたのよあんた!』
「ご、ごめん…。」
家を出たのがお昼前。
気づけば、外は真っ暗だ。
ちらりとスマホの時計を見れば、夜の8時を回ったところだった。
色々ありすぎて、てっきり忘れてた…。
電話を出る時に、履歴を見るとお母さんから沢山の着信とメッセージが来てた。