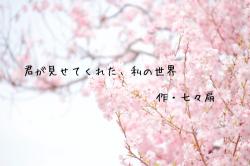「こんな気持ちを知るなら
貴方に出逢わなければよかった
わたしがわたしを嫌いになるくらい」
本当に。
貴方の存在を知らなければ良かった。
あの時、公園に行かなければ。
ハンカチを拾わなければ。
こんな思いをする必要なかった。
「それでもわたしは
貴方に恋焦がれるの
2人で花が見たいと笑い合いたいと
いつの日かを待ち侘びて
淡い期待と共に春を迎えるの」
きっともう、藤雅は。
わたしのことなんて忘れてる。
わたしと過ごした短い日々は、もう無かったことになっているかもしれない。
全部、自業自得だ。
自分から終わらせたんだから。
なのに、それを想像すると苦しくなる。
「……馬鹿だなあ、わたしは。」
自嘲的に笑うわたしの声が。
ただ暗闇の中に消えていった。
貴方に出逢わなければよかった
わたしがわたしを嫌いになるくらい」
本当に。
貴方の存在を知らなければ良かった。
あの時、公園に行かなければ。
ハンカチを拾わなければ。
こんな思いをする必要なかった。
「それでもわたしは
貴方に恋焦がれるの
2人で花が見たいと笑い合いたいと
いつの日かを待ち侘びて
淡い期待と共に春を迎えるの」
きっともう、藤雅は。
わたしのことなんて忘れてる。
わたしと過ごした短い日々は、もう無かったことになっているかもしれない。
全部、自業自得だ。
自分から終わらせたんだから。
なのに、それを想像すると苦しくなる。
「……馬鹿だなあ、わたしは。」
自嘲的に笑うわたしの声が。
ただ暗闇の中に消えていった。