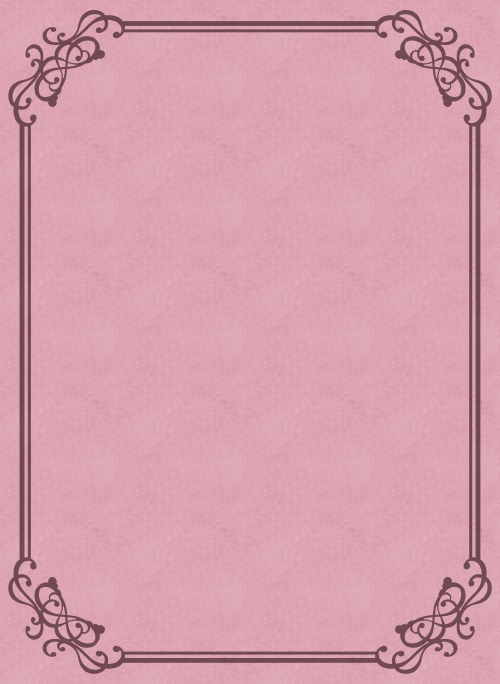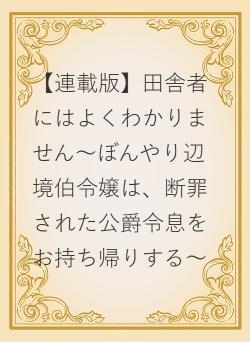颯爽と現れたオルウェン伯爵は、脇目もふらずリナリアの元に駆け付け、母とリナリアを抱きしめた。
「無事か!?」
普段は口数が少なく、気難しそうな父が、こんなに焦っている姿をリナリアは初めて見た。母が「リナリアも私も大丈夫よ。少し落ち着いて」と言うと、父は「良かった……」と、安堵のため息をつく。
そこで、ようやく辺りを見回す余裕ができた父は、王と王妃、そして宰相が騎士に拘束されていることに気がついたようだ。
「いったい何が起こっているのだ? それに、ローレル殿下はなぜリナリアにひざまずいている?」
「お父様……。それは今一番、私が知りたいことです」
リナリアがため息をつくと、今までローレルの豹変に呆然と立ち尽くしていた貴族たちが我に返った。貴族の一人がローレルに向かって果敢にも発言する。
「ローレル陛下! いくら王でも、陛下の発言だけで王族や貴族を罰することはできません! ここは正式に裁判を」
貴族の言葉の途中でローレルが立ち上がったので、発言した貴族はビクッと身体を震わせた。
「裁判? もちろんいいよ。でも、私が証拠もなくこんなことを言い出すとでも思っているの? 完璧な王子と讃えられた私が、裁判に勝てないとでも?」
笑みを浮かべたローレルの冷たい瞳にさらされ、貴族は青くなっている。
「私に意見した貴方は相当な額を脱税しているね。このままじゃ自分の罪まで暴かれると思って焦ったのかな? さっきも言ったけど、私は卒業と同時にこの国を亡ぼすつもりだったんだ。どうして、もう手遅れだと気がつかないのかなぁ? だからこの国はつまらないんだよ」
ローレルは集まっている貴族たちの顔を見渡した。
「私は王城に出入りする貴族の誰がどんな罪を犯しているか、全て調べがついているんだよ。これからは、よく考えてから発言してね」
爽やかなローレルの微笑みとは対照的に、貴族たちの顔は青いを通り越して土気色になっている。
状況が分からず、事の成り行きを見守っていたリナリアの父が不思議そうに「ローレル陛下、だと?」と母に尋ねたので、母が「あとから説明するわ」と耳打ちをした。
ローレルは、騎士たちに先王と前王妃、そして宰相の投獄を命じると、その場に居合わせた貴族達を事情聴取の名目で城に監禁した。
「さぁ、愛おしいリナリアのために、最高に住みやすい国にしないとね!」
心弾ませながらローレルは、その場を去って行った。あとに残されたのは、リナリアの家族とシオンだけだ。
父が「何がなんだか……。だが、君とリナリアが無事で良かったよ」と母に話しかけると、母は「まぁ、安心するのはまだ早いのよね」と言いながらシオンを見た。
「シオン殿下、リナリアの婚約者になるというのは本気ですか?」
父が「なっ!?」と驚きの声を上げる。シオンはすぐに「はい、本気です」と真剣な表情で答えた。
母が「シオン殿下は、王家とオルウェン伯爵家の長年の確執をご存じですよね?」と尋ねた。
「はい、知っています。だからこそ、オルウェンに受け入れてもらえるなら、私はなんでもいたします」
リナリアが「シオン……」と呟くと、父が声を上げた。
「ちょっと待ちなさい! シオン殿下とリナリアが婚約するだと!? そんなことは有り得ない! いったいなんの話だ!」
母が「この二人、付き合っているのよ」と言うと、父は驚きで大きく目を見開いた。
「つき、付き合って?」
「そう、愛しあっているの。リナリアに、シオン殿下と結婚したいと相談されてね、いちおう賛成はできないとは伝えたわ」
「当たり前だ! 賛成する訳がないだろう!? そもそも、リナリアは伯爵家を継ぐ身だぞ。王族のシオン殿下がうちの婿養子に入るわけがないだろう?」
母に「それは、ローレル殿下が王位を継いで、ローレル陛下になられたことで、許可を得られて解決したわ」と教えている。
「ローレル陛下!? いやいや、例えそうだとしても、シオン殿下の評判は最悪だ! オルウェンに受け入れるには……」
また母に「その評判は全てウソだったのよ。それも、ローレル陛下が責任をとって名誉挽回してくださるそうよ」と教えられ、父は少し黙り込んだ。
「いや、それでも私は許さない。王子として育った殿下が、リナリアに寄り添い支えられるとは思えない」
父の反対に会い、シオンはうつむいた。
「そうですよね……。私がリナリアの夫になりたいだなんて、許されることではないですよね……」
リナリアが「シオン」と名前を呼ぶと、シオンは「いいんだよ」と力なく微笑んだ。その言葉を聞いて、胸をなでおろした父を、シオンがまっすぐに見つめた。
「では、私をリナリアの従者にしてください。護衛でもいいです。どうしてもリナリアの側にいたいんです!」
シオンの言葉に父は戸惑いを隠せないようだ。
「いえ、殿下にそこまでは求めておりません。どうかリナリアを諦めてください」
「嫌です、リナリアの側にいれるなら、リナリアの奴隷でもペットでもかまいません!」
「ど、奴隷? は?」
父が助けを求めるように母を見た。
「……で、殿下は、何を言っているんだ?」
「まぁ、いろいろあるのでしょうね。私に言えることは、シオン殿下は絶対にリナリアを裏切らないってことかしら?」
シオンは「リナリアだけじゃありません! この世にリナリアを生み出してくれたお父様とお母様も決して裏切りませんし、この身を一生オルウェン伯爵家の発展に捧げることを誓います。だからどうか」と懇願した。
(シオン……そこまで言ってくれるなんて……)
リナリアは泣きそうになりながら、シオンの手を握った。
「お父様。私からもお願いします。私、シオン以外の男性が気持ち悪いんです。シオン以外と結婚できる気がしません」
父は低く唸りながら「と、とにかく、婚約の件は保留だ!」と言ったが、母に何かを耳打ちされて真っ赤になったあとに咳払いをした。
「う、うむ、そういうことなら二人の婚約を許そう」
「お父様、本当ですか!?」
「ああ」
シオンと見つめ合い微笑み合う。
こうしてリナリアとシオンは、ようやく婚約者になれた。
**
シオンと別れ、オルウェン伯爵家に戻る馬車の中で、リナリアは母にこっそりと尋ねた。
「お母様は、お父様に何を言ったのですか? どうして急にお父様は、婚約を許してくれたのでしょうか?」
「ああ、あれね」
クスッと笑った母は、馬車の横を、馬に乗って並走する父に視線を向けた。
「シオン殿下がリナリアに、毎朝リナリアの花束をくれることを教えてあげたのよ。まるで貴方みたいねって。私は貴方と結婚してとても幸せになれたから、貴方に似ている殿下もリナリアをとても幸せにしてくれるんじゃないかしらって言っただけよ」
「お母様……」
母はリナリアを優しく抱き締めた。抱きしめられると、今さらながらに身体が震えてきて、謁見室の場で起こったことが、とても怖かったのだと気がついた。
「ここまでよく頑張ったわね。リナリア、貴女はとても勇敢だったわ。王家との確執は、私たちの代で終わらせる。だから、貴女は、貴女が愛し、貴女を愛してくれる人と幸せになりなさい」
「……はい」
母の言葉の温かさに涙が滲んだ。
「無事か!?」
普段は口数が少なく、気難しそうな父が、こんなに焦っている姿をリナリアは初めて見た。母が「リナリアも私も大丈夫よ。少し落ち着いて」と言うと、父は「良かった……」と、安堵のため息をつく。
そこで、ようやく辺りを見回す余裕ができた父は、王と王妃、そして宰相が騎士に拘束されていることに気がついたようだ。
「いったい何が起こっているのだ? それに、ローレル殿下はなぜリナリアにひざまずいている?」
「お父様……。それは今一番、私が知りたいことです」
リナリアがため息をつくと、今までローレルの豹変に呆然と立ち尽くしていた貴族たちが我に返った。貴族の一人がローレルに向かって果敢にも発言する。
「ローレル陛下! いくら王でも、陛下の発言だけで王族や貴族を罰することはできません! ここは正式に裁判を」
貴族の言葉の途中でローレルが立ち上がったので、発言した貴族はビクッと身体を震わせた。
「裁判? もちろんいいよ。でも、私が証拠もなくこんなことを言い出すとでも思っているの? 完璧な王子と讃えられた私が、裁判に勝てないとでも?」
笑みを浮かべたローレルの冷たい瞳にさらされ、貴族は青くなっている。
「私に意見した貴方は相当な額を脱税しているね。このままじゃ自分の罪まで暴かれると思って焦ったのかな? さっきも言ったけど、私は卒業と同時にこの国を亡ぼすつもりだったんだ。どうして、もう手遅れだと気がつかないのかなぁ? だからこの国はつまらないんだよ」
ローレルは集まっている貴族たちの顔を見渡した。
「私は王城に出入りする貴族の誰がどんな罪を犯しているか、全て調べがついているんだよ。これからは、よく考えてから発言してね」
爽やかなローレルの微笑みとは対照的に、貴族たちの顔は青いを通り越して土気色になっている。
状況が分からず、事の成り行きを見守っていたリナリアの父が不思議そうに「ローレル陛下、だと?」と母に尋ねたので、母が「あとから説明するわ」と耳打ちをした。
ローレルは、騎士たちに先王と前王妃、そして宰相の投獄を命じると、その場に居合わせた貴族達を事情聴取の名目で城に監禁した。
「さぁ、愛おしいリナリアのために、最高に住みやすい国にしないとね!」
心弾ませながらローレルは、その場を去って行った。あとに残されたのは、リナリアの家族とシオンだけだ。
父が「何がなんだか……。だが、君とリナリアが無事で良かったよ」と母に話しかけると、母は「まぁ、安心するのはまだ早いのよね」と言いながらシオンを見た。
「シオン殿下、リナリアの婚約者になるというのは本気ですか?」
父が「なっ!?」と驚きの声を上げる。シオンはすぐに「はい、本気です」と真剣な表情で答えた。
母が「シオン殿下は、王家とオルウェン伯爵家の長年の確執をご存じですよね?」と尋ねた。
「はい、知っています。だからこそ、オルウェンに受け入れてもらえるなら、私はなんでもいたします」
リナリアが「シオン……」と呟くと、父が声を上げた。
「ちょっと待ちなさい! シオン殿下とリナリアが婚約するだと!? そんなことは有り得ない! いったいなんの話だ!」
母が「この二人、付き合っているのよ」と言うと、父は驚きで大きく目を見開いた。
「つき、付き合って?」
「そう、愛しあっているの。リナリアに、シオン殿下と結婚したいと相談されてね、いちおう賛成はできないとは伝えたわ」
「当たり前だ! 賛成する訳がないだろう!? そもそも、リナリアは伯爵家を継ぐ身だぞ。王族のシオン殿下がうちの婿養子に入るわけがないだろう?」
母に「それは、ローレル殿下が王位を継いで、ローレル陛下になられたことで、許可を得られて解決したわ」と教えている。
「ローレル陛下!? いやいや、例えそうだとしても、シオン殿下の評判は最悪だ! オルウェンに受け入れるには……」
また母に「その評判は全てウソだったのよ。それも、ローレル陛下が責任をとって名誉挽回してくださるそうよ」と教えられ、父は少し黙り込んだ。
「いや、それでも私は許さない。王子として育った殿下が、リナリアに寄り添い支えられるとは思えない」
父の反対に会い、シオンはうつむいた。
「そうですよね……。私がリナリアの夫になりたいだなんて、許されることではないですよね……」
リナリアが「シオン」と名前を呼ぶと、シオンは「いいんだよ」と力なく微笑んだ。その言葉を聞いて、胸をなでおろした父を、シオンがまっすぐに見つめた。
「では、私をリナリアの従者にしてください。護衛でもいいです。どうしてもリナリアの側にいたいんです!」
シオンの言葉に父は戸惑いを隠せないようだ。
「いえ、殿下にそこまでは求めておりません。どうかリナリアを諦めてください」
「嫌です、リナリアの側にいれるなら、リナリアの奴隷でもペットでもかまいません!」
「ど、奴隷? は?」
父が助けを求めるように母を見た。
「……で、殿下は、何を言っているんだ?」
「まぁ、いろいろあるのでしょうね。私に言えることは、シオン殿下は絶対にリナリアを裏切らないってことかしら?」
シオンは「リナリアだけじゃありません! この世にリナリアを生み出してくれたお父様とお母様も決して裏切りませんし、この身を一生オルウェン伯爵家の発展に捧げることを誓います。だからどうか」と懇願した。
(シオン……そこまで言ってくれるなんて……)
リナリアは泣きそうになりながら、シオンの手を握った。
「お父様。私からもお願いします。私、シオン以外の男性が気持ち悪いんです。シオン以外と結婚できる気がしません」
父は低く唸りながら「と、とにかく、婚約の件は保留だ!」と言ったが、母に何かを耳打ちされて真っ赤になったあとに咳払いをした。
「う、うむ、そういうことなら二人の婚約を許そう」
「お父様、本当ですか!?」
「ああ」
シオンと見つめ合い微笑み合う。
こうしてリナリアとシオンは、ようやく婚約者になれた。
**
シオンと別れ、オルウェン伯爵家に戻る馬車の中で、リナリアは母にこっそりと尋ねた。
「お母様は、お父様に何を言ったのですか? どうして急にお父様は、婚約を許してくれたのでしょうか?」
「ああ、あれね」
クスッと笑った母は、馬車の横を、馬に乗って並走する父に視線を向けた。
「シオン殿下がリナリアに、毎朝リナリアの花束をくれることを教えてあげたのよ。まるで貴方みたいねって。私は貴方と結婚してとても幸せになれたから、貴方に似ている殿下もリナリアをとても幸せにしてくれるんじゃないかしらって言っただけよ」
「お母様……」
母はリナリアを優しく抱き締めた。抱きしめられると、今さらながらに身体が震えてきて、謁見室の場で起こったことが、とても怖かったのだと気がついた。
「ここまでよく頑張ったわね。リナリア、貴女はとても勇敢だったわ。王家との確執は、私たちの代で終わらせる。だから、貴女は、貴女が愛し、貴女を愛してくれる人と幸せになりなさい」
「……はい」
母の言葉の温かさに涙が滲んだ。