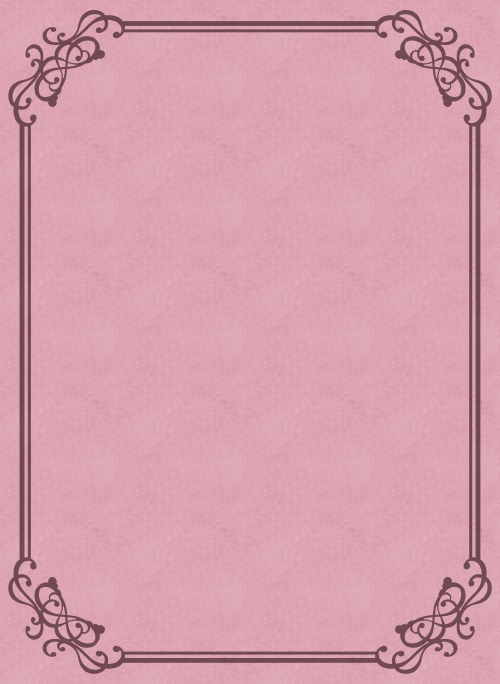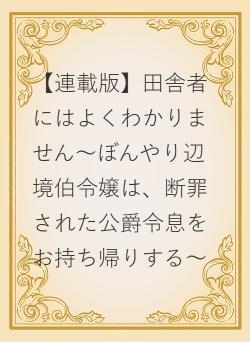それから数日後。
リナリアは王城へ呼び出された。
シオンに事前に「怖いことは起こらないよ。ローレルと私の関係について話すだけだから」と説明を受けていたが、リナリアは、数日前から緊張してしまっていた。
王城は、学園を卒業してから入ることの許される場所なので、今日は付き添いとして母も一緒に来てくれている。
在学中の者は王城内で、制服を着用することが義務付けられているため、リナリアはいつもの制服姿だった。チラリと横を歩く母を見ると、落ち着いた緑のドレスをまとい、凛とした雰囲気で堂々と歩いている。
そんな母を見ていると緊張が薄れた。リナリアは、素直に『私もこんな大人になりたいわ』と思った。
「リナリア、今、アルもこちらに向かっているわ」
「お父様も? お忙しくないんですか?」
「娘が急に陛下に呼びつけられたのに、黙って仕事なんてできる人ではないわ。今ごろ貴女のことが心配すぎて胃が痛くなっているんじゃないかしら?」
「お父様……」
心配をかけてしまい申し訳ないと思いつつ、心配してくれることに感謝する。
前を歩く案内人は、謁見室までリナリアと母を案内した。
(この扉の向こうに陛下が……)
二人かがりで開けられた扉の先には高い壇上があり、その上に王座が見えた
王座に座る王の横には王妃、そして、その左右にはシオンとローレルの姿もある。
母が「行くわよ」と言って、震えるリナリアの手を優しく握ってくれた。
「はい」
謁見室に足を踏み入れると、王族の他にも、見知らぬ貴族たちや、王子の護衛であるゼダやギアムがいることにも気がついた。
母と一緒に王座の前まで歩くと、母は淑女の礼(カーテシー)をとる。リナリアも制服のスカートをすこし摘まむと形だけの礼をした。
「おもてをあげよ」
重厚な王の声で、礼をやめて佇まいを整えた。直接顔をみるのは不敬になると聞いていたので、リナリアは王の足元らへんに目を向ける。
王は「そう怖がらなくて良い」と、リナリアに向けて言ったようだ。
「シオンから話は聞いた。到底信じられることではないが、ローレルのためにも不名誉なウワサが広がる前に、その芽を摘んでおきたい」
王が言っている意味が分からず、リナリアはつい顔を上げてシオンを見た。シオンは口元に笑みを浮かべながら、人差し指を立てて自身の唇に当てる。
(静かにってこと?)
しかし、王の発言は、『集めた証言は信じない。それどころか、その証言はローレルの不名誉なウワサであり、それを消したい』と言っている。
(どういうことなの? ローレルがシオンのふりをして周りを騙していたって分かったはずなのに……)
リナリアが困惑していると、王はさらに言葉を続けた。
「今日、そなたを呼び出したのは、礼を言いたかったからだ。ローレルのために動いてくれたこと、礼を言う」
そう言った王は慈悲深そうな瞳でローレルを見た。王妃も愛おしそうにローレルを見つめながら「わたくしからも礼を言います。ローレルの心が傷つけられなくて良かったわ」と微笑んでいる。
(何これ? ローレルのことばっかり)
王も王妃も、まるでシオンなど初めから存在していないかのような振る舞いだ。シオンはというと、そのことをまったく気にしていないようで、ニコニコと微笑みながらリナリアを見つめている。
隣の母を見ると口元は笑っているが、激しく怒っているのが怖いくらいに伝わってきた。
王が「それで、だ。この度、ローレルを救ってくれたオルウェン令嬢には、褒美にシオンを授けようと思う」と言ったので、母の口から「……褒美、ですか?」といつもよりも低く固い声が出た。
「そうだ。オルウェン令嬢は学園でシオンと付き合っているそうではないか? なら、悪い話ではないだろう? その代わり、この件は黙っていてほしいのだ」
バキッと音がしたかと思うと、母が手に持っていた扇を握り潰していた。
(お、お母様!? 私もものすごく腹が立ちますけど!)
母の怒りが強すぎて、リナリアは逆に冷静になってしまった。
(ようするに、シオンとの結婚を許す代わりに、ローレルが今までしてきたことを黙っていろってことよね? なんて酷い親なの?)
この場にいる貴族たちは、皆、王の意見に賛成のようで、笑みを浮かべながらうなずいている。
リナリアは、シオンの闇が深い理由がなんとなく分かったような気がした。
(シオンが言っていた『ローレルに完璧でいて欲しい人たち』の中に、陛下と王妃様も含まれていたのね)
『自分の両親に助けを求めてもムダだ』と言ったシオンの気持ちを考えると胸が切り裂かれたように痛んだ。
(シオンは、ずっとこんな扱いを受けてきたの?)
シオンは、両親に抗議してもムダだと分かっていたから、集めた証言を利用して陛下と交渉し、王室を除名されずに、リナリアと一緒になれる道を切り開いた。
(確かに、私たちの願いはかなえられたけど、でも、こんなの、私が望んでいたことじゃない!)
王に「どうだ? オルウェン嬢」と声をかけられたので、今まで黙っていたリナリアは口を開いた。
「ローレル殿下、殿下が私に『何を言っても罰しない』と言ってくれた約束は、まだ有効でしょうか?」
今この場で何を考えているのか分からないローレルは、爽やかな笑顔を浮かべながら「もちろんだよ」と言ってくれた。
リナリアは、隣の母に小声で「今から私がすることは、オルウェンに多大なご迷惑をかけるかもしれません」と伝えると、母は「貴女の気の済むようにやりなさい。なにがあっても、私やアルが貴女を助けるわ」と力強く言ってくれた。
小さくうなずいたリナリアは、ローレルを見つめた。
「では、陛下ではなく、ローレル殿下にだけ申し上げます」
リナリアは大きく息を吸った。
「私はローレル殿下のために証言を集めたのではありません! ローレル殿下がシオン殿下のふりをして、シオン殿下を貶めるのをやめていただきたかったのです! だから、ローレル殿下は、シオン殿下に謝ってください! そして、もう二度とシオン殿下のふりをしないと今ここで誓ってください!」
貴族の間から「不敬だ!」と叫び声が上がり、王と王妃は目を吊り上げた。
王が「無礼者を捕えよ!」と叫ぶと、謁見室の両端に控えていた騎士たちが反応したが、それより早くゼダとギアムが動き、リナリアを守るように取り囲んだ。
ギアムが「リナリア嬢は、ローレル殿下から『何を言っても不敬に問わない』という許可を得ています。証人は俺です」と言うと、王は「どういうことだ!?」と動揺する。
ざわつく謁見室の中に、ローレルの良く通る声が響いた。
「そのままの意味ですよ。良いんです」
王や王妃を含めた貴族たちが一斉にローレルを見た。視線の先でローレルは爽やかに微笑んでいる。
「リナリアだけは、私に何を言っても良いんですよ。ね?」
ローレルに微笑みかえられ、リナリアは眉をひそめた。
(いったい何を考えているの?)
ローレルはにこやかに王に語りかけた。
「それはそうと、父上、以前から一刻も早く、私に王位を譲りたいと言っていましたね?」
「ああ、ローレルになら今すぐにでも王位を譲ってやろう」
「では、今すぐに、私に王位を譲ってください」
驚きに目を見開いた王は、それまでとは打って変わり、顔をほころばせた。
「ようやく決心してくれたか! よいよい、今すぐにでも王位を譲ろう」
王が指示すると、すぐに侍従が仰々しい巻物を運んできた。それを受け取った王は、「ローレルよ。ここに署名しなさい。戴冠の儀などはあとで行おう」と嬉しそうだ。
ローレルもニコニコしながら巻物にペンを走らせた。
王が巻物を皆に見えるように掲げると、貴族たちは「ローレル王の誕生だ!」と喜んだ。
王が立ち上がり開けた玉座にローレルが座った。たった今、王になったばかりなのに、その貫禄に圧倒されてしまう。
王妃も「これでこの国は安泰です」と涙ぐんでいる。
気がつけば、シオンがリナリアの側に来ていた。
「シオン……」
シオンはとても嬉しそうに「ね? リナリアの願いは全て叶ったよ」と微笑む。その笑顔を見ると、リナリアは涙が溢れた。
「そう、だけど……そうじゃないわ」
「どうしたの? リナリア」
「だって、こんなの、ひどい……」
シオンは「でも、私は王室を除名されずにリナリアと結婚できるし、ローレルにはもう利用されずに済むよ。これじゃあダメだった?」と悲しそうな顔をしている。
「そうだけど……」
王や王妃がシオンの敵であるこの状態で、じゃあ、どうすれば良かったのかと聞かれれば、リナリアは答えることができない。
ローレルを讃える貴族たちが「ローレル陛下、何かお言葉を!」と言ったので、ローレルは玉座から立ち上がった。
「私は学園を卒業と同時に、このつまらない国を滅ぼしてやろうと決めていたが、リナリアのおかげで真実の愛に目覚めた。よって、今からこの国をより良くするための政策を行使する」
王や王妃、貴族たちがそろってポカンと口を開いた。しかし、それ以上にリナリアと、リナリアの母、そして、シオンが驚いた。
水を打ったような静けさの中、ローレルの声が響く。
「まず、私の父である、先王は絶対的な支持を得ている私に王位を譲り、周辺諸国へ戦をしかけ侵略し、王国を帝国にすることを計画していた。私の愛おしいリナリアの住まう国の平和を乱す王族は見過ごせない。よって死刑」
先王の顔から血の気が引いたが、誰も口を開かない。
「そして、母である前王妃は、現宰相と不義の関係にある。一夫一妻制のこの国で、婚姻後に夫以外の男と密通することは重罪だ。かつ、私以外に前王妃の血を継ぐ子どもが生まれる可能性を作り出すことは、私に対する反逆である。それは、愛おしいリナリアの未来を脅かすことでもある。よって死刑」
前王妃は真っ青になりながら、口をパクパクと動かした。
「前王妃と密通した宰相は、母の力を利用し、自分の娘を私の妃にあてがい、より多くの権力を得ようとしていたため、この場で宰相の任を解く。そして、死刑」
宰相がガタガタと震え、その場から逃げ出そうとしたので、ローレルが「捕えよ」と言うと、騎士たちが一斉に宰相を拘束した。
「この国を住みやすい国にするには、たくさんの愚か者を処罰しないといけないけど、今日はこのへんでやめようか」
先王が「ローレル……お前は、いったいどうしてしまったのだ?」と震える声で尋ねた。
前王妃が「そうです。貴方は慈悲深く、優秀で誰よりも完璧だったのに……」と泣き崩れる。
「完璧な人間などいる訳ないでしょう? 貴方たちは都合よく私に幻想を重ねていただけ。私はそれを利用して、好き勝手生きてきただけのこと。それに、もし私が完璧だというなら、私を生んだ両親である貴方たちも完璧であるべきでは?」
前王妃は「そんな……あんなにも貴方を愛してあげたのに……」と泣き崩れる。
「母上、貴女は確かに私を溺愛してくれました。でも、貴女の息子はもう一人いたでしょう? シオンを無視した貴女は、母として失格、そして、夫以外の男に抱かれた貴女は妻としても最低なのですよ。そんな女から、完璧な王子が生まれるわけがないでしょう?」
ローレルはとても楽しそうだ。
「あ、そうそう。シオンやリナリアが集めた証言は全て本当ですよ。私はずっとシオンのふりをして、暴力をふるったり、女遊びをしたりしていました」
玉座から降りたローレルは、シオンに向かって深く頭を下げた。
「シオン、今まですまなかった。許してくれとは言わないし、別に許してほしいとも思わない。ただ、リナリアが君に謝ってほしいというから謝るよ。シオンの名誉は必ず回復させる。それに、面倒でつまらない王位は私が引き受けてあげるよ。これからはシオンの好きなように生きてくれ。私は全力でそれを応援するから」
ローレルの謝罪を聞いたシオンは、なんの感情も動かなかったようで淡々と返した。
「ローレル、君の謝罪なんて何の価値も意味もない。それに、私は私の名誉の回復なんてどうでもいいけど、このままじゃリナリアが悲しむから、ぜひそうしてほしい。あと、このクソみたいな王位を引き受けてくれてありがとう。私は今、生まれて初めてローレルが兄で良かったと思ったよ」
息子たちの会話を聞いた前王妃は「ウソよ!」と気が狂ったように叫んだ。
「ローレル、貴方は完璧なの! そんなことをするはずがないわ! シオン……そうよ、シオンが全て悪いのよ!」
シオンにつかみかかろうとした前王妃は、ギアムにすばやく取り押さえられた。その光景をみたローレルは楽しそうに口端を上げる。
「母上、信じなくても結構です。私は性格がとても悪いので、これからはシオンの代わりに父上と母上で遊びますね。お二人が『早く処刑してくれ』と泣いて叫ぶまで、一緒に遊んであげますよ」
先王と前王妃がそろって青ざめたので、リナリアは『この二人、やっぱりシオンがローレルに酷い目にあわされていたことを知っていたんだわ。知っていた上で、気がつかないふりをしていたのね』と確信した。
シオンは、「ローレル」と低い声でローレルを呼んだ。
「なんだい? シオン」
「さっきから黙って聞いていれば、『真実の愛に目覚めた』だの、『愛しいリナリア』だのと、聞き捨てならない」
「ああ、そのこと?」
ローレルは、少しも悪びれない。
殺気立つシオンが「もし、私からリナリアを奪おうと言うなら……」と言う言葉をローレルはさえぎった。
「心配しないで。私のリナリアへの想いは、そういうのじゃないから」
驚くシオンを無視して、ローレルはリナリアにひざまずいた。
「リナリア、私にとっては、君だけが特別で、それ以外はどうでも良いその他大勢なんだ。これって、私がリナリアのことが好きってことだよね?」
その言葉は、確かに前にリナリアがローレルに言ったことだった。リナリアが顔をしかめながら言葉に詰まっていると、ローレルはうっとりとため息をついた。
「ああっ、リナリア! やっぱり君は最高だよ。お願いだから、一生私を嫌って気持ち悪がっていてね。それができるのは、君だけだから。特別な君だけが、私を王ではないただの男にしてくれる」
意味不明なことを熱烈に言われ、リナリアはつい「……気持ち悪っ」と呟いてしまった。その言葉にローレルがとても喜んだとき、勢いよく謁見室の扉が開いて、リナリアの父であるオルウェン伯爵が現れた。
リナリアは王城へ呼び出された。
シオンに事前に「怖いことは起こらないよ。ローレルと私の関係について話すだけだから」と説明を受けていたが、リナリアは、数日前から緊張してしまっていた。
王城は、学園を卒業してから入ることの許される場所なので、今日は付き添いとして母も一緒に来てくれている。
在学中の者は王城内で、制服を着用することが義務付けられているため、リナリアはいつもの制服姿だった。チラリと横を歩く母を見ると、落ち着いた緑のドレスをまとい、凛とした雰囲気で堂々と歩いている。
そんな母を見ていると緊張が薄れた。リナリアは、素直に『私もこんな大人になりたいわ』と思った。
「リナリア、今、アルもこちらに向かっているわ」
「お父様も? お忙しくないんですか?」
「娘が急に陛下に呼びつけられたのに、黙って仕事なんてできる人ではないわ。今ごろ貴女のことが心配すぎて胃が痛くなっているんじゃないかしら?」
「お父様……」
心配をかけてしまい申し訳ないと思いつつ、心配してくれることに感謝する。
前を歩く案内人は、謁見室までリナリアと母を案内した。
(この扉の向こうに陛下が……)
二人かがりで開けられた扉の先には高い壇上があり、その上に王座が見えた
王座に座る王の横には王妃、そして、その左右にはシオンとローレルの姿もある。
母が「行くわよ」と言って、震えるリナリアの手を優しく握ってくれた。
「はい」
謁見室に足を踏み入れると、王族の他にも、見知らぬ貴族たちや、王子の護衛であるゼダやギアムがいることにも気がついた。
母と一緒に王座の前まで歩くと、母は淑女の礼(カーテシー)をとる。リナリアも制服のスカートをすこし摘まむと形だけの礼をした。
「おもてをあげよ」
重厚な王の声で、礼をやめて佇まいを整えた。直接顔をみるのは不敬になると聞いていたので、リナリアは王の足元らへんに目を向ける。
王は「そう怖がらなくて良い」と、リナリアに向けて言ったようだ。
「シオンから話は聞いた。到底信じられることではないが、ローレルのためにも不名誉なウワサが広がる前に、その芽を摘んでおきたい」
王が言っている意味が分からず、リナリアはつい顔を上げてシオンを見た。シオンは口元に笑みを浮かべながら、人差し指を立てて自身の唇に当てる。
(静かにってこと?)
しかし、王の発言は、『集めた証言は信じない。それどころか、その証言はローレルの不名誉なウワサであり、それを消したい』と言っている。
(どういうことなの? ローレルがシオンのふりをして周りを騙していたって分かったはずなのに……)
リナリアが困惑していると、王はさらに言葉を続けた。
「今日、そなたを呼び出したのは、礼を言いたかったからだ。ローレルのために動いてくれたこと、礼を言う」
そう言った王は慈悲深そうな瞳でローレルを見た。王妃も愛おしそうにローレルを見つめながら「わたくしからも礼を言います。ローレルの心が傷つけられなくて良かったわ」と微笑んでいる。
(何これ? ローレルのことばっかり)
王も王妃も、まるでシオンなど初めから存在していないかのような振る舞いだ。シオンはというと、そのことをまったく気にしていないようで、ニコニコと微笑みながらリナリアを見つめている。
隣の母を見ると口元は笑っているが、激しく怒っているのが怖いくらいに伝わってきた。
王が「それで、だ。この度、ローレルを救ってくれたオルウェン令嬢には、褒美にシオンを授けようと思う」と言ったので、母の口から「……褒美、ですか?」といつもよりも低く固い声が出た。
「そうだ。オルウェン令嬢は学園でシオンと付き合っているそうではないか? なら、悪い話ではないだろう? その代わり、この件は黙っていてほしいのだ」
バキッと音がしたかと思うと、母が手に持っていた扇を握り潰していた。
(お、お母様!? 私もものすごく腹が立ちますけど!)
母の怒りが強すぎて、リナリアは逆に冷静になってしまった。
(ようするに、シオンとの結婚を許す代わりに、ローレルが今までしてきたことを黙っていろってことよね? なんて酷い親なの?)
この場にいる貴族たちは、皆、王の意見に賛成のようで、笑みを浮かべながらうなずいている。
リナリアは、シオンの闇が深い理由がなんとなく分かったような気がした。
(シオンが言っていた『ローレルに完璧でいて欲しい人たち』の中に、陛下と王妃様も含まれていたのね)
『自分の両親に助けを求めてもムダだ』と言ったシオンの気持ちを考えると胸が切り裂かれたように痛んだ。
(シオンは、ずっとこんな扱いを受けてきたの?)
シオンは、両親に抗議してもムダだと分かっていたから、集めた証言を利用して陛下と交渉し、王室を除名されずに、リナリアと一緒になれる道を切り開いた。
(確かに、私たちの願いはかなえられたけど、でも、こんなの、私が望んでいたことじゃない!)
王に「どうだ? オルウェン嬢」と声をかけられたので、今まで黙っていたリナリアは口を開いた。
「ローレル殿下、殿下が私に『何を言っても罰しない』と言ってくれた約束は、まだ有効でしょうか?」
今この場で何を考えているのか分からないローレルは、爽やかな笑顔を浮かべながら「もちろんだよ」と言ってくれた。
リナリアは、隣の母に小声で「今から私がすることは、オルウェンに多大なご迷惑をかけるかもしれません」と伝えると、母は「貴女の気の済むようにやりなさい。なにがあっても、私やアルが貴女を助けるわ」と力強く言ってくれた。
小さくうなずいたリナリアは、ローレルを見つめた。
「では、陛下ではなく、ローレル殿下にだけ申し上げます」
リナリアは大きく息を吸った。
「私はローレル殿下のために証言を集めたのではありません! ローレル殿下がシオン殿下のふりをして、シオン殿下を貶めるのをやめていただきたかったのです! だから、ローレル殿下は、シオン殿下に謝ってください! そして、もう二度とシオン殿下のふりをしないと今ここで誓ってください!」
貴族の間から「不敬だ!」と叫び声が上がり、王と王妃は目を吊り上げた。
王が「無礼者を捕えよ!」と叫ぶと、謁見室の両端に控えていた騎士たちが反応したが、それより早くゼダとギアムが動き、リナリアを守るように取り囲んだ。
ギアムが「リナリア嬢は、ローレル殿下から『何を言っても不敬に問わない』という許可を得ています。証人は俺です」と言うと、王は「どういうことだ!?」と動揺する。
ざわつく謁見室の中に、ローレルの良く通る声が響いた。
「そのままの意味ですよ。良いんです」
王や王妃を含めた貴族たちが一斉にローレルを見た。視線の先でローレルは爽やかに微笑んでいる。
「リナリアだけは、私に何を言っても良いんですよ。ね?」
ローレルに微笑みかえられ、リナリアは眉をひそめた。
(いったい何を考えているの?)
ローレルはにこやかに王に語りかけた。
「それはそうと、父上、以前から一刻も早く、私に王位を譲りたいと言っていましたね?」
「ああ、ローレルになら今すぐにでも王位を譲ってやろう」
「では、今すぐに、私に王位を譲ってください」
驚きに目を見開いた王は、それまでとは打って変わり、顔をほころばせた。
「ようやく決心してくれたか! よいよい、今すぐにでも王位を譲ろう」
王が指示すると、すぐに侍従が仰々しい巻物を運んできた。それを受け取った王は、「ローレルよ。ここに署名しなさい。戴冠の儀などはあとで行おう」と嬉しそうだ。
ローレルもニコニコしながら巻物にペンを走らせた。
王が巻物を皆に見えるように掲げると、貴族たちは「ローレル王の誕生だ!」と喜んだ。
王が立ち上がり開けた玉座にローレルが座った。たった今、王になったばかりなのに、その貫禄に圧倒されてしまう。
王妃も「これでこの国は安泰です」と涙ぐんでいる。
気がつけば、シオンがリナリアの側に来ていた。
「シオン……」
シオンはとても嬉しそうに「ね? リナリアの願いは全て叶ったよ」と微笑む。その笑顔を見ると、リナリアは涙が溢れた。
「そう、だけど……そうじゃないわ」
「どうしたの? リナリア」
「だって、こんなの、ひどい……」
シオンは「でも、私は王室を除名されずにリナリアと結婚できるし、ローレルにはもう利用されずに済むよ。これじゃあダメだった?」と悲しそうな顔をしている。
「そうだけど……」
王や王妃がシオンの敵であるこの状態で、じゃあ、どうすれば良かったのかと聞かれれば、リナリアは答えることができない。
ローレルを讃える貴族たちが「ローレル陛下、何かお言葉を!」と言ったので、ローレルは玉座から立ち上がった。
「私は学園を卒業と同時に、このつまらない国を滅ぼしてやろうと決めていたが、リナリアのおかげで真実の愛に目覚めた。よって、今からこの国をより良くするための政策を行使する」
王や王妃、貴族たちがそろってポカンと口を開いた。しかし、それ以上にリナリアと、リナリアの母、そして、シオンが驚いた。
水を打ったような静けさの中、ローレルの声が響く。
「まず、私の父である、先王は絶対的な支持を得ている私に王位を譲り、周辺諸国へ戦をしかけ侵略し、王国を帝国にすることを計画していた。私の愛おしいリナリアの住まう国の平和を乱す王族は見過ごせない。よって死刑」
先王の顔から血の気が引いたが、誰も口を開かない。
「そして、母である前王妃は、現宰相と不義の関係にある。一夫一妻制のこの国で、婚姻後に夫以外の男と密通することは重罪だ。かつ、私以外に前王妃の血を継ぐ子どもが生まれる可能性を作り出すことは、私に対する反逆である。それは、愛おしいリナリアの未来を脅かすことでもある。よって死刑」
前王妃は真っ青になりながら、口をパクパクと動かした。
「前王妃と密通した宰相は、母の力を利用し、自分の娘を私の妃にあてがい、より多くの権力を得ようとしていたため、この場で宰相の任を解く。そして、死刑」
宰相がガタガタと震え、その場から逃げ出そうとしたので、ローレルが「捕えよ」と言うと、騎士たちが一斉に宰相を拘束した。
「この国を住みやすい国にするには、たくさんの愚か者を処罰しないといけないけど、今日はこのへんでやめようか」
先王が「ローレル……お前は、いったいどうしてしまったのだ?」と震える声で尋ねた。
前王妃が「そうです。貴方は慈悲深く、優秀で誰よりも完璧だったのに……」と泣き崩れる。
「完璧な人間などいる訳ないでしょう? 貴方たちは都合よく私に幻想を重ねていただけ。私はそれを利用して、好き勝手生きてきただけのこと。それに、もし私が完璧だというなら、私を生んだ両親である貴方たちも完璧であるべきでは?」
前王妃は「そんな……あんなにも貴方を愛してあげたのに……」と泣き崩れる。
「母上、貴女は確かに私を溺愛してくれました。でも、貴女の息子はもう一人いたでしょう? シオンを無視した貴女は、母として失格、そして、夫以外の男に抱かれた貴女は妻としても最低なのですよ。そんな女から、完璧な王子が生まれるわけがないでしょう?」
ローレルはとても楽しそうだ。
「あ、そうそう。シオンやリナリアが集めた証言は全て本当ですよ。私はずっとシオンのふりをして、暴力をふるったり、女遊びをしたりしていました」
玉座から降りたローレルは、シオンに向かって深く頭を下げた。
「シオン、今まですまなかった。許してくれとは言わないし、別に許してほしいとも思わない。ただ、リナリアが君に謝ってほしいというから謝るよ。シオンの名誉は必ず回復させる。それに、面倒でつまらない王位は私が引き受けてあげるよ。これからはシオンの好きなように生きてくれ。私は全力でそれを応援するから」
ローレルの謝罪を聞いたシオンは、なんの感情も動かなかったようで淡々と返した。
「ローレル、君の謝罪なんて何の価値も意味もない。それに、私は私の名誉の回復なんてどうでもいいけど、このままじゃリナリアが悲しむから、ぜひそうしてほしい。あと、このクソみたいな王位を引き受けてくれてありがとう。私は今、生まれて初めてローレルが兄で良かったと思ったよ」
息子たちの会話を聞いた前王妃は「ウソよ!」と気が狂ったように叫んだ。
「ローレル、貴方は完璧なの! そんなことをするはずがないわ! シオン……そうよ、シオンが全て悪いのよ!」
シオンにつかみかかろうとした前王妃は、ギアムにすばやく取り押さえられた。その光景をみたローレルは楽しそうに口端を上げる。
「母上、信じなくても結構です。私は性格がとても悪いので、これからはシオンの代わりに父上と母上で遊びますね。お二人が『早く処刑してくれ』と泣いて叫ぶまで、一緒に遊んであげますよ」
先王と前王妃がそろって青ざめたので、リナリアは『この二人、やっぱりシオンがローレルに酷い目にあわされていたことを知っていたんだわ。知っていた上で、気がつかないふりをしていたのね』と確信した。
シオンは、「ローレル」と低い声でローレルを呼んだ。
「なんだい? シオン」
「さっきから黙って聞いていれば、『真実の愛に目覚めた』だの、『愛しいリナリア』だのと、聞き捨てならない」
「ああ、そのこと?」
ローレルは、少しも悪びれない。
殺気立つシオンが「もし、私からリナリアを奪おうと言うなら……」と言う言葉をローレルはさえぎった。
「心配しないで。私のリナリアへの想いは、そういうのじゃないから」
驚くシオンを無視して、ローレルはリナリアにひざまずいた。
「リナリア、私にとっては、君だけが特別で、それ以外はどうでも良いその他大勢なんだ。これって、私がリナリアのことが好きってことだよね?」
その言葉は、確かに前にリナリアがローレルに言ったことだった。リナリアが顔をしかめながら言葉に詰まっていると、ローレルはうっとりとため息をついた。
「ああっ、リナリア! やっぱり君は最高だよ。お願いだから、一生私を嫌って気持ち悪がっていてね。それができるのは、君だけだから。特別な君だけが、私を王ではないただの男にしてくれる」
意味不明なことを熱烈に言われ、リナリアはつい「……気持ち悪っ」と呟いてしまった。その言葉にローレルがとても喜んだとき、勢いよく謁見室の扉が開いて、リナリアの父であるオルウェン伯爵が現れた。