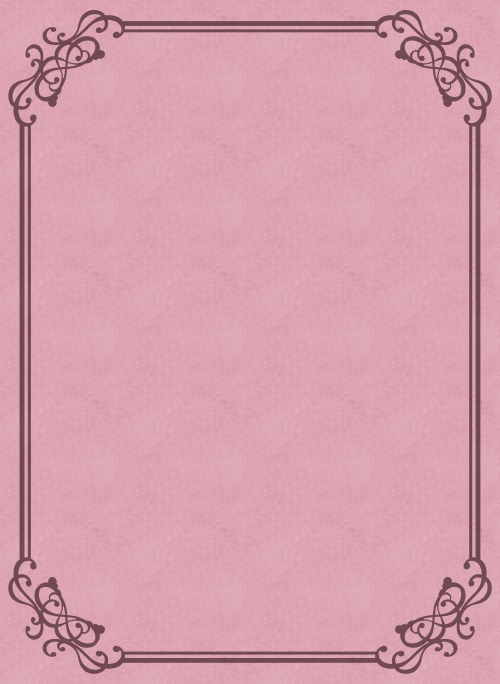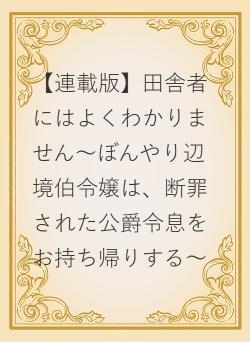走って息があがってしまったリナリアは、シオンが待つサロンの扉の前で呼吸を整えた。扉をノックすると、すぐに扉が開いて中に招き入れられる。
ニコッと微笑んだシオンは、すぐにリナリアに「何かあったの?」と尋ねてきた。
「何もないですよ?」
「でも……」
シオンの長く美しい指がリナリアの髪にふれる。
「髪が少し乱れているし、うっすら汗もかいている」
言われてみれば少し汗ばんでしまっていた。そのとたんに、リナリアは自分の姿が恥ずかしくなった。
(髪も整えず、汗臭い女ってシオンに思われた!? 嫌われたらどうしよう……)
これも全てローレルのせいだと半泣きになっていると、シオンはニッコリと微笑む。
「ねぇ、私を誘っているの?」
「え?」
「そうじゃないなら、そんなに可愛い顔をしないで」
シオンの整い過ぎた顔が近づいてきたかと思うと、リナリアのまぶたの上に口づけし離れていく。
(嫌われたわけじゃないみたい)
ホッと胸をなでおろすと、リナリアは手に持っていた紙束のこと思い出した。シオンはいつものようにお茶を淹れてくれている。
「シオン、前に言っていたローレルとシオンの違いですが、けっこう集まりましたよ」
お茶うけにお菓子まで準備してくれているシオンに近づき、リナリアは紙束をシオンに見せた。シオンは準備の手を止めることなく、リナリアがめくる紙束に目を通す。
「へぇ、私とローレルって意外と違いがあるんだね」
そこには、ローレルの指の付け根にある小さなホクロから、「この髪型をしていたらほめていただけたから、殿下はこの髪型が好き」まで、本当にささいなことが、たくさん書かれている。
「ケイトとゼダ様がどういう説明をしたのか分かりませんが、元恋人さん達は、『自分の証言が正しい』という署名まで書いてくれています」
シオンと付き合っていたつもりの女生徒たちに、『貴方が付き合っていたのはローレルですよ! 一緒にローレル殿下に抗議しましょう!』とは言っても信じてもらえないので、そこらへんはケイトとゼダで口裏を合わせてうまくやったのだろう。
(本当にケイトって優秀よね)
友達の新たな才能が知れて、リナリアは自分のことのように嬉しくなった。
顔に出ていたのか、シオンは「嬉しそうだね。リナリアが嬉しいと私も嬉しいよ」と微笑んでくれる。
「私もシオンが嬉しいと嬉しいですよ。だから、この証言を使って、ローレル殿下に抗議しましょう!」
「それはいいけど……結果は、あまり期待しないほうがいいよ」
シオンの紫水晶のように美しい瞳にかげりが見えた。
「リナリアの気持ちは嬉しいけど、もし、この証言でローレルに抗議しても、ローレルに完璧であってほしい人達に揉み消されると思うんだ」
「そんな……じゃあ、学園に抗議文を提出しますか?」
あきらめたように笑うシオンを見て、意味がないのだと分かった。
「では、陛下や王妃様に訴えてみては? これだけ証言があるのですから、すぐには信じてもらえなくても、真実を調べてはくださるでしょう?」
シオンは少し考えるそぶりをしたあとに、「ああ、そうか……これは交渉材料に使えるかもしれない」とまるで独り言のように呟いた。
「リナリアが思っているようなことではないけど、その案は良いと思う。この件、私に任せてくれないかな?」
「もちろんです!」
元からシオンの悪評を消したくて集めた証拠なので、シオンがやりたいことに使ってもらえるならそれがいい。リナリアは、お茶を淹れ終わったシオンに紙束を手渡した。
「ありがとう、リナリア」
にこやかに微笑むシオンは、なぜかお茶うけのクッキーを手に持ちながら「はい、あーん」と言ってくる。
「え?」
「あーんして、リナリア」
「え? いえ、え?」
突然の展開にリナリアが驚いていると、シオンは悲しそうに形の良い眉を下げた。
「リナリアは、クッキーは嫌い?」
「いえ、大好きですよ」
「じゃあ、私のことが嫌いなの?」
「いえ、大好きですよ!?」
シオンの言葉を慌てて否定すると、シオンは「良かった。じゃあ、はい、あーん」とリナリアの口元にクッキーを近づける。
「私とクッキーが大好きなら、食べてくれるよね?」
「あ、えっと、そういう問題ですか……?」
「そういう問題だよ」
なんだかうまく丸め込まれているような気がしたが、覚悟を決めたリナリアがクッキーを一口かじると、シオンは「どう? おいしい?」と不安そうに聞いてきた。
(恥ずかしすぎて、味なんて分からないわ……)
それでも「おいしいです」と答えるとシオンはホッと胸をなでおろす。
「良かった。リナリアのために私が作ったクッキーを気に入ってもらえて」
「これ、シオンが作ったんですか!?」
シオンは恥ずかしそうに「そうだよ」と微笑んでいる。
「シオンって……なんでもできるんですね……」
心の底から感心しているとシオンは、リナリアがかじったクッキーをパクリと食べた。
「あ!」
「どうかした?」
「いや、だって今……」
リナリアは『そのクッキー、私の食べかけですよ?』と言おうとした。
(でもシオンが気にしていないのに、私が気にするのは変よね? 自意識過剰だって思われたら嫌だし、もう食べちゃったあとだし)
悩んだ結果「いえ、なんでもないです」と誤魔化した。
「そう?」
シオンがクッキーの粉がついた指をペロリとなめたので、リナリアは慌てて視線をそらした。
(シオンの色気や色っぽいしぐさにもだいぶ慣れてきたつもりだったけど、私もまだまだね)
早鐘を打つ胸を抑えながら、リナリアは小さくため息をついた。
ニコッと微笑んだシオンは、すぐにリナリアに「何かあったの?」と尋ねてきた。
「何もないですよ?」
「でも……」
シオンの長く美しい指がリナリアの髪にふれる。
「髪が少し乱れているし、うっすら汗もかいている」
言われてみれば少し汗ばんでしまっていた。そのとたんに、リナリアは自分の姿が恥ずかしくなった。
(髪も整えず、汗臭い女ってシオンに思われた!? 嫌われたらどうしよう……)
これも全てローレルのせいだと半泣きになっていると、シオンはニッコリと微笑む。
「ねぇ、私を誘っているの?」
「え?」
「そうじゃないなら、そんなに可愛い顔をしないで」
シオンの整い過ぎた顔が近づいてきたかと思うと、リナリアのまぶたの上に口づけし離れていく。
(嫌われたわけじゃないみたい)
ホッと胸をなでおろすと、リナリアは手に持っていた紙束のこと思い出した。シオンはいつものようにお茶を淹れてくれている。
「シオン、前に言っていたローレルとシオンの違いですが、けっこう集まりましたよ」
お茶うけにお菓子まで準備してくれているシオンに近づき、リナリアは紙束をシオンに見せた。シオンは準備の手を止めることなく、リナリアがめくる紙束に目を通す。
「へぇ、私とローレルって意外と違いがあるんだね」
そこには、ローレルの指の付け根にある小さなホクロから、「この髪型をしていたらほめていただけたから、殿下はこの髪型が好き」まで、本当にささいなことが、たくさん書かれている。
「ケイトとゼダ様がどういう説明をしたのか分かりませんが、元恋人さん達は、『自分の証言が正しい』という署名まで書いてくれています」
シオンと付き合っていたつもりの女生徒たちに、『貴方が付き合っていたのはローレルですよ! 一緒にローレル殿下に抗議しましょう!』とは言っても信じてもらえないので、そこらへんはケイトとゼダで口裏を合わせてうまくやったのだろう。
(本当にケイトって優秀よね)
友達の新たな才能が知れて、リナリアは自分のことのように嬉しくなった。
顔に出ていたのか、シオンは「嬉しそうだね。リナリアが嬉しいと私も嬉しいよ」と微笑んでくれる。
「私もシオンが嬉しいと嬉しいですよ。だから、この証言を使って、ローレル殿下に抗議しましょう!」
「それはいいけど……結果は、あまり期待しないほうがいいよ」
シオンの紫水晶のように美しい瞳にかげりが見えた。
「リナリアの気持ちは嬉しいけど、もし、この証言でローレルに抗議しても、ローレルに完璧であってほしい人達に揉み消されると思うんだ」
「そんな……じゃあ、学園に抗議文を提出しますか?」
あきらめたように笑うシオンを見て、意味がないのだと分かった。
「では、陛下や王妃様に訴えてみては? これだけ証言があるのですから、すぐには信じてもらえなくても、真実を調べてはくださるでしょう?」
シオンは少し考えるそぶりをしたあとに、「ああ、そうか……これは交渉材料に使えるかもしれない」とまるで独り言のように呟いた。
「リナリアが思っているようなことではないけど、その案は良いと思う。この件、私に任せてくれないかな?」
「もちろんです!」
元からシオンの悪評を消したくて集めた証拠なので、シオンがやりたいことに使ってもらえるならそれがいい。リナリアは、お茶を淹れ終わったシオンに紙束を手渡した。
「ありがとう、リナリア」
にこやかに微笑むシオンは、なぜかお茶うけのクッキーを手に持ちながら「はい、あーん」と言ってくる。
「え?」
「あーんして、リナリア」
「え? いえ、え?」
突然の展開にリナリアが驚いていると、シオンは悲しそうに形の良い眉を下げた。
「リナリアは、クッキーは嫌い?」
「いえ、大好きですよ」
「じゃあ、私のことが嫌いなの?」
「いえ、大好きですよ!?」
シオンの言葉を慌てて否定すると、シオンは「良かった。じゃあ、はい、あーん」とリナリアの口元にクッキーを近づける。
「私とクッキーが大好きなら、食べてくれるよね?」
「あ、えっと、そういう問題ですか……?」
「そういう問題だよ」
なんだかうまく丸め込まれているような気がしたが、覚悟を決めたリナリアがクッキーを一口かじると、シオンは「どう? おいしい?」と不安そうに聞いてきた。
(恥ずかしすぎて、味なんて分からないわ……)
それでも「おいしいです」と答えるとシオンはホッと胸をなでおろす。
「良かった。リナリアのために私が作ったクッキーを気に入ってもらえて」
「これ、シオンが作ったんですか!?」
シオンは恥ずかしそうに「そうだよ」と微笑んでいる。
「シオンって……なんでもできるんですね……」
心の底から感心しているとシオンは、リナリアがかじったクッキーをパクリと食べた。
「あ!」
「どうかした?」
「いや、だって今……」
リナリアは『そのクッキー、私の食べかけですよ?』と言おうとした。
(でもシオンが気にしていないのに、私が気にするのは変よね? 自意識過剰だって思われたら嫌だし、もう食べちゃったあとだし)
悩んだ結果「いえ、なんでもないです」と誤魔化した。
「そう?」
シオンがクッキーの粉がついた指をペロリとなめたので、リナリアは慌てて視線をそらした。
(シオンの色気や色っぽいしぐさにもだいぶ慣れてきたつもりだったけど、私もまだまだね)
早鐘を打つ胸を抑えながら、リナリアは小さくため息をついた。