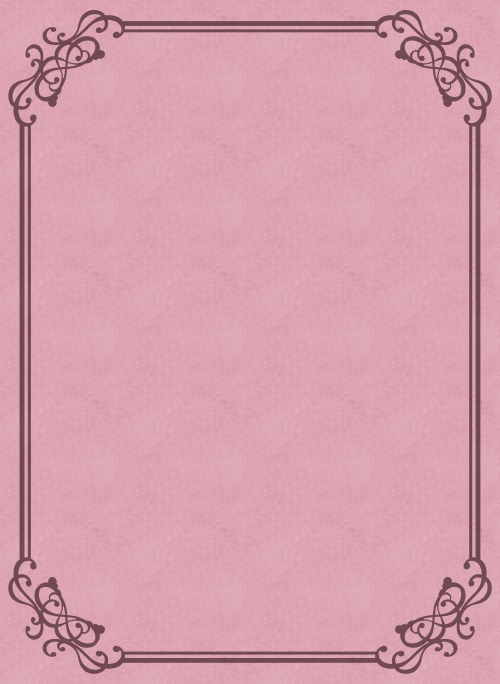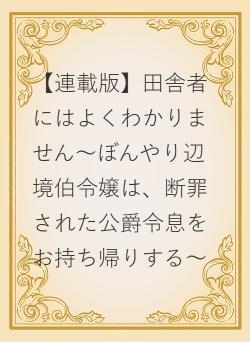ギアムに「俺に何をさせたいんですか?」と聞かれ、リナリアは小さく首を左右に振った。
「ギアム様に、何かをしてもらいたいというよりは何もせずに、私がすることを見逃して欲しいんです」
「ふーん? じゃあ、分かりました。これからお嬢さんがすることは、俺は何も見ていないということで」
「あ、え、はい……」
あっさりと受け入れられ、逆にリナリアのほうが戸惑ってしまう。
「あの、明日にでも正式にセリー商会と契約を……」
「いや、いりませんよ。もし、お嬢さんが俺を裏切ったら、セリー商会に、それ相応の対応をするだけですから」
ギアムの余裕な態度は、自分が圧倒的強者だと物語っている。契約や身分は、容赦のない暴力の前では、時に無意味なのかもしれない。
リナリアは、ふと『もし今が戦乱の時代なら、ギアム様は英雄と呼ばれていたのかも』と思った。
「もちろん、私もセリー商会もギアム様を裏切りません」
「そうあることを願います。こちらからの条件ですが、お嬢さんの用事が終わったら、俺を死んだことにしてください」
「え?」
ギアムは「そのほうが良いですよね、殿下? あっ……ちなみに、貴方はどっちの殿下ですか?」とシオンに確認した。
「シオンだよ。そうだね、ギアムは王族や貴族の秘密を知り過ぎているから、王家を離れるなら死なないと無理だね」
「そうそう、俺が王家を離れたら、弟や家に迷惑がかかるんで」
その言葉にシオンが「ギアムって、そういうことも考えられるんだ。お酒と剣のことしか頭にないかと思っていたよ」と感心している。
「殿下は俺をなんだと思ってんスか? まぁ、シオン殿下なら死体偽装とかそこらへん上手くできますよね? ほら、ローレル殿下に隠れて、コソコソするの得意じゃないですか」
シオンはニッコリと優雅に微笑みながら、「とりあえず、その軽率な口を閉じようか」と言うとリナリアを優しく抱きしめた。
「ギアムの言うことは気にしないでね」
「は、はい……」
返事をしながらも『シオンの闇って私が思っている以上に深いかも』とリナリアは思った。それでもシオンのことが少しも嫌だと思わないので、シオンへの愛の深さに自分自身でも驚いてしまう。
ギアムは両手を上に上げて、思いっきり伸びをした。
「よーし、俺にも運が向いてきたぞ! セリー商会では、ひと月に一回くらいは休みもらえますかね? ね、お嬢さん」
「いえ……。もっともらえると思いますよ」
「マジか……」
驚愕するギアムに「お嬢さんが何をするか知りませんが、頑張ってくださいね!」と握手を求められた。リナリアがその手を握り返す前に、シオンが間に割って入りギアムの手を叩き落とす。
「汚い手でリナリアにさわるな」
「まぁ確かに綺麗ではないですね」
ギアムは素直に納得している。
(変な二人。でも仲が悪いわけではないのね。……仲良くもなさそうだけど)
ギアムと別れてシオンと二人きりになった。授業が終わるまではまだ時間が残っていたので、いつものサロンへと向かう。
人通りのない廊下を歩いていると誰かに見つかったらどうしようと不安になってしまう。ようやくサロンにたどり着き、扉を閉めるとリナリアはホッと安堵のため息をついた。
「大丈夫?」
「はい、サボりって緊張しますね」
シオンは「リナリアは可愛いね」と微笑んでいる。
「今、お茶を淹れるね」
「あ、シオン、私が」
「ううん、私に淹れさせて。私が淹れたお茶をリナリアに飲んでほしいんだ」
そこまで言うならとリナリアはシオンに任せてソファーに座った。シオンは優雅な手つきでお茶の準備をしている。
「ねぇ、リナリア。これからどうするつもりなの?」
お茶を淹れる手を止めずにシオンが聞いてきた。
「そうですね。まず、シオンの悪評を消さないと。そのためには、今までシオンがしたとされていることを、ローレル殿下がしてきたと証明する必要があると思います。だから、今からその証拠探しですね」
「証拠ねぇ……」
シオンは茶葉を入れたティーポットにお湯を注ぎながら呟いた。
「あれが使えるかもしれない」
「え!? あるんですか!?」
「うん、私の考えでは『ローレルが作ったシオンの悪評を利用して王室から除名される』つもりだったから、そのために、シオンの悪評の証拠を密かに集めていたんだよ。シオンはこれだけ悪いことをしていますよって」
茶葉を蒸らしている間に、シオンはカギ付きの引き出しから分厚い書類の束を取りだした。
「在学中に、シオンのふりをしたローレルが、いつ、誰に、何をしたかをできる限り記録していたんだ」
「こんなにたくさん?」
「うん。記録だけじゃないよ、ローレルが私のふりをしている間、部屋から出るなと言われていたけど、私もローレルのふりをして、目撃者や被害者の証言を集めていたんだ。『シオンに困っているから、証拠を集めて彼を更生させたい』と言ったら、みんな喜んで協力してくれてね。証言が真実だと証明するためのサインも貰っている」
「もしかして、シオンが忙しくて私と一緒に帰れない理由って……」
「そう、本気でリナリアと一緒になりたくて、以前より必死に証拠集めをしていたんだ。まぁ、私の空回りだったけど」
少し恥ずかしそうにシオンはうつむいた。
「そんなことないです。だって、これがシオンではなくローレル殿下がやったことだと証明できれば証拠になります」
「問題は、それをどうやって証明するかだよね。ローレルが私のふりをしているときに、私がシオンとして現れたら、シオンが二人ってことにはできるけど、そこからどうするか……。だって、リナリアとゼダ以外、私たち王子を見分けられないのだから……」
「それなんですけど……。本当に誰も見分けられないんでしょうか?」
「ん? どういうこと?」
リナリアはまっすぐにシオンを見つめた。
「だって、好きな人のことって、なんでも知りたいし、小さなことだって覚えているじゃないですか。私だって、シオンの右耳の後ろらへんに小さなホクロがあること、ずっと覚えていましたから」
「ようするに、ローレルのことが好きな人は、ローレルと私の小さな違いに気がついている可能性があるってこと?」
「はい、ローレル殿下はたくさんの女性と遊んでいますが、遊ばれている女性は、自分だけは遊びではないと思っている方もいたと思います。それこそ、本当にローレル殿下を愛している方もいたはずです」
「なるほど、その女性たちは、普通なら気がつかないことにも気がついている可能性があるんだね」
「はい、少し調べてみても良いでしょうか?」
「うん、でも、今のシオンの恋人であるリナリアが、元恋人たちのことを調べるのは難しいと思うから、私からゼダに頼むよ」
「私も、ケイトにお願いしてみます」
トレーを持ったシオンは、テーブルに湯気の立つティーカップを並べた。
「はい、どうぞ」
「ありがとうございます」
ティーカップに口をつけるリナリアを、シオンは嬉しそうに眺めている。
「シオン、どうかしましたか?」
「私が淹れたお茶がリナリアの体内に入っていくのが嬉しくて」
妙な言い方をされてリナリアはむせた。
「次は料理でも学ぼうかな? そうしたら、私が作った料理がリナリアの身体の一部になるんだから最高だよね。ああ、想像しただけで楽しくなってきた」
シオンは、キラキラと爽やかな笑みを浮かべながらそんなことを言ってくる。
(た、たぶんシオンは、純粋な気持ちで私に手料理を食べさせたいって言ってくれているのよね? それなのに、なんだか、いやらしいことのように聞こえてしまうわ……。ごめんなさい、シオン)
リナリアは心の中で深く謝罪した。
「ギアム様に、何かをしてもらいたいというよりは何もせずに、私がすることを見逃して欲しいんです」
「ふーん? じゃあ、分かりました。これからお嬢さんがすることは、俺は何も見ていないということで」
「あ、え、はい……」
あっさりと受け入れられ、逆にリナリアのほうが戸惑ってしまう。
「あの、明日にでも正式にセリー商会と契約を……」
「いや、いりませんよ。もし、お嬢さんが俺を裏切ったら、セリー商会に、それ相応の対応をするだけですから」
ギアムの余裕な態度は、自分が圧倒的強者だと物語っている。契約や身分は、容赦のない暴力の前では、時に無意味なのかもしれない。
リナリアは、ふと『もし今が戦乱の時代なら、ギアム様は英雄と呼ばれていたのかも』と思った。
「もちろん、私もセリー商会もギアム様を裏切りません」
「そうあることを願います。こちらからの条件ですが、お嬢さんの用事が終わったら、俺を死んだことにしてください」
「え?」
ギアムは「そのほうが良いですよね、殿下? あっ……ちなみに、貴方はどっちの殿下ですか?」とシオンに確認した。
「シオンだよ。そうだね、ギアムは王族や貴族の秘密を知り過ぎているから、王家を離れるなら死なないと無理だね」
「そうそう、俺が王家を離れたら、弟や家に迷惑がかかるんで」
その言葉にシオンが「ギアムって、そういうことも考えられるんだ。お酒と剣のことしか頭にないかと思っていたよ」と感心している。
「殿下は俺をなんだと思ってんスか? まぁ、シオン殿下なら死体偽装とかそこらへん上手くできますよね? ほら、ローレル殿下に隠れて、コソコソするの得意じゃないですか」
シオンはニッコリと優雅に微笑みながら、「とりあえず、その軽率な口を閉じようか」と言うとリナリアを優しく抱きしめた。
「ギアムの言うことは気にしないでね」
「は、はい……」
返事をしながらも『シオンの闇って私が思っている以上に深いかも』とリナリアは思った。それでもシオンのことが少しも嫌だと思わないので、シオンへの愛の深さに自分自身でも驚いてしまう。
ギアムは両手を上に上げて、思いっきり伸びをした。
「よーし、俺にも運が向いてきたぞ! セリー商会では、ひと月に一回くらいは休みもらえますかね? ね、お嬢さん」
「いえ……。もっともらえると思いますよ」
「マジか……」
驚愕するギアムに「お嬢さんが何をするか知りませんが、頑張ってくださいね!」と握手を求められた。リナリアがその手を握り返す前に、シオンが間に割って入りギアムの手を叩き落とす。
「汚い手でリナリアにさわるな」
「まぁ確かに綺麗ではないですね」
ギアムは素直に納得している。
(変な二人。でも仲が悪いわけではないのね。……仲良くもなさそうだけど)
ギアムと別れてシオンと二人きりになった。授業が終わるまではまだ時間が残っていたので、いつものサロンへと向かう。
人通りのない廊下を歩いていると誰かに見つかったらどうしようと不安になってしまう。ようやくサロンにたどり着き、扉を閉めるとリナリアはホッと安堵のため息をついた。
「大丈夫?」
「はい、サボりって緊張しますね」
シオンは「リナリアは可愛いね」と微笑んでいる。
「今、お茶を淹れるね」
「あ、シオン、私が」
「ううん、私に淹れさせて。私が淹れたお茶をリナリアに飲んでほしいんだ」
そこまで言うならとリナリアはシオンに任せてソファーに座った。シオンは優雅な手つきでお茶の準備をしている。
「ねぇ、リナリア。これからどうするつもりなの?」
お茶を淹れる手を止めずにシオンが聞いてきた。
「そうですね。まず、シオンの悪評を消さないと。そのためには、今までシオンがしたとされていることを、ローレル殿下がしてきたと証明する必要があると思います。だから、今からその証拠探しですね」
「証拠ねぇ……」
シオンは茶葉を入れたティーポットにお湯を注ぎながら呟いた。
「あれが使えるかもしれない」
「え!? あるんですか!?」
「うん、私の考えでは『ローレルが作ったシオンの悪評を利用して王室から除名される』つもりだったから、そのために、シオンの悪評の証拠を密かに集めていたんだよ。シオンはこれだけ悪いことをしていますよって」
茶葉を蒸らしている間に、シオンはカギ付きの引き出しから分厚い書類の束を取りだした。
「在学中に、シオンのふりをしたローレルが、いつ、誰に、何をしたかをできる限り記録していたんだ」
「こんなにたくさん?」
「うん。記録だけじゃないよ、ローレルが私のふりをしている間、部屋から出るなと言われていたけど、私もローレルのふりをして、目撃者や被害者の証言を集めていたんだ。『シオンに困っているから、証拠を集めて彼を更生させたい』と言ったら、みんな喜んで協力してくれてね。証言が真実だと証明するためのサインも貰っている」
「もしかして、シオンが忙しくて私と一緒に帰れない理由って……」
「そう、本気でリナリアと一緒になりたくて、以前より必死に証拠集めをしていたんだ。まぁ、私の空回りだったけど」
少し恥ずかしそうにシオンはうつむいた。
「そんなことないです。だって、これがシオンではなくローレル殿下がやったことだと証明できれば証拠になります」
「問題は、それをどうやって証明するかだよね。ローレルが私のふりをしているときに、私がシオンとして現れたら、シオンが二人ってことにはできるけど、そこからどうするか……。だって、リナリアとゼダ以外、私たち王子を見分けられないのだから……」
「それなんですけど……。本当に誰も見分けられないんでしょうか?」
「ん? どういうこと?」
リナリアはまっすぐにシオンを見つめた。
「だって、好きな人のことって、なんでも知りたいし、小さなことだって覚えているじゃないですか。私だって、シオンの右耳の後ろらへんに小さなホクロがあること、ずっと覚えていましたから」
「ようするに、ローレルのことが好きな人は、ローレルと私の小さな違いに気がついている可能性があるってこと?」
「はい、ローレル殿下はたくさんの女性と遊んでいますが、遊ばれている女性は、自分だけは遊びではないと思っている方もいたと思います。それこそ、本当にローレル殿下を愛している方もいたはずです」
「なるほど、その女性たちは、普通なら気がつかないことにも気がついている可能性があるんだね」
「はい、少し調べてみても良いでしょうか?」
「うん、でも、今のシオンの恋人であるリナリアが、元恋人たちのことを調べるのは難しいと思うから、私からゼダに頼むよ」
「私も、ケイトにお願いしてみます」
トレーを持ったシオンは、テーブルに湯気の立つティーカップを並べた。
「はい、どうぞ」
「ありがとうございます」
ティーカップに口をつけるリナリアを、シオンは嬉しそうに眺めている。
「シオン、どうかしましたか?」
「私が淹れたお茶がリナリアの体内に入っていくのが嬉しくて」
妙な言い方をされてリナリアはむせた。
「次は料理でも学ぼうかな? そうしたら、私が作った料理がリナリアの身体の一部になるんだから最高だよね。ああ、想像しただけで楽しくなってきた」
シオンは、キラキラと爽やかな笑みを浮かべながらそんなことを言ってくる。
(た、たぶんシオンは、純粋な気持ちで私に手料理を食べさせたいって言ってくれているのよね? それなのに、なんだか、いやらしいことのように聞こえてしまうわ……。ごめんなさい、シオン)
リナリアは心の中で深く謝罪した。