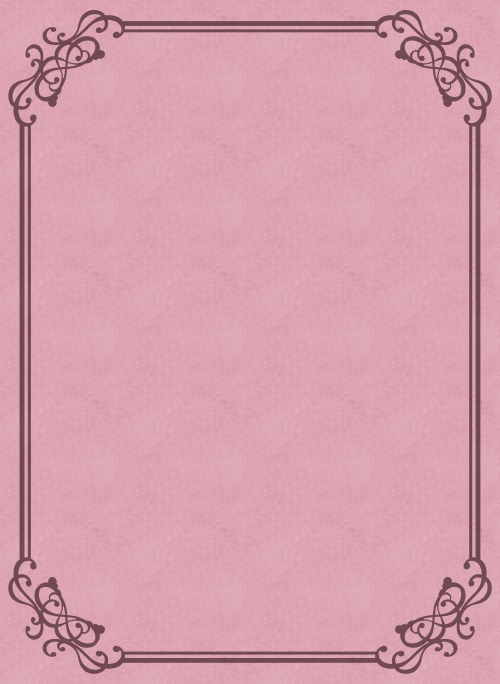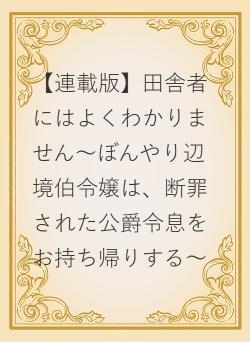シオンの顔が近すぎて、金色のまつ毛の一本一本まで見えてしまう。
(まつ毛、長い……)
馬車のカーテンの隙間から差し込む朝日に照らされ、シオンの金髪がキラキラと輝いている。
(シオンって、やっぱりすごく綺麗だわ)
でもこの美しい外見だけに惹かれてシオンを好きになったのではない。もし外見だけに惹かれていたなら、同じくらい綺麗な顔をしているローレルでも良かったはずだ。
「リナリア、何を考えているの?」
今にも鼻と鼻がふれてしまいそうな至近距離でシオンが甘く囁く。
「前に私がシオンのお顔が大好きって話をしましたよね?」
「そうだね」
「私は、確かにシオンのお顔が大好きですけど、もし、シオンがお顔に大怪我をおってしまっても、私はシオンのことが大好きです」
シオンの紫色の瞳がわずかに見開いた。
「私は……子どものころに泣いている私を慰めてくれた優しいシオンに恋をしました。学園に入学してからは、この想いが叶うはずがないと分かっていて、ずっと遠くから見つめていたんです」
「見つめるだけ?」
「はい、シオンのファンでしたからね! シオンも私を見守ってくれていたんですよね? 私とシオンって少し似ている気がしませんか?」
リナリアがそう言うと、シオンが愛おしそうにリナリアの髪をなでた。
「そうだったら良かったんだけど……。私とリナリアの想いは、贈り合った薔薇の本数くらいの違いはあると思うよ?」
「私よりシオンのほうが愛が多いってことですか?」
シオンは答えずにニッコリと優雅に微笑む。
リナリアが「そうかな?」と呟くと、「そのうち、嫌っていうほど分からせてあげるよ」とシオンは意味深なことをいう。今は教えてくれる気はないようだ。
髪をなでるシオンの優しい手にドキドキしながらも、リナリアは母との会話を伝えた。
「そういえば、私の母は学生の間はシオンと付き合うことに反対しないって言ってくれました。それに、サジェスから助けてくれたことをとても感謝していると」
「そう」
シオンは嬉しそうに口元を緩めた。
「あ、でも、節度を持ったお付き合いをしなさいとも言われました」
「節度って?」
「ほら、身体の関係を持つとかはダメって……あっ」
はしたないことを言ってしまったとリナリアがうつむくと、シオンはわざわざうつむいた顔を覗き込んでくる。
「リナリア、顔が真っ赤だよ」
恥ずかしすぎて言葉が返せない。
「リナリアって、そういうこと知らないのかと思っていたよ」
「し、知っていますよ!? からかわないでください!」
リナリアがシオンを両手で押しのけても、シオンは嬉しそうに笑っている。
「だって、リナリアは手のひらへのキスの意味も知らなかったし、私が壁際に追い詰めても少しも抵抗したり、嫌がったりしなかったから。恋愛の知識があまりないのかなって思って」
「あれは、驚きすぎたのと、あと、シオンだったから嫌じゃなくて、嬉しくて……その」
リナリアが必死に言い訳をしていると、今度はシオンがうつむいた。
「シオン?」
心配になって顔を覗き込むと、今度はシオンが赤くなっている。
「リナリアは、本当にずるいよ」
シオンは赤い顔のまま「今日は、学園に行かず、このまま二人きりで過ごさない?」と甘い誘惑をしてくる。こういうときのシオンの色気は相変わらず凄まじい。
(うっ、気をしっかり持つのよ!)
自分自身に気合をいれながらリナリアは首を左右にふった。
「サボりはダメです! それに、今日は私、ギアム様にお話があって……」
「ギアムに?」
そう呟いたシオンの声がとても冷たくて、馬車内の温度が一気に下がったような気がする。
「どうして? なんの用なの? まさか、ギアムと二人きりで話すつもり?」
シオンは、感情の起伏がない声で早口に問い詰めてくる。
「違いますよ。ギアム様とお話する時は、もちろんシオンにも付き合ってもらいます。だって、これは私とシオンのためですから」
「リナリアと私のため?」
「はい、私はシオンが悪評のせいで王室から除名されるなんて嫌です。もっと良い方法があると思います。だから、私とシオンのより良い未来のために、私ができることは全てします」
「より良い未来……」
驚いているシオンを今度はリナリアが問い詰めた。
「シオン、よく考えてみてください。悪評を消さないと、もし私たちに子どもができたとき、そのせいでつらいめにあうかもしれませんよ?」
「リナリアと私の子ども……」
「そうですよ! お父様のひどいウワサなんて、子どもは聞きたくないでしょう? 私も夫の悪口なんて聞きたくありません」
「……そっか、そうだね」
シオンはまるで眩しいものを見るかのように、美しい瞳を細めた。
(まつ毛、長い……)
馬車のカーテンの隙間から差し込む朝日に照らされ、シオンの金髪がキラキラと輝いている。
(シオンって、やっぱりすごく綺麗だわ)
でもこの美しい外見だけに惹かれてシオンを好きになったのではない。もし外見だけに惹かれていたなら、同じくらい綺麗な顔をしているローレルでも良かったはずだ。
「リナリア、何を考えているの?」
今にも鼻と鼻がふれてしまいそうな至近距離でシオンが甘く囁く。
「前に私がシオンのお顔が大好きって話をしましたよね?」
「そうだね」
「私は、確かにシオンのお顔が大好きですけど、もし、シオンがお顔に大怪我をおってしまっても、私はシオンのことが大好きです」
シオンの紫色の瞳がわずかに見開いた。
「私は……子どものころに泣いている私を慰めてくれた優しいシオンに恋をしました。学園に入学してからは、この想いが叶うはずがないと分かっていて、ずっと遠くから見つめていたんです」
「見つめるだけ?」
「はい、シオンのファンでしたからね! シオンも私を見守ってくれていたんですよね? 私とシオンって少し似ている気がしませんか?」
リナリアがそう言うと、シオンが愛おしそうにリナリアの髪をなでた。
「そうだったら良かったんだけど……。私とリナリアの想いは、贈り合った薔薇の本数くらいの違いはあると思うよ?」
「私よりシオンのほうが愛が多いってことですか?」
シオンは答えずにニッコリと優雅に微笑む。
リナリアが「そうかな?」と呟くと、「そのうち、嫌っていうほど分からせてあげるよ」とシオンは意味深なことをいう。今は教えてくれる気はないようだ。
髪をなでるシオンの優しい手にドキドキしながらも、リナリアは母との会話を伝えた。
「そういえば、私の母は学生の間はシオンと付き合うことに反対しないって言ってくれました。それに、サジェスから助けてくれたことをとても感謝していると」
「そう」
シオンは嬉しそうに口元を緩めた。
「あ、でも、節度を持ったお付き合いをしなさいとも言われました」
「節度って?」
「ほら、身体の関係を持つとかはダメって……あっ」
はしたないことを言ってしまったとリナリアがうつむくと、シオンはわざわざうつむいた顔を覗き込んでくる。
「リナリア、顔が真っ赤だよ」
恥ずかしすぎて言葉が返せない。
「リナリアって、そういうこと知らないのかと思っていたよ」
「し、知っていますよ!? からかわないでください!」
リナリアがシオンを両手で押しのけても、シオンは嬉しそうに笑っている。
「だって、リナリアは手のひらへのキスの意味も知らなかったし、私が壁際に追い詰めても少しも抵抗したり、嫌がったりしなかったから。恋愛の知識があまりないのかなって思って」
「あれは、驚きすぎたのと、あと、シオンだったから嫌じゃなくて、嬉しくて……その」
リナリアが必死に言い訳をしていると、今度はシオンがうつむいた。
「シオン?」
心配になって顔を覗き込むと、今度はシオンが赤くなっている。
「リナリアは、本当にずるいよ」
シオンは赤い顔のまま「今日は、学園に行かず、このまま二人きりで過ごさない?」と甘い誘惑をしてくる。こういうときのシオンの色気は相変わらず凄まじい。
(うっ、気をしっかり持つのよ!)
自分自身に気合をいれながらリナリアは首を左右にふった。
「サボりはダメです! それに、今日は私、ギアム様にお話があって……」
「ギアムに?」
そう呟いたシオンの声がとても冷たくて、馬車内の温度が一気に下がったような気がする。
「どうして? なんの用なの? まさか、ギアムと二人きりで話すつもり?」
シオンは、感情の起伏がない声で早口に問い詰めてくる。
「違いますよ。ギアム様とお話する時は、もちろんシオンにも付き合ってもらいます。だって、これは私とシオンのためですから」
「リナリアと私のため?」
「はい、私はシオンが悪評のせいで王室から除名されるなんて嫌です。もっと良い方法があると思います。だから、私とシオンのより良い未来のために、私ができることは全てします」
「より良い未来……」
驚いているシオンを今度はリナリアが問い詰めた。
「シオン、よく考えてみてください。悪評を消さないと、もし私たちに子どもができたとき、そのせいでつらいめにあうかもしれませんよ?」
「リナリアと私の子ども……」
「そうですよ! お父様のひどいウワサなんて、子どもは聞きたくないでしょう? 私も夫の悪口なんて聞きたくありません」
「……そっか、そうだね」
シオンはまるで眩しいものを見るかのように、美しい瞳を細めた。