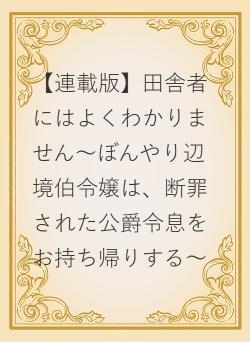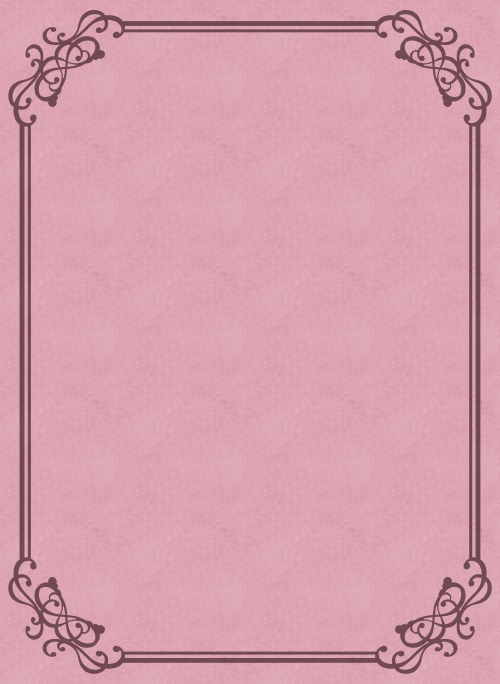リナリアはケイトと別れてオルウェン伯爵家の馬車に乗り込んだ。
最近シオンは何かと忙しいようで、帰りは別々に帰っている。それでも毎朝一緒に登校しているし、放課後も一緒に過ごせるので寂しいとは思わない。
(シオンは、毎朝リナリアの花束をくれていたけど、明日からはどうなるのかな?)
リナリアの花言葉は『この恋に気づいて』なので、シオンの恋に気がついた今は、リナリアの花は必要ない。
(それに、貰うばっかりじゃなくて、私もシオンに何かあげたい)
悩んだ結果、リナリアはシオンに赤い薔薇を贈ろうと決めた。オルウェン伯爵領にある本邸では、広い庭園で様々な花を育てているが、リナリアが住んでいる都市用の邸宅では残念ながら庭園に力を入れていない。
(でも、薔薇一本ならあるよね)
シオンのように両手いっぱいの花束は贈れないが、今できる精一杯の気持ちを伝えたい。
(赤い薔薇の花言葉は『愛しています』だって、お母様が言っていたものね)
リナリアの花言葉を知っているシオンなら、薔薇の花言葉も知っているかもしれない。
(もし、知らなかったらシオンに教えてあげよう)
口元を緩ませながらそんなことを考えていると、あっと言う間に馬車はオルウェン伯爵家の邸宅に着いた。
(あ、お母様だわ)
夕暮れどきの邸宅の小さな庭で、母がのんびりと花を眺めている。
「お母様、ただいま戻りました」
「お帰りなさい、リナリア」
「お散歩ですか?」
そう尋ねると、母は「貴女の帰りを待っていたのよ」と優しく微笑む。
すぐに領地に戻るのかと思っていた母は「せっかく来たのだから、しばらくここにいるわ」と言って邸宅に残ってくれた。
(きっとシオンとの関係を心配してくれているのね)
そう思うと申し訳ない気持ちになってしまう。
「貴女が着替えたら、食事にしましょうか」という母をリナリアは呼び止めた。
「お母様、お話があります」
「何かしら?」
「シオン殿下のことです」
穏やかだった母の表情が少しだけ曇った。
「お母様の言う通り、シオン殿下は私に好意を持ってくださっていました」
「……そう」
母は少しも驚かずに「まぁそうよね。あんなに毎朝リナリアの花束を贈ってくれるんだから、そうじゃないとおかしいわよね」と、納得している。
「それで、シオン殿下のお気持ちに気がついた貴女はどうするの?」
「私は……。実は、私もシオン殿下のことがずっと好きだったんです! 今は、殿下とお付き合いしています。その、将来的には結婚したいです」
頬が熱い。リナリアは、恥ずかしくて、そして、反対されるのが怖くて母の顔が見られなかった。
「それは、困ったけど……嬉しいわね」
「え?」
リナリアがおそるおそる母を見ると、母は優しい目をしていた。
「怒らないんですか?」
「リナリアは、怒られたかったの?」
「い、いえ」
「だってねぇ、好きになっちゃったんだから仕方ないわよね。確かにオルウェン伯爵家としては困るけど、貴女の母としては、貴女が結婚したいと思えるくらい好きな人に出会えたことが素直に嬉しいわ」
「お母様……」
母の温かい言葉に胸がいっぱいになってしまう。
「それで、どういう流れで二人の気持ちが通じたの?」
瞳を輝かせながら少女のように母が聞いてくる。
「そうですね……一番のきっかけは、ライラック伯爵家のサジェスから助けてもらったことだと思います」
それまでニコニコしていた母の顔が強張った。
「ん? ライラックの次男が? 貴女に何かしたの?」
(あ、そういえば、サジェスから嫌がらせを受けていたことを、お母様に報告していなかったわ)
あのときは、学園内でサジェスを避けて無視すれば良いだけと思っていた。
暴言をはかれて自分の心が傷つくことをそれほど深刻に考えていなかったし、離れて暮らす両親を心配させたくなかった。
「あ、ちょっといろいろありまして……」
「リナリア、その『ちょっといろいろあったこと』を詳しく話しなさい」
そう言った母の瞳の怖さに、リナリアは『言わなければ良かった』と後悔した。
最近シオンは何かと忙しいようで、帰りは別々に帰っている。それでも毎朝一緒に登校しているし、放課後も一緒に過ごせるので寂しいとは思わない。
(シオンは、毎朝リナリアの花束をくれていたけど、明日からはどうなるのかな?)
リナリアの花言葉は『この恋に気づいて』なので、シオンの恋に気がついた今は、リナリアの花は必要ない。
(それに、貰うばっかりじゃなくて、私もシオンに何かあげたい)
悩んだ結果、リナリアはシオンに赤い薔薇を贈ろうと決めた。オルウェン伯爵領にある本邸では、広い庭園で様々な花を育てているが、リナリアが住んでいる都市用の邸宅では残念ながら庭園に力を入れていない。
(でも、薔薇一本ならあるよね)
シオンのように両手いっぱいの花束は贈れないが、今できる精一杯の気持ちを伝えたい。
(赤い薔薇の花言葉は『愛しています』だって、お母様が言っていたものね)
リナリアの花言葉を知っているシオンなら、薔薇の花言葉も知っているかもしれない。
(もし、知らなかったらシオンに教えてあげよう)
口元を緩ませながらそんなことを考えていると、あっと言う間に馬車はオルウェン伯爵家の邸宅に着いた。
(あ、お母様だわ)
夕暮れどきの邸宅の小さな庭で、母がのんびりと花を眺めている。
「お母様、ただいま戻りました」
「お帰りなさい、リナリア」
「お散歩ですか?」
そう尋ねると、母は「貴女の帰りを待っていたのよ」と優しく微笑む。
すぐに領地に戻るのかと思っていた母は「せっかく来たのだから、しばらくここにいるわ」と言って邸宅に残ってくれた。
(きっとシオンとの関係を心配してくれているのね)
そう思うと申し訳ない気持ちになってしまう。
「貴女が着替えたら、食事にしましょうか」という母をリナリアは呼び止めた。
「お母様、お話があります」
「何かしら?」
「シオン殿下のことです」
穏やかだった母の表情が少しだけ曇った。
「お母様の言う通り、シオン殿下は私に好意を持ってくださっていました」
「……そう」
母は少しも驚かずに「まぁそうよね。あんなに毎朝リナリアの花束を贈ってくれるんだから、そうじゃないとおかしいわよね」と、納得している。
「それで、シオン殿下のお気持ちに気がついた貴女はどうするの?」
「私は……。実は、私もシオン殿下のことがずっと好きだったんです! 今は、殿下とお付き合いしています。その、将来的には結婚したいです」
頬が熱い。リナリアは、恥ずかしくて、そして、反対されるのが怖くて母の顔が見られなかった。
「それは、困ったけど……嬉しいわね」
「え?」
リナリアがおそるおそる母を見ると、母は優しい目をしていた。
「怒らないんですか?」
「リナリアは、怒られたかったの?」
「い、いえ」
「だってねぇ、好きになっちゃったんだから仕方ないわよね。確かにオルウェン伯爵家としては困るけど、貴女の母としては、貴女が結婚したいと思えるくらい好きな人に出会えたことが素直に嬉しいわ」
「お母様……」
母の温かい言葉に胸がいっぱいになってしまう。
「それで、どういう流れで二人の気持ちが通じたの?」
瞳を輝かせながら少女のように母が聞いてくる。
「そうですね……一番のきっかけは、ライラック伯爵家のサジェスから助けてもらったことだと思います」
それまでニコニコしていた母の顔が強張った。
「ん? ライラックの次男が? 貴女に何かしたの?」
(あ、そういえば、サジェスから嫌がらせを受けていたことを、お母様に報告していなかったわ)
あのときは、学園内でサジェスを避けて無視すれば良いだけと思っていた。
暴言をはかれて自分の心が傷つくことをそれほど深刻に考えていなかったし、離れて暮らす両親を心配させたくなかった。
「あ、ちょっといろいろありまして……」
「リナリア、その『ちょっといろいろあったこと』を詳しく話しなさい」
そう言った母の瞳の怖さに、リナリアは『言わなければ良かった』と後悔した。