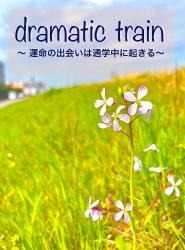千夏は泉の部屋に入ると、二人用の小さなダイニングテーブルの前に立った。先ほど保冷バッグに詰めたばかりのタッパーを、一つずつ丁寧に取り出して、順番に並べていく。その手つきには、どこか静かな儀式のような感じがした。
「これ、全部千夏さんの手作り?」
「そうだけど文句ある?」
普段の夕食はもっと質素なものだ。けれど今夜は特別だった。泉のことを考えると胸の奥がざわつき、そのもやもやを振り払うように台所に立ったのだ。
ところが、出来上がった料理を前にして気づけば、泉が箸をつけようとしている。まるで最初から彼に食べさせるために腕を振るったかのようで、妙な気持ちにさせられた。
「マジ嬉しい。」
千夏が並べたタッパーをいくつか選び取ると泉は電子レンジで温め直した。
「待ってる間って暇じゃない?」
そう言って泉は千夏を引き寄せ、強く抱きしめた。
胸に押しつけられた彼の体温と呼吸の膨らみを感じ取った瞬間、千夏の意識は自分の匂いへと向かう。
(お風呂入ったし……大丈夫、だよね……?)
小さな不安が心の隅をかすめる。
静寂を破るように、背後では電子レンジの低い機械音がブォーーと規則正しく響いていた。
「ちょっと、くっつき過ぎよ!」
流されるまま抱きしめられている自分に気づいた瞬間、千夏の頬は熱く染まった。
「もしかして照れてるの?俺たちもっとすごいことしてんじゃん。」
いたずらっ子のように口元を緩めると、彼の仕草は次第に熱を帯びていく。スキンシップは自然とエスカレートし、やがて首筋に柔らかな唇がかすかに触れた。
「千夏さん、俺の声好きでしょ?」
泉の低く艶のある声が、耳元にそっと触れるように響いた瞬間、背筋をゾクリと震えが駆け抜けた。鳥肌が一斉に立ち、体からふっと力が抜け落ちていく。
ーーーピピピッ、ピピピッ。
電子レンジの無機質な音が響いた瞬間、ふたりを包んでいた甘やかな空気は静かにほどけ、静けさだけが残った。
「ほっ、ほら、温め終わったからさっさと食べちゃって!!食料届けたんだから私帰るからっ!」
ドキドキと高鳴る鼓動を誤魔化すように、千夏はわざと声を張り上げて言葉を投げた。泉に気づかれまいとしたその仕草さえも、逆に隠しきれない。案の定、泉はそれを見抜いたようにニヤリと口角を上げた。
「1人で食べるの、いやだ。せっかく会えたんだから、もっと一緒にいようよ。」
キッチンからリビングへと移動し、千夏をソファに座らせると、ダイニングテーブルに戻り自分はそっと彼女の作った料理に手を伸ばした。
「うまい……。今度はうちで作ってよ。出来立てが食べたいな。」
お世辞かと思いきや、泉はあっという間に平らげ、その顔には本当に美味しそうな表情が浮かんでいた。思わず見ているこちらまで、心が温かくなる。
「食べおわったならもう良いでしょ?今度こそ帰るから。」
カバンと上着を手に取って、そっとソファから立ち上がる。ダイニングテーブルに座る泉の横を通り過ぎ、玄関へ向かおうとしたその瞬間――彼の手が私の腕をそっと掴む。
次の瞬間、千夏はまるで吸い込まれるかのように、再び彼の胸の中にすっぽりと収まっていた。
「デザートがまだだよ。」
泉はゆっくりと千夏の頬に手を当てて髪をかきあげながら顔を自分に向けると優しくキスをした。
「デザートに千夏さん食べたい。」
「駄目よ。」
「やだ。食べる。」
駄々をこねるように子供のように頬を膨らませて見せ、キスを続けながら泉はソファに座り千夏を自分の膝の上に座らせた。
「明日、仕事だもの…。ダメ…。」
偶然にも知人の兄だとはいえ、出会ってまだ二度目の彼と距離が近くなるたび、胸の奥がざわついた。軽々しく関係を重ねる自分にはなりたくない——そう思いながらも、心の奥のどこかで不思議な落ち着きと期待が入り混じる。自分ではまだ気づいていないけれど、知らず知らずのうちに、声だけではなく彼の存在自体に惹かれているのかもしれない。その思いに戸惑いながらも、どうしても拒否できずにいる自分がいた。
「明日が仕事じゃなければイイの?」
「……そう言うわけじゃない。」
泉の手が千夏の腰に触れた瞬間、思わず身体が硬くなる。手はそっと背中に沿って動き、千夏は軽く息を呑んだ。予想していなかった展開の早い距離感に戸惑う。
「ちょっ…。」
千夏は泉の手から逃れようともがいたが、細身の割には意外に力のある彼にあっさりと捕まってしまった。
「千夏さん、可愛い。」
千夏はクルッと反転させられ、視界に天井が広がった。
(このまま、いつでも都合よく扱われる軽い女にはなりたくない……)
心の中で強くそう思っても、泉の手慣れた動きに、どうしても上手く抵抗できない自分がいた。
「千夏さんの体ってエロいよね。」
器用に千夏の服を脱がしながら息を荒くして泉は言った。
(そうよ、彼の声がいけないの!こんな良い声で囁かれたら抗えない。)
「今日もお姫様だっこしてあげるね。」
そう言うと泉はスッと千夏を抱きかかえ、あの夜と同じように寝室へと運んだ。
「これ、全部千夏さんの手作り?」
「そうだけど文句ある?」
普段の夕食はもっと質素なものだ。けれど今夜は特別だった。泉のことを考えると胸の奥がざわつき、そのもやもやを振り払うように台所に立ったのだ。
ところが、出来上がった料理を前にして気づけば、泉が箸をつけようとしている。まるで最初から彼に食べさせるために腕を振るったかのようで、妙な気持ちにさせられた。
「マジ嬉しい。」
千夏が並べたタッパーをいくつか選び取ると泉は電子レンジで温め直した。
「待ってる間って暇じゃない?」
そう言って泉は千夏を引き寄せ、強く抱きしめた。
胸に押しつけられた彼の体温と呼吸の膨らみを感じ取った瞬間、千夏の意識は自分の匂いへと向かう。
(お風呂入ったし……大丈夫、だよね……?)
小さな不安が心の隅をかすめる。
静寂を破るように、背後では電子レンジの低い機械音がブォーーと規則正しく響いていた。
「ちょっと、くっつき過ぎよ!」
流されるまま抱きしめられている自分に気づいた瞬間、千夏の頬は熱く染まった。
「もしかして照れてるの?俺たちもっとすごいことしてんじゃん。」
いたずらっ子のように口元を緩めると、彼の仕草は次第に熱を帯びていく。スキンシップは自然とエスカレートし、やがて首筋に柔らかな唇がかすかに触れた。
「千夏さん、俺の声好きでしょ?」
泉の低く艶のある声が、耳元にそっと触れるように響いた瞬間、背筋をゾクリと震えが駆け抜けた。鳥肌が一斉に立ち、体からふっと力が抜け落ちていく。
ーーーピピピッ、ピピピッ。
電子レンジの無機質な音が響いた瞬間、ふたりを包んでいた甘やかな空気は静かにほどけ、静けさだけが残った。
「ほっ、ほら、温め終わったからさっさと食べちゃって!!食料届けたんだから私帰るからっ!」
ドキドキと高鳴る鼓動を誤魔化すように、千夏はわざと声を張り上げて言葉を投げた。泉に気づかれまいとしたその仕草さえも、逆に隠しきれない。案の定、泉はそれを見抜いたようにニヤリと口角を上げた。
「1人で食べるの、いやだ。せっかく会えたんだから、もっと一緒にいようよ。」
キッチンからリビングへと移動し、千夏をソファに座らせると、ダイニングテーブルに戻り自分はそっと彼女の作った料理に手を伸ばした。
「うまい……。今度はうちで作ってよ。出来立てが食べたいな。」
お世辞かと思いきや、泉はあっという間に平らげ、その顔には本当に美味しそうな表情が浮かんでいた。思わず見ているこちらまで、心が温かくなる。
「食べおわったならもう良いでしょ?今度こそ帰るから。」
カバンと上着を手に取って、そっとソファから立ち上がる。ダイニングテーブルに座る泉の横を通り過ぎ、玄関へ向かおうとしたその瞬間――彼の手が私の腕をそっと掴む。
次の瞬間、千夏はまるで吸い込まれるかのように、再び彼の胸の中にすっぽりと収まっていた。
「デザートがまだだよ。」
泉はゆっくりと千夏の頬に手を当てて髪をかきあげながら顔を自分に向けると優しくキスをした。
「デザートに千夏さん食べたい。」
「駄目よ。」
「やだ。食べる。」
駄々をこねるように子供のように頬を膨らませて見せ、キスを続けながら泉はソファに座り千夏を自分の膝の上に座らせた。
「明日、仕事だもの…。ダメ…。」
偶然にも知人の兄だとはいえ、出会ってまだ二度目の彼と距離が近くなるたび、胸の奥がざわついた。軽々しく関係を重ねる自分にはなりたくない——そう思いながらも、心の奥のどこかで不思議な落ち着きと期待が入り混じる。自分ではまだ気づいていないけれど、知らず知らずのうちに、声だけではなく彼の存在自体に惹かれているのかもしれない。その思いに戸惑いながらも、どうしても拒否できずにいる自分がいた。
「明日が仕事じゃなければイイの?」
「……そう言うわけじゃない。」
泉の手が千夏の腰に触れた瞬間、思わず身体が硬くなる。手はそっと背中に沿って動き、千夏は軽く息を呑んだ。予想していなかった展開の早い距離感に戸惑う。
「ちょっ…。」
千夏は泉の手から逃れようともがいたが、細身の割には意外に力のある彼にあっさりと捕まってしまった。
「千夏さん、可愛い。」
千夏はクルッと反転させられ、視界に天井が広がった。
(このまま、いつでも都合よく扱われる軽い女にはなりたくない……)
心の中で強くそう思っても、泉の手慣れた動きに、どうしても上手く抵抗できない自分がいた。
「千夏さんの体ってエロいよね。」
器用に千夏の服を脱がしながら息を荒くして泉は言った。
(そうよ、彼の声がいけないの!こんな良い声で囁かれたら抗えない。)
「今日もお姫様だっこしてあげるね。」
そう言うと泉はスッと千夏を抱きかかえ、あの夜と同じように寝室へと運んだ。