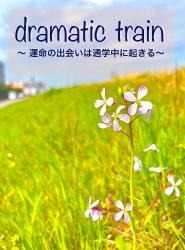駐車場に停めたシルバーの車の後部座席には、澪が静かに眠っていた。凪の大きな上着が、その小さな体をすっぽりと包み込んでいる。まるで守るようにかけられた布地の隙間から、澪の細い指が少しだけ覗いていた。
外の気温に比べると地下駐車場の空気は冷たく、街灯の明かりが車体に淡い光を落としている。
体調が悪いせいなのか、あるいは薬のせいなのか――
澪は処置室を出て千夏の腕に抱かれたまま、駐車場へ向かう途中で眠ってしまった。
その寝息は小さく、規則正しく、まるで「もう大丈夫」と告げるように穏やかだった。
千夏は後部座席のドアをそっと閉め、助手席に滑り込んだ。
凪はエレベーター横の自販機で買った、小さなペットボトル入りのコーヒーを差し出す。
「……ありがとう。」
「………。」
空調の微かな風が頬をなでる。エンジン音のない電気自動車の中で、キャップをひねるカチリという音だけが響いた。
澪の年齢。
幼い頃の凪にそっくりな顔。
そして――凪がアメリカへ行ってから、千夏が一度も連絡をくれなかった理由。
彼女の沈黙も、遠ざけた態度も、すべてが一本の線でつながっていく。
凪は、ようやくすべてのピースがはまったことを悟った。
千夏は、凪の視線に気づいていた。
隠し通せると思っていた秘密が、とうとう露わになってしまったのだ。
胸の奥がざわめく。
職場から病院まで付き添ってくれたことへの感謝を伝えたい。
それだけじゃない。
今も昔も、凪のことを変わらず大切に思っている、その気持ちも――。
けれど、何から話せばいいのだろう。
言葉は喉の奥で絡まり、息とともに消えていく。
ただ、俯くことしかできなかった。
沈黙が重く車内を包み、時間だけがゆっくりと流れていく。やがて、運転席から凪の手が伸び、千夏の手を静かに包んだ。けれど、それでも言葉は生まれない。
ただ、触れ合った手の温もりだけが、二人の間に確かなものとして残っていた。
「いつまで隠しておくつもりだったの? もしかして、一生、俺に言わないつもりだった?」
先に口を開いたのは、凪だった。
その声には、怒りよりも、混乱と痛みが混じっていた。
千夏は視線を落とし、指先をぎゅっと握りしめた。
「……いつかは話さなくちゃと思ってた。でも、今回たまたま再会して……デビューが決まってるって聞いたから、今じゃないって思ったの。」
「おろそうとは思わなかった?」
その言葉に、千夏の肩が小さく震えた。
唇を噛みしめ、やっとの思いで言葉を紡ぐ。
「ごめんなさい……。勝手に決めて、相談もしないで産んでしまって……。でも、大切な凪との“絆”だと思ったら、どうしても手放せなかったの。
誰にも言わないし、養育費の請求もしない。凪には、絶対に迷惑かけないから……安心して。」
その必死な声を聞きながら、凪の胸の奥で何かがきしむ。
“絆”という言葉が、どうしようもなく心に刺さった。
「俺との絆……? だったら、なんで連絡しなかったんだよ……っ!」
声が少し荒くなる。
「俺だって、千夏さんとの間にそんな大切な繋がりがあるなら、もっと早く帰ってきたのに……。」
はっとして、凪は自分の声の大きさに気づいた。
後部座席では、澪が小さな寝息を立てている。
彼女の寝顔を一瞥し、凪は声を落とした。
「……でも、どうして俺に隠そうとしたんだ。」
千夏は静かに答えた。
「凪には夢があって、アメリカに行ったでしょ。だから……集中してほしかったの。」
その声は、涙を堪えるようにかすかに震えていた。
言葉の端がほどけるたび、今まで堪えていた胸の奥の痛みまで滲み出してしまいそうだった。
凪はしばらく黙って千夏を見つめていた。
その瞳には、懐かしさと迷い、そして決意が入り混じっていた。
「千夏さん……。アメリカに行く前、最後に会ったときの俺は、ただの子供だったかもしれない。高校を卒業したばかりで、何もわかってなかった。」
彼は静かに息を整え、言葉を紡いだ。
「でも今の俺は違う。酒も飲めるし、車も運転できる。ひとりで生きていける――いや、千夏さんと澪ちゃんをちゃんと守っていける。大人の男になったんだ。」
彼の声には、若さの勢いではなく、年月を重ねて得た確かな温度があった。
「俺は、愛してる人を泣かせたり、守れなかったりするような情けない人間にはなりたくない。……だから、今度こそ、俺のプロポーズを受けてくれないか?」
千夏の胸の奥で、何かが静かに崩れ落ちた。
澪のことを知っても、なお自分を選んでくれる――その事実が、ただ嬉しかった。
気づけば、頬を伝う涙が止まらない。
「……愛してる。ずっと、ずっと千夏さんだけを思ってたんだ。」
凪は握っていた千夏の手を、もう一度強く握りしめた。
その手の温もりが、これまでの孤独をゆっくりと溶かしていくようだった。
千夏は胸の奥が熱くなり、こらえきれずに凪の手を握り返す。
それだけで、何も言えなくても、想いが通じ合う気がした。
凪はそのまま、握っていない方の手をそっと伸ばした。
千夏の頬を伝う涙を、指先で丁寧に拭う。
そして――ためらうように、けれど確かな意志を込めて、彼女にゆっくりと唇を重ねた。
短く、やわらかいキスだった。
離れたあとも、互いの息が触れ合うほどの距離で、凪が囁く。
「……うん、って言ってよ。千夏さん。」
その笑顔はどこまでも優しく、どこか澪の面影を映していた。
胸の奥が痛むほど、懐かしくて、愛おしい。
「……うん。本当に、凪は私でいいの?」
問いかける声は涙に濡れ、震えていた。
「千夏さんじゃなくちゃ、嫌なんだ。」
凪の言葉はまっすぐで、迷いがなかった。
その瞬間、千夏の中で何かが静かにほどけていく。
過去の痛みも、後悔も、すべてがその言葉に包まれていくようだった。
外の気温に比べると地下駐車場の空気は冷たく、街灯の明かりが車体に淡い光を落としている。
体調が悪いせいなのか、あるいは薬のせいなのか――
澪は処置室を出て千夏の腕に抱かれたまま、駐車場へ向かう途中で眠ってしまった。
その寝息は小さく、規則正しく、まるで「もう大丈夫」と告げるように穏やかだった。
千夏は後部座席のドアをそっと閉め、助手席に滑り込んだ。
凪はエレベーター横の自販機で買った、小さなペットボトル入りのコーヒーを差し出す。
「……ありがとう。」
「………。」
空調の微かな風が頬をなでる。エンジン音のない電気自動車の中で、キャップをひねるカチリという音だけが響いた。
澪の年齢。
幼い頃の凪にそっくりな顔。
そして――凪がアメリカへ行ってから、千夏が一度も連絡をくれなかった理由。
彼女の沈黙も、遠ざけた態度も、すべてが一本の線でつながっていく。
凪は、ようやくすべてのピースがはまったことを悟った。
千夏は、凪の視線に気づいていた。
隠し通せると思っていた秘密が、とうとう露わになってしまったのだ。
胸の奥がざわめく。
職場から病院まで付き添ってくれたことへの感謝を伝えたい。
それだけじゃない。
今も昔も、凪のことを変わらず大切に思っている、その気持ちも――。
けれど、何から話せばいいのだろう。
言葉は喉の奥で絡まり、息とともに消えていく。
ただ、俯くことしかできなかった。
沈黙が重く車内を包み、時間だけがゆっくりと流れていく。やがて、運転席から凪の手が伸び、千夏の手を静かに包んだ。けれど、それでも言葉は生まれない。
ただ、触れ合った手の温もりだけが、二人の間に確かなものとして残っていた。
「いつまで隠しておくつもりだったの? もしかして、一生、俺に言わないつもりだった?」
先に口を開いたのは、凪だった。
その声には、怒りよりも、混乱と痛みが混じっていた。
千夏は視線を落とし、指先をぎゅっと握りしめた。
「……いつかは話さなくちゃと思ってた。でも、今回たまたま再会して……デビューが決まってるって聞いたから、今じゃないって思ったの。」
「おろそうとは思わなかった?」
その言葉に、千夏の肩が小さく震えた。
唇を噛みしめ、やっとの思いで言葉を紡ぐ。
「ごめんなさい……。勝手に決めて、相談もしないで産んでしまって……。でも、大切な凪との“絆”だと思ったら、どうしても手放せなかったの。
誰にも言わないし、養育費の請求もしない。凪には、絶対に迷惑かけないから……安心して。」
その必死な声を聞きながら、凪の胸の奥で何かがきしむ。
“絆”という言葉が、どうしようもなく心に刺さった。
「俺との絆……? だったら、なんで連絡しなかったんだよ……っ!」
声が少し荒くなる。
「俺だって、千夏さんとの間にそんな大切な繋がりがあるなら、もっと早く帰ってきたのに……。」
はっとして、凪は自分の声の大きさに気づいた。
後部座席では、澪が小さな寝息を立てている。
彼女の寝顔を一瞥し、凪は声を落とした。
「……でも、どうして俺に隠そうとしたんだ。」
千夏は静かに答えた。
「凪には夢があって、アメリカに行ったでしょ。だから……集中してほしかったの。」
その声は、涙を堪えるようにかすかに震えていた。
言葉の端がほどけるたび、今まで堪えていた胸の奥の痛みまで滲み出してしまいそうだった。
凪はしばらく黙って千夏を見つめていた。
その瞳には、懐かしさと迷い、そして決意が入り混じっていた。
「千夏さん……。アメリカに行く前、最後に会ったときの俺は、ただの子供だったかもしれない。高校を卒業したばかりで、何もわかってなかった。」
彼は静かに息を整え、言葉を紡いだ。
「でも今の俺は違う。酒も飲めるし、車も運転できる。ひとりで生きていける――いや、千夏さんと澪ちゃんをちゃんと守っていける。大人の男になったんだ。」
彼の声には、若さの勢いではなく、年月を重ねて得た確かな温度があった。
「俺は、愛してる人を泣かせたり、守れなかったりするような情けない人間にはなりたくない。……だから、今度こそ、俺のプロポーズを受けてくれないか?」
千夏の胸の奥で、何かが静かに崩れ落ちた。
澪のことを知っても、なお自分を選んでくれる――その事実が、ただ嬉しかった。
気づけば、頬を伝う涙が止まらない。
「……愛してる。ずっと、ずっと千夏さんだけを思ってたんだ。」
凪は握っていた千夏の手を、もう一度強く握りしめた。
その手の温もりが、これまでの孤独をゆっくりと溶かしていくようだった。
千夏は胸の奥が熱くなり、こらえきれずに凪の手を握り返す。
それだけで、何も言えなくても、想いが通じ合う気がした。
凪はそのまま、握っていない方の手をそっと伸ばした。
千夏の頬を伝う涙を、指先で丁寧に拭う。
そして――ためらうように、けれど確かな意志を込めて、彼女にゆっくりと唇を重ねた。
短く、やわらかいキスだった。
離れたあとも、互いの息が触れ合うほどの距離で、凪が囁く。
「……うん、って言ってよ。千夏さん。」
その笑顔はどこまでも優しく、どこか澪の面影を映していた。
胸の奥が痛むほど、懐かしくて、愛おしい。
「……うん。本当に、凪は私でいいの?」
問いかける声は涙に濡れ、震えていた。
「千夏さんじゃなくちゃ、嫌なんだ。」
凪の言葉はまっすぐで、迷いがなかった。
その瞬間、千夏の中で何かが静かにほどけていく。
過去の痛みも、後悔も、すべてがその言葉に包まれていくようだった。