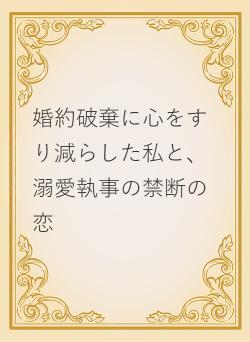フィーネはゆっくりと目を開けて目の前にいるオスヴァルトを見上げると、ふっと笑った。
(そうね……、私なんか吸血鬼に食べられちゃうくらいがちょうどいいのかもね)
突然何かを悟り、自分の死を覚悟したような笑いを浮かべたフィーネに、オスヴァルトは真剣な面持ちで尋ねる。
「君はもしかして私に食べられると思っているのかい?」
「え……?」
きょとんとしたフィーネの顔に優しく手を添えると、これまた特別に優しい目で彼女を見つめる。
「そんなことしないよ」
オスヴァルトはそっとフィーネの髪をなでると、ちゅっと唇とつける。
「私は君のことを食べたりしない。安心して」
低くて甘い言葉にフィーネの体温は少しだけ上がった──
(そうね……、私なんか吸血鬼に食べられちゃうくらいがちょうどいいのかもね)
突然何かを悟り、自分の死を覚悟したような笑いを浮かべたフィーネに、オスヴァルトは真剣な面持ちで尋ねる。
「君はもしかして私に食べられると思っているのかい?」
「え……?」
きょとんとしたフィーネの顔に優しく手を添えると、これまた特別に優しい目で彼女を見つめる。
「そんなことしないよ」
オスヴァルトはそっとフィーネの髪をなでると、ちゅっと唇とつける。
「私は君のことを食べたりしない。安心して」
低くて甘い言葉にフィーネの体温は少しだけ上がった──