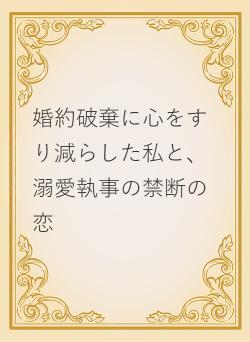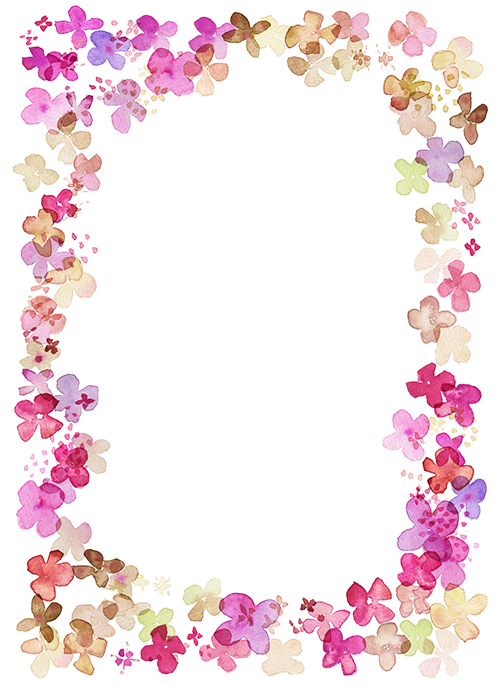次期公爵としてもう決まったレールを歩くことに、オズは嫌気がさしていた。
メイドや執事も全員彼を叱ろうとせず、何をするにも褒めたたえる。
「さすがでございますっ! オスヴァルト坊ちゃま!」
「これは将来安泰ですな」
大人たちの期待の目とそして誰も自分自身を見てくれていないという虚しさがそこにはあった。
だが、幸いにも彼の父と母は彼を溺愛して、そして愛していた。
そんな人並みの愛を感じられて、オスヴァルトはありがたいと思っていたし、幸せだなと思ってもいた。
でも、何か、どこか足りないような気がしていた──
メイドや執事も全員彼を叱ろうとせず、何をするにも褒めたたえる。
「さすがでございますっ! オスヴァルト坊ちゃま!」
「これは将来安泰ですな」
大人たちの期待の目とそして誰も自分自身を見てくれていないという虚しさがそこにはあった。
だが、幸いにも彼の父と母は彼を溺愛して、そして愛していた。
そんな人並みの愛を感じられて、オスヴァルトはありがたいと思っていたし、幸せだなと思ってもいた。
でも、何か、どこか足りないような気がしていた──