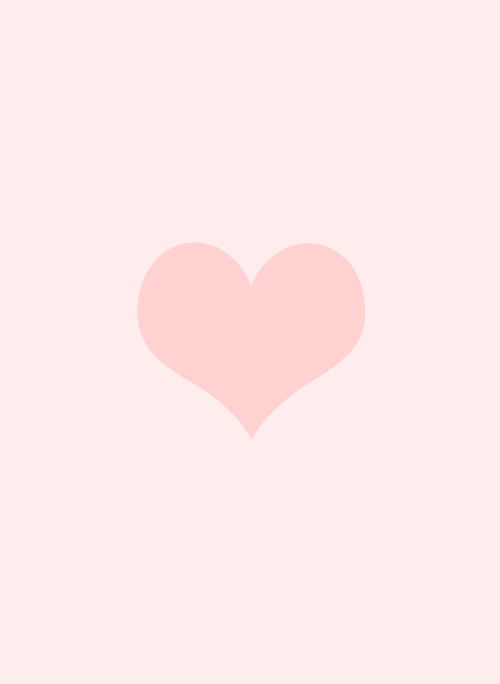『ここに来て先生達と話すと、日本に帰ってきたんだなって実感したよ。相変わらず依子さんの料理も美味いし。今日は瑠衣も作ってくれたのか?』
『はい。来年から社会人ですし、さすがに料理のひとつくらいできないと困ると思って教わってるんです』
そのままふたりで少しの時間、話をした。
大和がアメリカでどんな生活を送っていたのか、瑠衣が『アナスタシア』という一流高級ホテルへの内定が決まり、今はフロント業務に必要な英語を猛特訓をしているなど、話題は尽きなかった。
『就職か。二年……いや、ほぼ三年ぶりくらいか。変わるわけだな』
『なにがですか?』
『いや。こっちの話。それより、英語の勉強を?』
『そうなんです。フロントならやっぱり英語ができた方がいいと思って。一度留学も視野に入れたんですけど、尻込みしちゃいました。アメリカはどうでしたか? 弁護士さんはただでさえ難しい用語が多そうなのに、それを英語でこなせるなんて尊敬しかないです。やっぱり、いずれは向こうで活躍したいですか?』
『うーん、そうだな。機会があれば。やり甲斐はあったよ。とにかくスケールの大きな案件が多いし、日本とじゃ弁護士の仕事の幅もかなり違ったし』
苦笑いで言葉を濁され、さすがに所属している事務所の所長の娘に〝いつかアメリカに行きたい〟とは言い辛いのではと気付いた。
会社の制度で留学したのだから、その分事務所に利益をもたらすべきだと考えているのかもしれない。
けれど優秀な大和ならば、いずれ留学先で体験してきたような大きな案件に携わりたいと思うようになるのではないか。
如月法律事務所だって日本有数の事務所だけれど、彼の言うようにアメリカと比べればスケールが違う。
その時、瑠衣は『そろそろ戻ろうかな』と腰を上げた大和を見上げて、彼はいつかアメリカに行ってしまうのかもしれないと、少し寂しく感じたのだった。