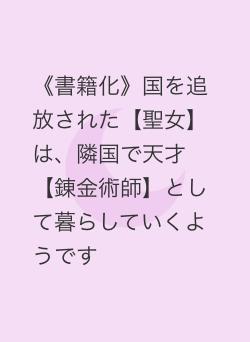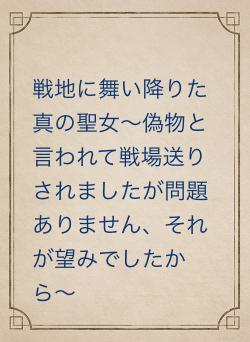「少なくともミザリーの記憶にある人間関係は、ゲームの設定と同じなのね」
ゲームの攻略対象である七王子、それぞれが隠し持つトラウマとそれを植え付けたミザリーへの深い憎しみを持つ。
ミザリーの記憶を知った私にとっては、事の発端やその後の原因もほんの些細なすれ違いによるものばかり。
だけど、人間関係が不器用なミザリーはそれを肥大化させてしまったみたい。
「うーん。色々とこじらせちゃってるなぁ。ヒロインがどうやって落としていくかは暗記してるから、どうにかできないかな……」
ミザリーと同学年で入学したヒロインは、三年間の学園生活で攻略対象と恋仲になる。
その王子が過去との決別として、ミザリーを処刑してハッピーエンド!
ってことなんだけど、残念ながら現在ミザリーになってしまった私にとってはバッドエンドの何物でもない。
ひとまずは処刑を思い留めてくれるくらいには、自分の悪い評判をなんとかしないと。
ふと、ゲーム中にミザリーと一緒になってヒロインに嫌がらせをしてくる、取り巻きの令嬢たちを思い出した。
ヒロインに嫌がらせをするのは、ミザリーの使いとして、取り巻きの令嬢たちがあの手この手でヒロインに嫌がらせをする。
「あの取り巻きたちだって、本当のミザリーの友人ではないのよね。最終的にミザリーが劣勢に陥ると容赦なく切ろうとするし……」
今の自分、ミザリーに対して本心から好意を抱いている人間はいないみたい。
あくまでミザリーの公爵令嬢という肩書きが重要、ということなのよね。
「しょうがない。守ってくれる人が居ないなら、自分の身は自分で守れるようにならないとね!」
私はミザリーの記憶にあるであろう、一つの知識にアクセスする。
それは現実にはなかったゲームの設定の一つ、魔法。
貴族のほとんどは星の守護を宿し、ミザリーも例に漏れない。
庶民で守護を宿す者は稀だが、能力が認められると、将来の国政の担い手候補として、貴族と同じ学園に送られる。
ヒロインはその中でも陽の星の守護を持つ。
一方、ミザリーは冥の星の守護を宿していた。
星の守護を持つ者はその星の属性に沿った魔法を習得できる。
ミザリーの扱うことの出来る魔法は「ペイン」や「ホラー」といった幻痛や幻覚を相手に与えるもの。
ゲームの中では様々な場所でミザリーがヒロインや王子などに使ったと言及があるが、最後まで証拠を見せなかった。
弁明もしないけど、分からないように嫌がらせを行う陰湿さ。
私がミザリーが処刑されてスッキリしていた理由がこれなんだけど。
「うー、ゲームやってる時はなんてやな奴っ! って思ってたけど、記憶を辿るとそんなことしそうにないのよねぇ。まぁ、それはその時になれば分かるかな?」
そんな魔法の知識に目を向けたのは今後のため。
ミザリーは初級と言えるこの魔法しか使って来なかったが、対するヒロインは育てれば様々な魔法を習得していく。
当然と言うべきか、鍛錬を積んだ後で覚える魔法ほど、強力な効果を持つ。
一人で生き残ることを考えると、私もゲームのヒロインみたいに鍛えておくべきよね。
「今日から毎日、ゲームみたいに練習しないとね。えーっと、確か練習用の水晶が必要なんだけど……」
部屋を見渡してもそれらしい物は見当たらない。
ミザリーの記憶を辿ってもこの部屋にはそもそも無いようだった。
「えーいっ! そんなんだからヒロインなんかに負けるのよ! あ、そうだ。メイドさんに持ってきてもらお。そんな珍しいものじゃないはずだし、きっとすぐよね」
私は陽気に鼻歌を歌いながら扉へと向かう。
扉を自ら開けるとその隙間から顔を出し、側仕えのメイドの一人に声をかける。
「ねぇ。悪いのだけれど。魔法練習用の水晶を一つ持ってきてちょうだい? 出来るだけ早く、お願いね」
「え? は、はい! かしこまりましたっ! ただいま、すぐにっ!!」
顔を向けられたメイドは青ざめた顔で返事をしてから、まるでその場から逃げ出すような勢いで駆け出して行った。
周りに残ったメイドたちも自分の方に及ぶのを危惧しているのか緊張した面持ちだ。
「どうしたのかしら。うふふ。変な人ねぇ?」
私はとりあえずはその場に残ったメイドに愛想笑いを振りまく。
顔を向けられたメイドたちは複雑な顔をしたまま、私が扉を閉めるまで微動だにしなかった。
前途多難……まずはメイドたちの信頼を勝ち取った方がいいのかしら……
ゲームの攻略対象である七王子、それぞれが隠し持つトラウマとそれを植え付けたミザリーへの深い憎しみを持つ。
ミザリーの記憶を知った私にとっては、事の発端やその後の原因もほんの些細なすれ違いによるものばかり。
だけど、人間関係が不器用なミザリーはそれを肥大化させてしまったみたい。
「うーん。色々とこじらせちゃってるなぁ。ヒロインがどうやって落としていくかは暗記してるから、どうにかできないかな……」
ミザリーと同学年で入学したヒロインは、三年間の学園生活で攻略対象と恋仲になる。
その王子が過去との決別として、ミザリーを処刑してハッピーエンド!
ってことなんだけど、残念ながら現在ミザリーになってしまった私にとってはバッドエンドの何物でもない。
ひとまずは処刑を思い留めてくれるくらいには、自分の悪い評判をなんとかしないと。
ふと、ゲーム中にミザリーと一緒になってヒロインに嫌がらせをしてくる、取り巻きの令嬢たちを思い出した。
ヒロインに嫌がらせをするのは、ミザリーの使いとして、取り巻きの令嬢たちがあの手この手でヒロインに嫌がらせをする。
「あの取り巻きたちだって、本当のミザリーの友人ではないのよね。最終的にミザリーが劣勢に陥ると容赦なく切ろうとするし……」
今の自分、ミザリーに対して本心から好意を抱いている人間はいないみたい。
あくまでミザリーの公爵令嬢という肩書きが重要、ということなのよね。
「しょうがない。守ってくれる人が居ないなら、自分の身は自分で守れるようにならないとね!」
私はミザリーの記憶にあるであろう、一つの知識にアクセスする。
それは現実にはなかったゲームの設定の一つ、魔法。
貴族のほとんどは星の守護を宿し、ミザリーも例に漏れない。
庶民で守護を宿す者は稀だが、能力が認められると、将来の国政の担い手候補として、貴族と同じ学園に送られる。
ヒロインはその中でも陽の星の守護を持つ。
一方、ミザリーは冥の星の守護を宿していた。
星の守護を持つ者はその星の属性に沿った魔法を習得できる。
ミザリーの扱うことの出来る魔法は「ペイン」や「ホラー」といった幻痛や幻覚を相手に与えるもの。
ゲームの中では様々な場所でミザリーがヒロインや王子などに使ったと言及があるが、最後まで証拠を見せなかった。
弁明もしないけど、分からないように嫌がらせを行う陰湿さ。
私がミザリーが処刑されてスッキリしていた理由がこれなんだけど。
「うー、ゲームやってる時はなんてやな奴っ! って思ってたけど、記憶を辿るとそんなことしそうにないのよねぇ。まぁ、それはその時になれば分かるかな?」
そんな魔法の知識に目を向けたのは今後のため。
ミザリーは初級と言えるこの魔法しか使って来なかったが、対するヒロインは育てれば様々な魔法を習得していく。
当然と言うべきか、鍛錬を積んだ後で覚える魔法ほど、強力な効果を持つ。
一人で生き残ることを考えると、私もゲームのヒロインみたいに鍛えておくべきよね。
「今日から毎日、ゲームみたいに練習しないとね。えーっと、確か練習用の水晶が必要なんだけど……」
部屋を見渡してもそれらしい物は見当たらない。
ミザリーの記憶を辿ってもこの部屋にはそもそも無いようだった。
「えーいっ! そんなんだからヒロインなんかに負けるのよ! あ、そうだ。メイドさんに持ってきてもらお。そんな珍しいものじゃないはずだし、きっとすぐよね」
私は陽気に鼻歌を歌いながら扉へと向かう。
扉を自ら開けるとその隙間から顔を出し、側仕えのメイドの一人に声をかける。
「ねぇ。悪いのだけれど。魔法練習用の水晶を一つ持ってきてちょうだい? 出来るだけ早く、お願いね」
「え? は、はい! かしこまりましたっ! ただいま、すぐにっ!!」
顔を向けられたメイドは青ざめた顔で返事をしてから、まるでその場から逃げ出すような勢いで駆け出して行った。
周りに残ったメイドたちも自分の方に及ぶのを危惧しているのか緊張した面持ちだ。
「どうしたのかしら。うふふ。変な人ねぇ?」
私はとりあえずはその場に残ったメイドに愛想笑いを振りまく。
顔を向けられたメイドたちは複雑な顔をしたまま、私が扉を閉めるまで微動だにしなかった。
前途多難……まずはメイドたちの信頼を勝ち取った方がいいのかしら……