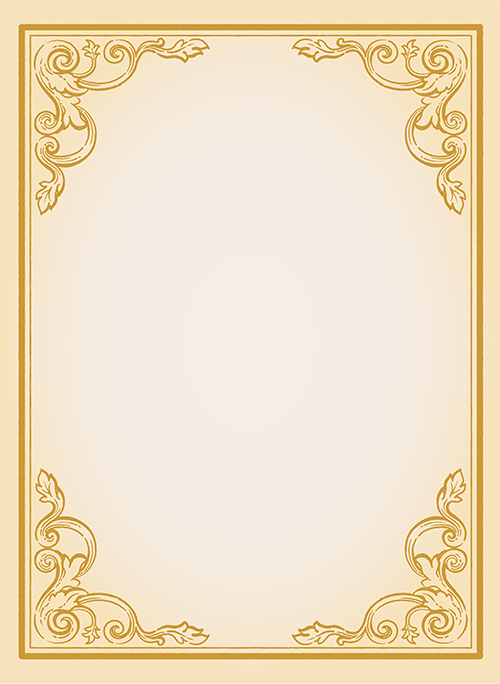「あなたは人間の両親のもとで生まれ、貧乏暮らしのために仕方なく孤児院に預けられたようよ。今までだいぶ苦労をしたのね…。でもあなたはいつか、小さな人間の男の子を膝に乗せて寝かしつけることになるわ」
その言葉が気に障った彼はその娘をギラリと睨みつける。
しかし娘は全く気にするでもなく、すました表情で彼を見つめて言った。
「あら大丈夫、誰にも言ったりしないわ。あなたが居なくなるなんて嫌だもの」
彼女はくるりと背中を向け、小屋に戻っていく。
一体何が言いたかったのだろう?
おまけに、なぜ彼女はよりにもよって自分のことを占いとやらで視ようとしたのか、全く理解が出来ない。
彼は考えるのを止め、いつものように一人檻の中で眠りについた。
しかし次の日の夜もその次の日の夜も、日付が変わる頃に娘はこっそりとバラドのいる檻の前にやってきた。
彼女の口から出るのは他愛もない話ばかり。
この見世物小屋で三本の指に入る人気の“魔女”である彼女。
そんな彼女がこんな夜更けに“野獣の子”と呼ばれた自分の元へ。
これはからかわれているとしか思えない。
いくら無口な彼でもとうとうある夜堪りかね、いつものようにやってきた娘に自分から声を掛けた。
「…毎晩のようにここへ来て、お前は一体俺に何が言いたい?」
聞いた彼女は心外とでも言うように目を瞬く。
「あら、私はあなたと話がしたいだけよ。他に理由が?…まあ、あなたは返事すらしてくれなかったけれど、こうして今夜はね。ふふっ」
彼女はそう、本当に嬉しそうに笑った。
彼は興味本位で自分に近付いただけであろう彼女が気に入らない。
しかし真っ正直な彼は寝たふりを決め込むことも出来ず、いつも無表情であまり出ない割にも不機嫌なまま今夜も彼女の話に付き合った。
その言葉が気に障った彼はその娘をギラリと睨みつける。
しかし娘は全く気にするでもなく、すました表情で彼を見つめて言った。
「あら大丈夫、誰にも言ったりしないわ。あなたが居なくなるなんて嫌だもの」
彼女はくるりと背中を向け、小屋に戻っていく。
一体何が言いたかったのだろう?
おまけに、なぜ彼女はよりにもよって自分のことを占いとやらで視ようとしたのか、全く理解が出来ない。
彼は考えるのを止め、いつものように一人檻の中で眠りについた。
しかし次の日の夜もその次の日の夜も、日付が変わる頃に娘はこっそりとバラドのいる檻の前にやってきた。
彼女の口から出るのは他愛もない話ばかり。
この見世物小屋で三本の指に入る人気の“魔女”である彼女。
そんな彼女がこんな夜更けに“野獣の子”と呼ばれた自分の元へ。
これはからかわれているとしか思えない。
いくら無口な彼でもとうとうある夜堪りかね、いつものようにやってきた娘に自分から声を掛けた。
「…毎晩のようにここへ来て、お前は一体俺に何が言いたい?」
聞いた彼女は心外とでも言うように目を瞬く。
「あら、私はあなたと話がしたいだけよ。他に理由が?…まあ、あなたは返事すらしてくれなかったけれど、こうして今夜はね。ふふっ」
彼女はそう、本当に嬉しそうに笑った。
彼は興味本位で自分に近付いただけであろう彼女が気に入らない。
しかし真っ正直な彼は寝たふりを決め込むことも出来ず、いつも無表情であまり出ない割にも不機嫌なまま今夜も彼女の話に付き合った。