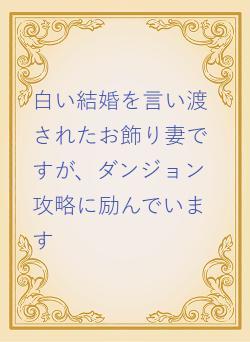化粧を落とすためメイドに乳液を借り、それをガーゼに含ませてマリエル様の顔を拭った。
そして苦戦しながらウィッグを外していると、小さなため息が聞こえた。
「痛いですよね、申し訳ありません。なにぶんこういう作業は不慣れですから……」
「いや、そうではない」
マリエル様は再びため息をついた。
「あの男、見覚えがある」
最後に合流した初老の男のことだろう。左頬に大きなほくろのある顔が印象的で何度か見かけた記憶がある。
「……男のひとりはおそらく、グラーツィ伯爵家の関係者でしょうね」
マリエル様も頷く。
「そうだ」
あの男を見かけたのはいずれもライラ様の周辺だ。
年に一、二度、柱の陰から彼女を覗き見していたマリエル様も、あの男の存在に気づいていたらしい。
グラーツィ伯爵家は先代が前国王の宰相、現当主でライラ様の父親はいま外務大臣を務めているエリート家系であり、足元をすくわれないようライラ様の周囲にも厳重な護衛体制を敷いている。
だからあの男が何年も前からライラ様の動向を探るためにつきまとっていたとは考えにくい。あの男もグラーツィ伯爵家側の人間だと考えるのが妥当だ。
おかしいと思っていたんだ。
いくらライラ様と姉が画策したお忍び訪問だったとしても、彼女の周囲には彼女が気づいていない護衛が大勢ついているはずで、その全てを出し抜いてここまでたどり着くことができるのだろうかと。
つまり、ライラ様をかどわかすという企みは、彼女の可愛らしい計略を逆手に取ったグラーツィ伯爵家の自作自演だったということだ。
もちろん、いま地下牢に閉じ込めてある男たちには後でしっかり尋問して答え合わせをするつもりだけれど。
「伯爵家の目的は何でしょうね」
親に隠し事をしたら怖い目に遭うんだぞというお仕置きにしてはやることが大掛かりすぎる。
「婚約解消だろうな」
椅子に腰かけるマリエル様の背中が丸くなった。
誘拐事件に巻き込まれる、あるいは未遂であっても、そんな物騒な土地に娘を嫁にはやれん! という難癖をつけたかったのだろうか。
ようやくウィッグを外し終えぐちゃぐちゃになった赤褐色の髪を櫛でといていると、ライラ様の馬車の到着が告げられた。
「どうなさいますか?」
服装はシルクシャツに黒いトラウザーズだ。
「構わん、このまま出迎える」
手櫛で髪を整えながら我が主が立ち上がる。
何も言えないまま、その後ろについて再び屋敷の玄関へ向かったのだった。
そして苦戦しながらウィッグを外していると、小さなため息が聞こえた。
「痛いですよね、申し訳ありません。なにぶんこういう作業は不慣れですから……」
「いや、そうではない」
マリエル様は再びため息をついた。
「あの男、見覚えがある」
最後に合流した初老の男のことだろう。左頬に大きなほくろのある顔が印象的で何度か見かけた記憶がある。
「……男のひとりはおそらく、グラーツィ伯爵家の関係者でしょうね」
マリエル様も頷く。
「そうだ」
あの男を見かけたのはいずれもライラ様の周辺だ。
年に一、二度、柱の陰から彼女を覗き見していたマリエル様も、あの男の存在に気づいていたらしい。
グラーツィ伯爵家は先代が前国王の宰相、現当主でライラ様の父親はいま外務大臣を務めているエリート家系であり、足元をすくわれないようライラ様の周囲にも厳重な護衛体制を敷いている。
だからあの男が何年も前からライラ様の動向を探るためにつきまとっていたとは考えにくい。あの男もグラーツィ伯爵家側の人間だと考えるのが妥当だ。
おかしいと思っていたんだ。
いくらライラ様と姉が画策したお忍び訪問だったとしても、彼女の周囲には彼女が気づいていない護衛が大勢ついているはずで、その全てを出し抜いてここまでたどり着くことができるのだろうかと。
つまり、ライラ様をかどわかすという企みは、彼女の可愛らしい計略を逆手に取ったグラーツィ伯爵家の自作自演だったということだ。
もちろん、いま地下牢に閉じ込めてある男たちには後でしっかり尋問して答え合わせをするつもりだけれど。
「伯爵家の目的は何でしょうね」
親に隠し事をしたら怖い目に遭うんだぞというお仕置きにしてはやることが大掛かりすぎる。
「婚約解消だろうな」
椅子に腰かけるマリエル様の背中が丸くなった。
誘拐事件に巻き込まれる、あるいは未遂であっても、そんな物騒な土地に娘を嫁にはやれん! という難癖をつけたかったのだろうか。
ようやくウィッグを外し終えぐちゃぐちゃになった赤褐色の髪を櫛でといていると、ライラ様の馬車の到着が告げられた。
「どうなさいますか?」
服装はシルクシャツに黒いトラウザーズだ。
「構わん、このまま出迎える」
手櫛で髪を整えながら我が主が立ち上がる。
何も言えないまま、その後ろについて再び屋敷の玄関へ向かったのだった。