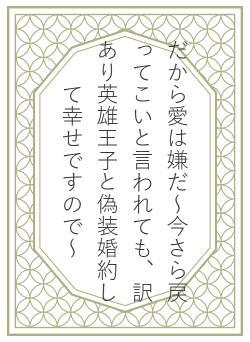ロベリアは美しい瞳にうっすら涙を浮かべながら「ウ、ウソです……ごめんなさい」とつぶやいた。
(ウソ、だったのか)
つい本気にしてしまい、ダグラスはもう少しでロベリアが差し出したサンドイッチを食べるところだった。周囲に気を取られすぎて、とっさの正しい状況判断ができなくなっている。
なぜかというと、今、学園中の視線がここに集まっているからだ。
それもそのはずで、学園の庭園にこの国の王子カマルとその婚約者リリー、麗しい侯爵令嬢ロベリアがそろってしまっている。
その姿を一目見ようと、学生だけでなく教師の姿まで見えた。こちらに向けられる視線の多くは羨望(せんぼう)だが、嫉妬や殺意に近いものまである。
その悪意にいちいち身体が反応してしまい、目の前にロベリアがいるのに少しも集中できない。
(これが殿下やロベリアが住んでいる世界……)
常に人から見られることが当たり前で、他者からのいろんな感情に一方的にさらされるのが当然の世界。
(生まれてから、ずっとこういう世界を生きてきたんだな)
だからこそ、誰もそのことを不思議に思っていない。
でも、ダグラスは人に見られることが当たり前の世界の住人ではなかった。カマルを守るために行動を共にしていたが、護衛のことをいちいち気にする人なんていない。
しかし、ロベリアの婚約者になった今、ダグラスも確実に違う世界へ足を踏み入れたという自覚があった。
見る側から見られる側へ。常に羨望と嫉妬を向けられる日々。
今までの人生とは違いすぎて、本来ならまいってしまいそうな変化だったが、これもロベリアと共にいるためだと思うと少しの辛さも感じなかった。
今だって、刺さるような視線を感じながらも、目の前でもぐもぐとサンドイッチを食べるロベリアが可愛くて仕方ない。
(そんなに小さな口でゆっくり食べていたら、いつ食べ終わるんだろう?)
不思議に思っていると、ロベリアは途中で食べるのをやめてしまった。
「ロベリア、もう食べないのか?」
「え? はい、お腹がいっぱいで……」
「これだけしか食べていないのに?」
「けっこう食べましたよ。ダグラス様……じゃなくて! ダグラスは、もっと食べられるの?」
こくりとうなずくと、ロベリアに「じゃあ、残りだけど食べる?」と聞かれた。ふと、さきほどリリーが手に持っていたウィンナーを、カマルがリリーの手を引き寄せて食べていたことを思い出す。
(ああいうのが、恋人同士の礼儀なのかもしれないな)
詳しいことはわからないが、カマルがやっていたことに間違いはないはず。
ダグラスは、ロベリアの細い手首をそっとつかむと引き寄せ、その手に持っている食べかけのサンドイッチにかぶりついた。
ロベリアの瞳が大きく見開いている。一瞬『何か間違ったか!?』とあせったが、赤くなったロベリアの顔に笑みが浮かんだので、ダグラスはホッと胸をなでおろした。
「ふふっ嬉しい」
幸せそうに微笑むロベリアから目が離せない。
「実は私、ダグラスと一緒に学生らしいことをしてみたいって思っていたの」
「学生らしいこと?」
「そう、でもそれが何かはよくわからなくて……」
ロベリアがそんなことを思っているなんて知らなかった。確かに、言われてみれば、今までカマルの護衛が第一で、ダグラスは学生らしいことをしてこなかった。
そのせいで、ロベリアに寂しい思いをさせていたのかもしれない。
「こうして、一緒にお昼を食べるのって学生らしいわよね?」
「そうだと思う」
「ひとつ、素敵な思い出ができたわ」
一生幸せにすると決めた女性は、こんなにも簡単なことで喜んでくれる。
「ロベリア、これからも一緒に学生らしいことをして思い出を作っていこう」
ロベリアがあまりに幸せそうに笑ってくれるので、ダグラスはいつの間にか周囲の視線が気にならなくなっていた。
「あ、そうだ」
制服の胸ポケットからダグラスは、飾り気のない封筒を取り出した。この手紙の送り主は、ダグラスの父だ。
父は侯爵令嬢ロベリアとの婚約を認めてくれたものの、まだ半信半疑でいるらしい。手紙には、『一度、家に帰ってきて話を聞かせてくれ』と書かれていた。
「実は、今度の長期休暇、領地に帰るつもりなんだ」
「そうなのね……」
しょんぼりしてしまったロベリアを、ダグラスは勇気を振り絞って誘ってみた。
「その、ロベリアさえ良ければ、一緒に来ないか?」
とたんにパァと輝いたロベリアの顔を見て、返事を聞く前に答えがわかってしまいダグラスの口元が緩む。
「私が行っていいの?」
「ロベリアが来てくれると嬉しい」
「行くわ!」
今まで長期休暇を楽しみにしたことがなかったが、今度の休暇は楽しみで仕方がない。またひとつロベリアとの素敵な思い出と作れそうで、ダグラスの心は弾んだ。
(ウソ、だったのか)
つい本気にしてしまい、ダグラスはもう少しでロベリアが差し出したサンドイッチを食べるところだった。周囲に気を取られすぎて、とっさの正しい状況判断ができなくなっている。
なぜかというと、今、学園中の視線がここに集まっているからだ。
それもそのはずで、学園の庭園にこの国の王子カマルとその婚約者リリー、麗しい侯爵令嬢ロベリアがそろってしまっている。
その姿を一目見ようと、学生だけでなく教師の姿まで見えた。こちらに向けられる視線の多くは羨望(せんぼう)だが、嫉妬や殺意に近いものまである。
その悪意にいちいち身体が反応してしまい、目の前にロベリアがいるのに少しも集中できない。
(これが殿下やロベリアが住んでいる世界……)
常に人から見られることが当たり前で、他者からのいろんな感情に一方的にさらされるのが当然の世界。
(生まれてから、ずっとこういう世界を生きてきたんだな)
だからこそ、誰もそのことを不思議に思っていない。
でも、ダグラスは人に見られることが当たり前の世界の住人ではなかった。カマルを守るために行動を共にしていたが、護衛のことをいちいち気にする人なんていない。
しかし、ロベリアの婚約者になった今、ダグラスも確実に違う世界へ足を踏み入れたという自覚があった。
見る側から見られる側へ。常に羨望と嫉妬を向けられる日々。
今までの人生とは違いすぎて、本来ならまいってしまいそうな変化だったが、これもロベリアと共にいるためだと思うと少しの辛さも感じなかった。
今だって、刺さるような視線を感じながらも、目の前でもぐもぐとサンドイッチを食べるロベリアが可愛くて仕方ない。
(そんなに小さな口でゆっくり食べていたら、いつ食べ終わるんだろう?)
不思議に思っていると、ロベリアは途中で食べるのをやめてしまった。
「ロベリア、もう食べないのか?」
「え? はい、お腹がいっぱいで……」
「これだけしか食べていないのに?」
「けっこう食べましたよ。ダグラス様……じゃなくて! ダグラスは、もっと食べられるの?」
こくりとうなずくと、ロベリアに「じゃあ、残りだけど食べる?」と聞かれた。ふと、さきほどリリーが手に持っていたウィンナーを、カマルがリリーの手を引き寄せて食べていたことを思い出す。
(ああいうのが、恋人同士の礼儀なのかもしれないな)
詳しいことはわからないが、カマルがやっていたことに間違いはないはず。
ダグラスは、ロベリアの細い手首をそっとつかむと引き寄せ、その手に持っている食べかけのサンドイッチにかぶりついた。
ロベリアの瞳が大きく見開いている。一瞬『何か間違ったか!?』とあせったが、赤くなったロベリアの顔に笑みが浮かんだので、ダグラスはホッと胸をなでおろした。
「ふふっ嬉しい」
幸せそうに微笑むロベリアから目が離せない。
「実は私、ダグラスと一緒に学生らしいことをしてみたいって思っていたの」
「学生らしいこと?」
「そう、でもそれが何かはよくわからなくて……」
ロベリアがそんなことを思っているなんて知らなかった。確かに、言われてみれば、今までカマルの護衛が第一で、ダグラスは学生らしいことをしてこなかった。
そのせいで、ロベリアに寂しい思いをさせていたのかもしれない。
「こうして、一緒にお昼を食べるのって学生らしいわよね?」
「そうだと思う」
「ひとつ、素敵な思い出ができたわ」
一生幸せにすると決めた女性は、こんなにも簡単なことで喜んでくれる。
「ロベリア、これからも一緒に学生らしいことをして思い出を作っていこう」
ロベリアがあまりに幸せそうに笑ってくれるので、ダグラスはいつの間にか周囲の視線が気にならなくなっていた。
「あ、そうだ」
制服の胸ポケットからダグラスは、飾り気のない封筒を取り出した。この手紙の送り主は、ダグラスの父だ。
父は侯爵令嬢ロベリアとの婚約を認めてくれたものの、まだ半信半疑でいるらしい。手紙には、『一度、家に帰ってきて話を聞かせてくれ』と書かれていた。
「実は、今度の長期休暇、領地に帰るつもりなんだ」
「そうなのね……」
しょんぼりしてしまったロベリアを、ダグラスは勇気を振り絞って誘ってみた。
「その、ロベリアさえ良ければ、一緒に来ないか?」
とたんにパァと輝いたロベリアの顔を見て、返事を聞く前に答えがわかってしまいダグラスの口元が緩む。
「私が行っていいの?」
「ロベリアが来てくれると嬉しい」
「行くわ!」
今まで長期休暇を楽しみにしたことがなかったが、今度の休暇は楽しみで仕方がない。またひとつロベリアとの素敵な思い出と作れそうで、ダグラスの心は弾んだ。