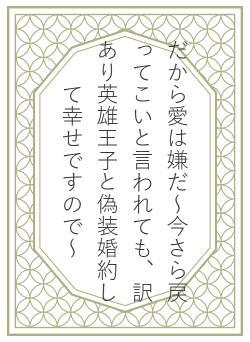カマルは「時間も遅いし、今日はこれくらいにしようか」とソファから立ち上がった。
「ロベリアと話せて楽しかったよ。よければまたダグラスの良さを話してほしい」
「そういうことでしたら喜んで!」」
ダグラスの良いところなら何時間でも語ることができてしまう。
「私もダグラス様の素敵さをお話できて、とても楽しかったです」
ニコニコ笑顔でカマルと分かれると、部屋の扉の側にダグラスが控えていた。
「ダグラス様!」
ロベリアが嬉しくなってダグラスに駆け寄ると、ダグラスは顔を背けた。
(あ、そうだったわ。ダグラス様には他に好きな女性がいるんだから、私に付きまとわれたら迷惑よね)
しょんぼりしながら「失礼しました」と会釈すると、ダグラスに「ロベリア様」と呼び止められる。
「え? はい」
ダグラスは、長い前髪の下で視線を彷徨わせたあと「殿下と何をお話されたのですか?」と聞いてくる。
「その……とても楽しそうな殿下の笑い声が聞こえたので……。もちろん、内容までは聞いていません」
カマルと二人でダグラスの素敵さを讃えることに夢中になってしまい、だいぶ声が大きくなっていたようだ。
(さすがの私も、ご本人を前にして『貴方の素敵さを讃えて盛り上がっていました』とは言えないわ)
恥ずかしくて頬が熱くなる。
「えっと、そ、それは……」
ロベリアが恥ずかしくなりうつむくと、ダグラスは「おかしなことを聞いて申し訳ありません」と礼儀正しく頭を下げた。
「い、いえ、では、私はこれで失礼しますね」
その場を去ろうとするロベリアをダグラスが引き留める。
「女子寮までお送りします」
「そんなっ! 大丈夫です!」
いくら断わってもダグラスは諦めてくれない。最終的には「ロベリア様は、その、殿下の大切なお方のようなので」と引っかかる言い方をされた。
(ん? もしかして、カマル殿下との仲を疑われているの?)
確かに状況を見ると、遅い時間にカマルに呼び出され二人きりになり楽しく談笑していたので、そう勘違いされても仕方がない。
(仕方がない、けど……。そっか、ダグラス様は、本当に私のことをなんとも思っていないのね……)
分かっていたはずなのに、ズキッと胸が痛み、不意に涙がでそうになった。
「ダグラス様、それは誤解です。殿下と私は何もありません」
そう伝えたがダグラスは無理やりにでも、ロベリアを女子寮まで送るつもりらしい。
(お仕えする殿下の想い人かもしれないから、私を大切に扱ってくれるのね)
断わることを諦めてダグラスに送ってもらうと、外はもう暗くなっていた。星々が煌めき、綺麗な半月が夜空を照らしている。とてもロマンチックな夜を、憧れの人と二人で歩いているのに少しも心が弾まない。
女性寮の入口にたどり着くと、ダグラスはまた礼儀正しく他人行儀にロベリアに頭を下げた。
「失礼します」
「送ってくださり、ありがとうございました」
もう作り笑いを浮かべる元気もない。ダグラスの後ろ姿を見ていると、また悲しくなってきた。
(完全に……失恋しちゃった……)
見上げた半月は、涙で滲んで良く見えなかった。
*
その日から、ロベリアは学園内でカマルに良く声をかけられるようになった。カマルの背後には、いつもダグラスが控えていたが、以前のようにダグラスから声をかけてくることはなくなった。
ロベリアがダグラスに挨拶しても、興味無さそうに小さな会釈が返ってくるだけ。
(はぁ……。ダグラス様に好かれていないことは分かっていたけど、ここまであからさまに距離を取られるとつらいわ……)
ダグラスとしては、カマルの想い人と適切な距離を取っているだけだと分かっているが、それでも複雑な乙女心が傷ついてしまう。
(ダグラス様の好きな女性ってどんな方なのかしら?)
もしかするとこの学園内にいるのかもしれない。
(はっ!? ダグラス様とその方が心通じて、付き合うことになったらどうしよう……)
学園内でダグラスと、ダグラスに愛された女性が仲良さそうに過ごす姿を想像したら、胸がギュッと締め付けられる。
(わぁ……絶対無理……)
そんなことを考えているとロベリアは、ふとゲームの悪役令嬢ロベリアのことを思い出した。ゲームの中で彼女は、大好きなカマルに相手にされず、しかも、愛する人が妹のリリーと仲良く過ごす様子を毎日見せつけられるのだ。
(うわっ……地獄)
想像しただけで泣きたくなった。今ならゲームのロベリアの深い悲しみや苦しさが分かるような気がする。そして、分かってしまうからこそ、ああなってはいけないとも思った。
(そうだわ、ダグラス様に彼女ができたら、私はすぐにこの学園を辞めよう。そして、遠く離れた田舎の別荘で一人静かに暮らそう……。そうだ、それがいい……ああ、お幸せにダグラス様……)
気が付けば、ロベリアの頬は涙で濡れていた。
「お姉さま、みーつけた!」
背後で可愛らしい声がして、ロベリアの腰に細い腕が巻き付いた。振り返るとリリーが嬉しそうに抱きついている。
「って、お姉様が泣いてる!?」
リリーと側にいたレナは、驚いて二人で顔を見合わせた。
「どうしたの? はっ!? まさかあのカマル王子の護衛に何かされたんじゃ……」
リリーの口から『護衛』という言葉が出て、ロベリアはまたダグラスのことを思い出し悲しくなった。
「違うの……ダグラス様に、か、彼女ができて……」
「はぁ!? あの根暗そうで顔面凶器みたいな男に彼女が!?」
ダグラスの余りの評価の酷さに、ロベリアは少し冷静になった。
「リリー違うの、これは私の想像よ。もしダグラス様に彼女ができたら泣いちゃうなって、話で……」
「ああ、なんだ……そうよね。あんなのに優しくしてあげられるのは、聖女様並みに心が清らかで、女神様並みに慈悲深いお姉さまくらいだもの」
リリーが呆れたようにロベリアの手を引っ張った。
「もう、お姉さまったら。そんなありもしない、くだらないこと考えて泣かないでよ。今日もレナに絵の続きを描いてもらうんだからね!」
「くだらなくないわ、これはとても大切なことで……」
リリーは「はいはい」と適当に相づちをうつと、「レナ、どこで絵を描く?」と、もうロベリアの相手すらしてくれない。
「リリー……」
「はいはい、よしよし。もう本当に困ったお姉さまね」
リリーの手がロベリアの頭をなでる。その様子を見てレナが微笑みながら、スケッチブックに鉛筆を走らせた。
「ロベリアと話せて楽しかったよ。よければまたダグラスの良さを話してほしい」
「そういうことでしたら喜んで!」」
ダグラスの良いところなら何時間でも語ることができてしまう。
「私もダグラス様の素敵さをお話できて、とても楽しかったです」
ニコニコ笑顔でカマルと分かれると、部屋の扉の側にダグラスが控えていた。
「ダグラス様!」
ロベリアが嬉しくなってダグラスに駆け寄ると、ダグラスは顔を背けた。
(あ、そうだったわ。ダグラス様には他に好きな女性がいるんだから、私に付きまとわれたら迷惑よね)
しょんぼりしながら「失礼しました」と会釈すると、ダグラスに「ロベリア様」と呼び止められる。
「え? はい」
ダグラスは、長い前髪の下で視線を彷徨わせたあと「殿下と何をお話されたのですか?」と聞いてくる。
「その……とても楽しそうな殿下の笑い声が聞こえたので……。もちろん、内容までは聞いていません」
カマルと二人でダグラスの素敵さを讃えることに夢中になってしまい、だいぶ声が大きくなっていたようだ。
(さすがの私も、ご本人を前にして『貴方の素敵さを讃えて盛り上がっていました』とは言えないわ)
恥ずかしくて頬が熱くなる。
「えっと、そ、それは……」
ロベリアが恥ずかしくなりうつむくと、ダグラスは「おかしなことを聞いて申し訳ありません」と礼儀正しく頭を下げた。
「い、いえ、では、私はこれで失礼しますね」
その場を去ろうとするロベリアをダグラスが引き留める。
「女子寮までお送りします」
「そんなっ! 大丈夫です!」
いくら断わってもダグラスは諦めてくれない。最終的には「ロベリア様は、その、殿下の大切なお方のようなので」と引っかかる言い方をされた。
(ん? もしかして、カマル殿下との仲を疑われているの?)
確かに状況を見ると、遅い時間にカマルに呼び出され二人きりになり楽しく談笑していたので、そう勘違いされても仕方がない。
(仕方がない、けど……。そっか、ダグラス様は、本当に私のことをなんとも思っていないのね……)
分かっていたはずなのに、ズキッと胸が痛み、不意に涙がでそうになった。
「ダグラス様、それは誤解です。殿下と私は何もありません」
そう伝えたがダグラスは無理やりにでも、ロベリアを女子寮まで送るつもりらしい。
(お仕えする殿下の想い人かもしれないから、私を大切に扱ってくれるのね)
断わることを諦めてダグラスに送ってもらうと、外はもう暗くなっていた。星々が煌めき、綺麗な半月が夜空を照らしている。とてもロマンチックな夜を、憧れの人と二人で歩いているのに少しも心が弾まない。
女性寮の入口にたどり着くと、ダグラスはまた礼儀正しく他人行儀にロベリアに頭を下げた。
「失礼します」
「送ってくださり、ありがとうございました」
もう作り笑いを浮かべる元気もない。ダグラスの後ろ姿を見ていると、また悲しくなってきた。
(完全に……失恋しちゃった……)
見上げた半月は、涙で滲んで良く見えなかった。
*
その日から、ロベリアは学園内でカマルに良く声をかけられるようになった。カマルの背後には、いつもダグラスが控えていたが、以前のようにダグラスから声をかけてくることはなくなった。
ロベリアがダグラスに挨拶しても、興味無さそうに小さな会釈が返ってくるだけ。
(はぁ……。ダグラス様に好かれていないことは分かっていたけど、ここまであからさまに距離を取られるとつらいわ……)
ダグラスとしては、カマルの想い人と適切な距離を取っているだけだと分かっているが、それでも複雑な乙女心が傷ついてしまう。
(ダグラス様の好きな女性ってどんな方なのかしら?)
もしかするとこの学園内にいるのかもしれない。
(はっ!? ダグラス様とその方が心通じて、付き合うことになったらどうしよう……)
学園内でダグラスと、ダグラスに愛された女性が仲良さそうに過ごす姿を想像したら、胸がギュッと締め付けられる。
(わぁ……絶対無理……)
そんなことを考えているとロベリアは、ふとゲームの悪役令嬢ロベリアのことを思い出した。ゲームの中で彼女は、大好きなカマルに相手にされず、しかも、愛する人が妹のリリーと仲良く過ごす様子を毎日見せつけられるのだ。
(うわっ……地獄)
想像しただけで泣きたくなった。今ならゲームのロベリアの深い悲しみや苦しさが分かるような気がする。そして、分かってしまうからこそ、ああなってはいけないとも思った。
(そうだわ、ダグラス様に彼女ができたら、私はすぐにこの学園を辞めよう。そして、遠く離れた田舎の別荘で一人静かに暮らそう……。そうだ、それがいい……ああ、お幸せにダグラス様……)
気が付けば、ロベリアの頬は涙で濡れていた。
「お姉さま、みーつけた!」
背後で可愛らしい声がして、ロベリアの腰に細い腕が巻き付いた。振り返るとリリーが嬉しそうに抱きついている。
「って、お姉様が泣いてる!?」
リリーと側にいたレナは、驚いて二人で顔を見合わせた。
「どうしたの? はっ!? まさかあのカマル王子の護衛に何かされたんじゃ……」
リリーの口から『護衛』という言葉が出て、ロベリアはまたダグラスのことを思い出し悲しくなった。
「違うの……ダグラス様に、か、彼女ができて……」
「はぁ!? あの根暗そうで顔面凶器みたいな男に彼女が!?」
ダグラスの余りの評価の酷さに、ロベリアは少し冷静になった。
「リリー違うの、これは私の想像よ。もしダグラス様に彼女ができたら泣いちゃうなって、話で……」
「ああ、なんだ……そうよね。あんなのに優しくしてあげられるのは、聖女様並みに心が清らかで、女神様並みに慈悲深いお姉さまくらいだもの」
リリーが呆れたようにロベリアの手を引っ張った。
「もう、お姉さまったら。そんなありもしない、くだらないこと考えて泣かないでよ。今日もレナに絵の続きを描いてもらうんだからね!」
「くだらなくないわ、これはとても大切なことで……」
リリーは「はいはい」と適当に相づちをうつと、「レナ、どこで絵を描く?」と、もうロベリアの相手すらしてくれない。
「リリー……」
「はいはい、よしよし。もう本当に困ったお姉さまね」
リリーの手がロベリアの頭をなでる。その様子を見てレナが微笑みながら、スケッチブックに鉛筆を走らせた。