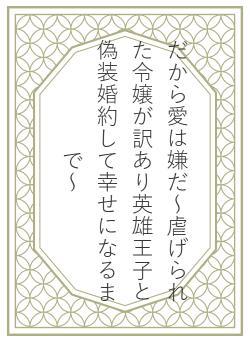夜会はお開きとなり、数日後にサティスが病にかかり療養のために離宮に移されたと聞いた。でもそれは建前で、人前に出せない王族を隔離するのが目的だった。
そのことを伝えに来てくれたバルトが言うには「兄上は、二度と離宮から出てこられないだろう」とのことだ。
一月後には、男爵令嬢エルの裁判が始まった。裁判では、エルの罪よりも、エルを利用してアレクサンドラを含む侯爵家を陥れようと画策していた貴族たちが暴かれ粛清されていった。
エルはというと、積極的に黒幕の正体を証言して捜査に協力したため、男爵家は取り潰されたがエル本人は修道院行きで済んだ。
それを聞いたアレクサンドラが、ホッと胸をなでおろすと、バルトはニコリと微笑む。
「エルが助かってホッとした?」
「ええ、まぁ。なんだか憎めない方でしたし、あの方のおかげでサティス殿下への対処法が分かったこともありましたので……」
「そんなに甘いことを言っていたらいけないよ、アリー」
愛称を呼ばれて驚くと、いつの間にかバルトがアレクサンドラの側にいた。
「君は、あの夜会の場でもあの男爵令嬢を助けようとしていたね?」
「そ、それは……」
バルトにツンッと指で頬をつつかれ、アレクサンドラは悲鳴を上げた。
「な、なんですの!?」
「そんなことでは王妃は務まらないよ……と言いたいところだけど、君に足りないところは私が補うから安心してね」
「お、王妃? バルト殿下が補う?」
「バルト殿下、だなんて。またバルバルって呼んでほしいな」
妙に迫力のある上品な笑みに圧倒されていると、バルトはアレクサンドラの長い髪に口づけをした。
「私との約束を忘れたなんて言わせないよ? 君は、私に協力を仰いだときに『お礼に、私にできることならなんでもいたします』と言ったのだから」
確かに、バルトに『真実の愛』の相手役をお願いするとき、アレクサンドラはそう言った。
「近いうちに私が王太子に選ばれるんだ。王太子妃は、もちろん君だよ」
「は、はぁ!?」
アレクサンドラが令嬢にあるまじき声を出すと、バルトは楽しそうに笑う。
「何を驚いているの? 私たちは真実の愛で結ばれているんだよ?」
「あ、あれは、演技で……」
「君だから引き受けたんだ」
澄み切った青い瞳がアレクサンドラを見つめている。
「例え一時(いっとき)でも、君の『真実の愛』の相手になれるから引き受けた。君に『アリーと呼んでください』と言われたとき、私がどれほど嬉しかったか分かる? 甘えた声でバルバルと呼ばれて、私がどれほど胸を高鳴らせていたか」
バルトの瞳が切なそうに揺れている。
「君が……アリーが本気でサティスを支えていくと決めていたから、この想いをずっと秘めていたんだ。でも、もう我慢はしない」
バルトはひざまずくと、アレクサンドラの手を取った。
「アリー。私の望みは、君と『真実の愛』をこれからもずっと育むことだよ」
想定外のお願いにアレクサンドラが口をパクパクさせていると、バルトは「無理強いはしないけど、君が『はい』と言ってくれるまでは頑張るつもりだから」と恥ずかしそうに微笑んだ。
おわり
そのことを伝えに来てくれたバルトが言うには「兄上は、二度と離宮から出てこられないだろう」とのことだ。
一月後には、男爵令嬢エルの裁判が始まった。裁判では、エルの罪よりも、エルを利用してアレクサンドラを含む侯爵家を陥れようと画策していた貴族たちが暴かれ粛清されていった。
エルはというと、積極的に黒幕の正体を証言して捜査に協力したため、男爵家は取り潰されたがエル本人は修道院行きで済んだ。
それを聞いたアレクサンドラが、ホッと胸をなでおろすと、バルトはニコリと微笑む。
「エルが助かってホッとした?」
「ええ、まぁ。なんだか憎めない方でしたし、あの方のおかげでサティス殿下への対処法が分かったこともありましたので……」
「そんなに甘いことを言っていたらいけないよ、アリー」
愛称を呼ばれて驚くと、いつの間にかバルトがアレクサンドラの側にいた。
「君は、あの夜会の場でもあの男爵令嬢を助けようとしていたね?」
「そ、それは……」
バルトにツンッと指で頬をつつかれ、アレクサンドラは悲鳴を上げた。
「な、なんですの!?」
「そんなことでは王妃は務まらないよ……と言いたいところだけど、君に足りないところは私が補うから安心してね」
「お、王妃? バルト殿下が補う?」
「バルト殿下、だなんて。またバルバルって呼んでほしいな」
妙に迫力のある上品な笑みに圧倒されていると、バルトはアレクサンドラの長い髪に口づけをした。
「私との約束を忘れたなんて言わせないよ? 君は、私に協力を仰いだときに『お礼に、私にできることならなんでもいたします』と言ったのだから」
確かに、バルトに『真実の愛』の相手役をお願いするとき、アレクサンドラはそう言った。
「近いうちに私が王太子に選ばれるんだ。王太子妃は、もちろん君だよ」
「は、はぁ!?」
アレクサンドラが令嬢にあるまじき声を出すと、バルトは楽しそうに笑う。
「何を驚いているの? 私たちは真実の愛で結ばれているんだよ?」
「あ、あれは、演技で……」
「君だから引き受けたんだ」
澄み切った青い瞳がアレクサンドラを見つめている。
「例え一時(いっとき)でも、君の『真実の愛』の相手になれるから引き受けた。君に『アリーと呼んでください』と言われたとき、私がどれほど嬉しかったか分かる? 甘えた声でバルバルと呼ばれて、私がどれほど胸を高鳴らせていたか」
バルトの瞳が切なそうに揺れている。
「君が……アリーが本気でサティスを支えていくと決めていたから、この想いをずっと秘めていたんだ。でも、もう我慢はしない」
バルトはひざまずくと、アレクサンドラの手を取った。
「アリー。私の望みは、君と『真実の愛』をこれからもずっと育むことだよ」
想定外のお願いにアレクサンドラが口をパクパクさせていると、バルトは「無理強いはしないけど、君が『はい』と言ってくれるまでは頑張るつもりだから」と恥ずかしそうに微笑んだ。
おわり