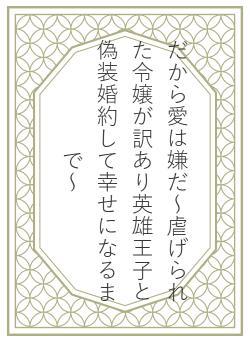「し、しかし、アレクサンドラ、お前は私の婚約者で……」
「サティス殿下だって、わたくしの婚約者ですわ。でも、真実の愛に目覚めたら、婚約者をないがしろにしても良いのですよね? だって、殿下はずっとそうされていましたもの」
アレクサンドラは、自身のドレスの裾をつかむと、無邪気に見えるようにその場で一回転した。
「このドレスは、バルバルがわたくしに贈ってくださったものですの。婚約者以外の男性からの贈り物を着て夜会に出るなど非常識ですが、殿下はわたくしにはドレスをくださらず、エル様に贈られたので、真実の愛ならばこの行為も許されるのですよね?」
呆然としているサティスをよそに、バルトはまるで恋人にするようにアレクサンドラの腰に手を回し引き寄せた。
(名演技ですわ、バルト殿下)
あまりの密着具合に内心で焦りながらも、アレクサンドラはバルトを讃えた。バルトはどこまでも優しい笑みを浮かべている。
「真実の愛に目覚めた兄上は、全ての公務を放り出してエル嬢と会っていたそうですね。ですから、真実の愛に目覚めた私も公務を放り出し、アリーに会いに来たのです。真実の愛なら許されますよね?」
バルトは「ああ、でも私の愛しのアリーに兄上の公務を押しつけるのは止めていただきたい。アリーと私の愛を育む時間が減ってしまいますから」と満面の笑みを浮かべる。
周囲の貴族たちは、サティスがこれまで何をしてきたのか、そして今、何が起こっているのか気がつき始めたようだ。
サティスに面と向かって『貴方は婚約者をないがしろにし、その女性に無実の罪を着せて断罪しようとしている。それはとても悪いことなのですよ』と言っても伝わらない。
だから、アレクサンドラは、サティスのやり方で、今、サティスの愚かさを説明している。
「ねぇ、バルバルぅ」
「なんだい? アリー」
自身の言動に照れて笑ってしまいそうだが、茶番に付き合ってくれているバルトが少しも笑わないので、アレクサンドラも必死にこらえた。
「わたくし、貴方との真実の愛に目覚めたので、エル様をいじめていませんわ」
「そうだね、アリーは私を愛しているのだから、エル嬢に嫉妬するなんて有り得ないものね」
チュッと音と立てて髪に口づけをされる。『バルト殿下、少しやりすぎでは?』と思わなくもないが、相手が残念すぎるサティスなので、これくらいやったほうが分かりやすく伝わるのかもしれない。
サティスを見れば、怒りで顔を真っ赤に染めて、握りしめた両手を震わせている。
「そんなことが許されるものか! お前たちがやっていることは、ただの不貞だ! 何が真実の愛だ、バカバカしい!」
自身の言葉にハッとなったサティスは、ようやく周囲の貴族たちの冷たい視線に気がついたようだ。
「サティス殿下だって、わたくしの婚約者ですわ。でも、真実の愛に目覚めたら、婚約者をないがしろにしても良いのですよね? だって、殿下はずっとそうされていましたもの」
アレクサンドラは、自身のドレスの裾をつかむと、無邪気に見えるようにその場で一回転した。
「このドレスは、バルバルがわたくしに贈ってくださったものですの。婚約者以外の男性からの贈り物を着て夜会に出るなど非常識ですが、殿下はわたくしにはドレスをくださらず、エル様に贈られたので、真実の愛ならばこの行為も許されるのですよね?」
呆然としているサティスをよそに、バルトはまるで恋人にするようにアレクサンドラの腰に手を回し引き寄せた。
(名演技ですわ、バルト殿下)
あまりの密着具合に内心で焦りながらも、アレクサンドラはバルトを讃えた。バルトはどこまでも優しい笑みを浮かべている。
「真実の愛に目覚めた兄上は、全ての公務を放り出してエル嬢と会っていたそうですね。ですから、真実の愛に目覚めた私も公務を放り出し、アリーに会いに来たのです。真実の愛なら許されますよね?」
バルトは「ああ、でも私の愛しのアリーに兄上の公務を押しつけるのは止めていただきたい。アリーと私の愛を育む時間が減ってしまいますから」と満面の笑みを浮かべる。
周囲の貴族たちは、サティスがこれまで何をしてきたのか、そして今、何が起こっているのか気がつき始めたようだ。
サティスに面と向かって『貴方は婚約者をないがしろにし、その女性に無実の罪を着せて断罪しようとしている。それはとても悪いことなのですよ』と言っても伝わらない。
だから、アレクサンドラは、サティスのやり方で、今、サティスの愚かさを説明している。
「ねぇ、バルバルぅ」
「なんだい? アリー」
自身の言動に照れて笑ってしまいそうだが、茶番に付き合ってくれているバルトが少しも笑わないので、アレクサンドラも必死にこらえた。
「わたくし、貴方との真実の愛に目覚めたので、エル様をいじめていませんわ」
「そうだね、アリーは私を愛しているのだから、エル嬢に嫉妬するなんて有り得ないものね」
チュッと音と立てて髪に口づけをされる。『バルト殿下、少しやりすぎでは?』と思わなくもないが、相手が残念すぎるサティスなので、これくらいやったほうが分かりやすく伝わるのかもしれない。
サティスを見れば、怒りで顔を真っ赤に染めて、握りしめた両手を震わせている。
「そんなことが許されるものか! お前たちがやっていることは、ただの不貞だ! 何が真実の愛だ、バカバカしい!」
自身の言葉にハッとなったサティスは、ようやく周囲の貴族たちの冷たい視線に気がついたようだ。