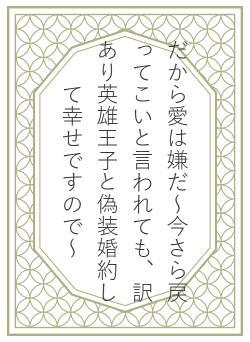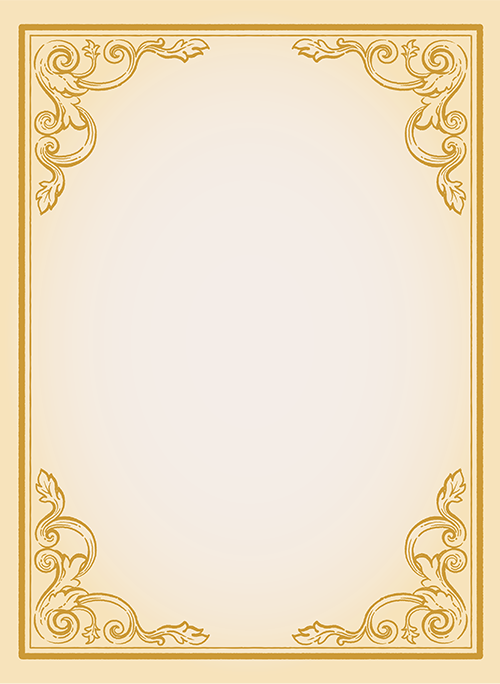アレクサンドラは、周囲の人垣の中に微笑みかけた。それに応えるように一人の男性が姿を現す。サティスと同じ金髪碧眼で、よく似た雰囲気だったが、身体を鍛えているのかサティスより体格が良く精悍な顔つきをしている。
「バルト!?」
叫ぶサティスに続き、エルも「え!? この方が第二王子殿下のバルト様?」と驚いている。
「お前、国境付近に視察へ行っていたのではないのか!?」
「はい、ですが兄上が真実の愛に目覚めたと聞いて、お祝いをするために急ぎ戻ってまいりました」
バルトがにこやかに微笑むと、エルは「素敵」と呟いた。それを見たサティスは怒りで顔を赤らめる。
「父上より与えられた公務を放棄するとは何事だ!?」
サティスの言葉を聞きながら、アレクサンドラは『その公務を私に押しつけて、女性と逢瀬を楽しんでいたのは誰でしょう? あと、公式の場で陛下を父上と言ってはいけませんとあれほどお伝えしたのに……』と思ったが、言ったところでサティスには通じない。
アレクサンドラは、バルトに視線を送った。思慮深い瞳を優しく細めてバルトがうなずく。
サティスは、言葉では説得できない。言葉が通じない相手に、どう説明すれば理解してもらえるのか? サティスの婚約者になってから、アレクサンドラはずっと悩み考えてきた。
その結果、一つの仮説が生まれた。
――サティス殿下の言動を受け入れた上で、彼と同じ行動を取ればいいのでは?
このことにアレクサンドラが気がつけたのは、エルのおかげだった。エルがどのようにサティスに取り入ったか調べたところ、サティスの全てを肯定し、全てを受け入れてあげたそうだ。
サティスがどれほど間違っていても、どれほど愚かな行動をしても咎めず讃える。そうして、エルはサティスの寵愛を得ていった。
この行動は、サティスを正しいほうへ導かなければならないと思っていたアレクサンドラには衝撃であり、学ぶことが多かった。
(エル様、ありがとうございます。貴女のおかげでわたくしは、ようやくサティス殿下とお話ができそうですわ)
アレクサンドラは優雅に微笑む。
「サティス殿下の『真実の愛』に感銘を受け、わたくしも『真実の愛』に生きることにいたしました」
アレクサンドラがバルトに右腕を伸ばすと、バルトはその手を優しくつかんで、手の甲に唇を落とす。
「ね? バルバル」
「そうだね、アリー」
事前に決めておいたこっぱずかしい愛称を呼び、バルトと見つめ合う。視線の先のバルトは、全ての令嬢たちがうっとりしてしまいそうなほど魅力的な笑みを浮かべている。
周囲の貴族たちはざわめき、サティスは「なっ!?」と叫んだ。
「あ、アリー? バルバルだと!? お前ら、正気か!?」
アレクサンドラは、こてんと首をかしげる。
「どうして驚かれるのですか? サティス殿下は、このような公式の場でもエル様を『エルル』と呼びましたし、エル様はサティス殿下を『サーサ』と呼んでいたではありませんか? 非常識な行動ですが、真実の愛ならば許されるのですよね?」
サティスは「ぐっ」と言葉に詰まった。
「バルト!?」
叫ぶサティスに続き、エルも「え!? この方が第二王子殿下のバルト様?」と驚いている。
「お前、国境付近に視察へ行っていたのではないのか!?」
「はい、ですが兄上が真実の愛に目覚めたと聞いて、お祝いをするために急ぎ戻ってまいりました」
バルトがにこやかに微笑むと、エルは「素敵」と呟いた。それを見たサティスは怒りで顔を赤らめる。
「父上より与えられた公務を放棄するとは何事だ!?」
サティスの言葉を聞きながら、アレクサンドラは『その公務を私に押しつけて、女性と逢瀬を楽しんでいたのは誰でしょう? あと、公式の場で陛下を父上と言ってはいけませんとあれほどお伝えしたのに……』と思ったが、言ったところでサティスには通じない。
アレクサンドラは、バルトに視線を送った。思慮深い瞳を優しく細めてバルトがうなずく。
サティスは、言葉では説得できない。言葉が通じない相手に、どう説明すれば理解してもらえるのか? サティスの婚約者になってから、アレクサンドラはずっと悩み考えてきた。
その結果、一つの仮説が生まれた。
――サティス殿下の言動を受け入れた上で、彼と同じ行動を取ればいいのでは?
このことにアレクサンドラが気がつけたのは、エルのおかげだった。エルがどのようにサティスに取り入ったか調べたところ、サティスの全てを肯定し、全てを受け入れてあげたそうだ。
サティスがどれほど間違っていても、どれほど愚かな行動をしても咎めず讃える。そうして、エルはサティスの寵愛を得ていった。
この行動は、サティスを正しいほうへ導かなければならないと思っていたアレクサンドラには衝撃であり、学ぶことが多かった。
(エル様、ありがとうございます。貴女のおかげでわたくしは、ようやくサティス殿下とお話ができそうですわ)
アレクサンドラは優雅に微笑む。
「サティス殿下の『真実の愛』に感銘を受け、わたくしも『真実の愛』に生きることにいたしました」
アレクサンドラがバルトに右腕を伸ばすと、バルトはその手を優しくつかんで、手の甲に唇を落とす。
「ね? バルバル」
「そうだね、アリー」
事前に決めておいたこっぱずかしい愛称を呼び、バルトと見つめ合う。視線の先のバルトは、全ての令嬢たちがうっとりしてしまいそうなほど魅力的な笑みを浮かべている。
周囲の貴族たちはざわめき、サティスは「なっ!?」と叫んだ。
「あ、アリー? バルバルだと!? お前ら、正気か!?」
アレクサンドラは、こてんと首をかしげる。
「どうして驚かれるのですか? サティス殿下は、このような公式の場でもエル様を『エルル』と呼びましたし、エル様はサティス殿下を『サーサ』と呼んでいたではありませんか? 非常識な行動ですが、真実の愛ならば許されるのですよね?」
サティスは「ぐっ」と言葉に詰まった。