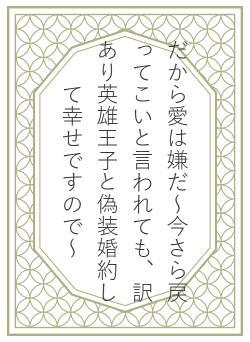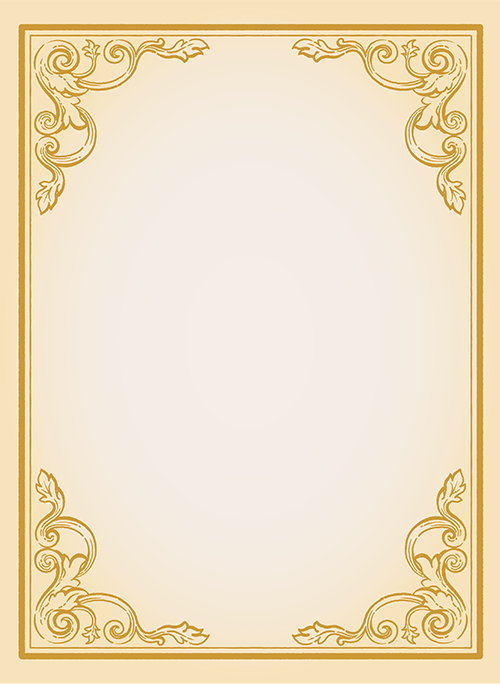その数年後に、まさか自分がサティスの婚約者に選ばれるなんて、アレクサンドラは夢にも思っていなかった。とてもじゃないがサティスを夫だなんて思えない。しかし、王族からの婚約の打診をそう簡単に断れないし、この婚約自体は侯爵家にとって利益もある。
娘に甘い父は「嫌なら断っても良い」と言ってくれたが、アレクサンドラ自身が『ここまでひどいと逆に支えがいがあるわ。私がこれまで学んできたこと全てで彼を支えたら名君にできるかもしれない』と思ってしまった。
その日から、アレクサンドラは、責任感のない婚約者があちらこちらでやらかした後始末に奔走することになる。大変だったが、それをきっかけに交友関係が広がり、たくさんの知識を得て、経験を積み上げていく過程は、それなりに充実した日々でもあった。
(それも今日で終わるのね……)
「聞いているのか!?」
サティスの怒声を無視して、アレクサンドラは口元だけで微笑んだ。
「はい、もちろんですわ。サティス殿下は、わたくしとの婚約を破棄し、新たにそちらの令嬢とご婚約をされるということですよね?」
「そうだ!」
サティスは、アレクサンドラの視線からエルを庇うように一歩前に出た。その姿は、まるで姫を守る騎士のようで、自分の姿に酔っている。
「悪女のお前がどれほど嫌がろうが、この決定は覆らない! 醜い心を持つ者など次期王妃に相応しくないからな!」
あまりに散々な言われようだったので、無駄だと分かっていたがアレクサンドラは反論した。
「殿下、お待ちください。わたくしは、そちらのエル様と一度もお話ししたことはありません」
アレクサンドラの記憶では、数カ月前に急にサティスから彼が担当している僅かな公務を押しつけられたので、事情を聞くために王宮内でサティスを探しているときに、庭園の片隅で逢瀬を楽しんでいるサティスとエルらしき人物をチラリと見かけただけだ。
「エルと話したことがないだと!? それこそ、お前がエルを無視し、虐げた証拠だ!」
「いえ、そうではなく。……そもそもどうして、男爵家のエル様が王宮内に?」
誰かが手引きでもしない限り、男爵令嬢では気軽に王宮に出入りできない。
「エルを侮辱する気か!? いいかげん嫉妬はやめろ!」
今までもそうだったが、アレクサンドラが丁寧に説明してもサティスに言葉は通じない。これまでの付き合いで言葉だけでは、サティスは理解できないと分かっていた。
「アレクサンドラ! お前がどれほど卑怯なことをしようが、私とエルを引き裂くことはできない。なぜなら私たちは、真実の愛で結ばれているからな!」
「真実の愛ですか……。まぁまぁ、それはそれは」
そう呟いたアレクサンドラは、小さく何度も頷きながら微笑んだ。
サティスが側近たちに命令するときも、『真実の愛』という言葉を熱弁していたので、すでにこちらに情報は入っていた。ちなみに、サティスの側近たちとアレクサンドラは、残念な主に仕える身として親しみを感じつつ、共に後始末をするうちに同胞のような強い絆で結ばれていたため、サティスの情報はこちらに筒抜けだ。
娘に甘い父は「嫌なら断っても良い」と言ってくれたが、アレクサンドラ自身が『ここまでひどいと逆に支えがいがあるわ。私がこれまで学んできたこと全てで彼を支えたら名君にできるかもしれない』と思ってしまった。
その日から、アレクサンドラは、責任感のない婚約者があちらこちらでやらかした後始末に奔走することになる。大変だったが、それをきっかけに交友関係が広がり、たくさんの知識を得て、経験を積み上げていく過程は、それなりに充実した日々でもあった。
(それも今日で終わるのね……)
「聞いているのか!?」
サティスの怒声を無視して、アレクサンドラは口元だけで微笑んだ。
「はい、もちろんですわ。サティス殿下は、わたくしとの婚約を破棄し、新たにそちらの令嬢とご婚約をされるということですよね?」
「そうだ!」
サティスは、アレクサンドラの視線からエルを庇うように一歩前に出た。その姿は、まるで姫を守る騎士のようで、自分の姿に酔っている。
「悪女のお前がどれほど嫌がろうが、この決定は覆らない! 醜い心を持つ者など次期王妃に相応しくないからな!」
あまりに散々な言われようだったので、無駄だと分かっていたがアレクサンドラは反論した。
「殿下、お待ちください。わたくしは、そちらのエル様と一度もお話ししたことはありません」
アレクサンドラの記憶では、数カ月前に急にサティスから彼が担当している僅かな公務を押しつけられたので、事情を聞くために王宮内でサティスを探しているときに、庭園の片隅で逢瀬を楽しんでいるサティスとエルらしき人物をチラリと見かけただけだ。
「エルと話したことがないだと!? それこそ、お前がエルを無視し、虐げた証拠だ!」
「いえ、そうではなく。……そもそもどうして、男爵家のエル様が王宮内に?」
誰かが手引きでもしない限り、男爵令嬢では気軽に王宮に出入りできない。
「エルを侮辱する気か!? いいかげん嫉妬はやめろ!」
今までもそうだったが、アレクサンドラが丁寧に説明してもサティスに言葉は通じない。これまでの付き合いで言葉だけでは、サティスは理解できないと分かっていた。
「アレクサンドラ! お前がどれほど卑怯なことをしようが、私とエルを引き裂くことはできない。なぜなら私たちは、真実の愛で結ばれているからな!」
「真実の愛ですか……。まぁまぁ、それはそれは」
そう呟いたアレクサンドラは、小さく何度も頷きながら微笑んだ。
サティスが側近たちに命令するときも、『真実の愛』という言葉を熱弁していたので、すでにこちらに情報は入っていた。ちなみに、サティスの側近たちとアレクサンドラは、残念な主に仕える身として親しみを感じつつ、共に後始末をするうちに同胞のような強い絆で結ばれていたため、サティスの情報はこちらに筒抜けだ。