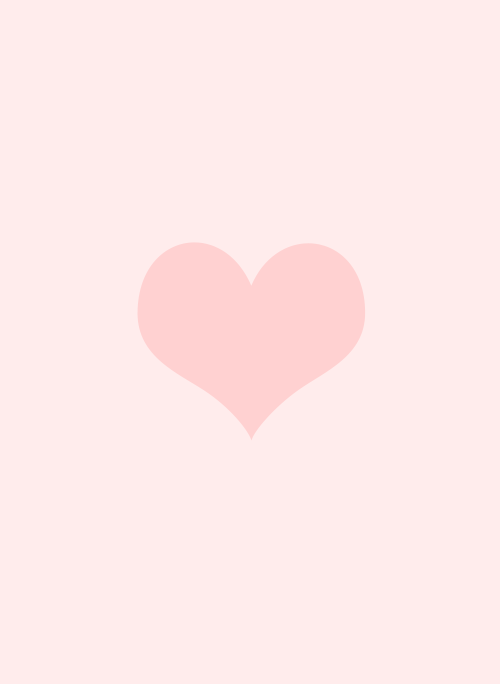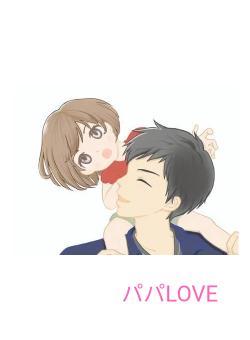松下は後ろに振り返り、肩を震わせながら目じりを押さえていた。
「先生…」
「すまない…仲村は本当にいい娘だった。誰にでも笑顔で接し、誰にでも優しかった。それに…こんな口が悪く、怒ると直ぐに手が出るような男勝りな私に、アイツは何の迷いも抵抗もなく飛び込んできた。挙げ句の果てに“先生大好き”とまで言いやがった。そんなアイツを誰よりも可愛くない訳がないだろう…うぅぅぅ…‥」
松下は、ポケットから取り出したハンカチを目にあてて、少しの間泣き続けていた。
「通夜と葬儀は、お前が入院している間に執り行われて、仲村は荼毘に付された」
松下は僕の方に向き直り、時々涙を拭いながら話をしていた。
「僕が悪いんです。僕のせいで…」
「ふざけた事を言ってんじゃねえよっ。お前のそんな言葉を聞く為に、仲村は命を投げ出した訳じゃねえんだよ」
「でも…」
「アイツはお前だったから助けたんだっ」
「僕だったから?僕と仲村さんの関係って何だったんですか?」
「お前は友達としか思ってなかったようだけど、仲村にとってお前は…特別な存在だったんだ」
松下は、さっきまでの荒々しい話し方とは打って変わって穏やかな口調に変わった。
「特別?」
「そうだ…。これを見れば、どういう事か直ぐにわかる」
すると松下から赤い表紙の日記らしき物を手渡された。
これってもしかして、仲村さんの日記…。
「どうして僕に?」
「お前には、この日記を読む義務がある?」
「僕に、これを読む資格なんてありません…」
「いいから読んでみろっ。“特別な存在”の意味がわかるはずだ」
「はっ‥はい…」
僕は緊張で震える手を必死に抑えながら、日記を開いて読み始めた。
【紺野くん…
あなたは気付いていないけど、私はいつもあなたを見ていたの。
中学の時からずっとだよ。
聞いたらビックリするかな?
それに私がS高に入学したのは、紺野くんと一緒の高校に入りたかったから。
S高は、私の学力では無理だと先生に反対されていたけど、紺野くんの傍にいたいから、死ぬほど勉強して合格したんだよ。
えらいでしょ!?
えらいって言って欲しいけど、この事は絶対に内緒。
だって、紺野くんと一緒にいたくて、こんなに頑張ってたって知られたら恥ずかしいもん。
だから、この事は私の胸の中に一生しまっておくの…】
「先生…」
「すまない…仲村は本当にいい娘だった。誰にでも笑顔で接し、誰にでも優しかった。それに…こんな口が悪く、怒ると直ぐに手が出るような男勝りな私に、アイツは何の迷いも抵抗もなく飛び込んできた。挙げ句の果てに“先生大好き”とまで言いやがった。そんなアイツを誰よりも可愛くない訳がないだろう…うぅぅぅ…‥」
松下は、ポケットから取り出したハンカチを目にあてて、少しの間泣き続けていた。
「通夜と葬儀は、お前が入院している間に執り行われて、仲村は荼毘に付された」
松下は僕の方に向き直り、時々涙を拭いながら話をしていた。
「僕が悪いんです。僕のせいで…」
「ふざけた事を言ってんじゃねえよっ。お前のそんな言葉を聞く為に、仲村は命を投げ出した訳じゃねえんだよ」
「でも…」
「アイツはお前だったから助けたんだっ」
「僕だったから?僕と仲村さんの関係って何だったんですか?」
「お前は友達としか思ってなかったようだけど、仲村にとってお前は…特別な存在だったんだ」
松下は、さっきまでの荒々しい話し方とは打って変わって穏やかな口調に変わった。
「特別?」
「そうだ…。これを見れば、どういう事か直ぐにわかる」
すると松下から赤い表紙の日記らしき物を手渡された。
これってもしかして、仲村さんの日記…。
「どうして僕に?」
「お前には、この日記を読む義務がある?」
「僕に、これを読む資格なんてありません…」
「いいから読んでみろっ。“特別な存在”の意味がわかるはずだ」
「はっ‥はい…」
僕は緊張で震える手を必死に抑えながら、日記を開いて読み始めた。
【紺野くん…
あなたは気付いていないけど、私はいつもあなたを見ていたの。
中学の時からずっとだよ。
聞いたらビックリするかな?
それに私がS高に入学したのは、紺野くんと一緒の高校に入りたかったから。
S高は、私の学力では無理だと先生に反対されていたけど、紺野くんの傍にいたいから、死ぬほど勉強して合格したんだよ。
えらいでしょ!?
えらいって言って欲しいけど、この事は絶対に内緒。
だって、紺野くんと一緒にいたくて、こんなに頑張ってたって知られたら恥ずかしいもん。
だから、この事は私の胸の中に一生しまっておくの…】