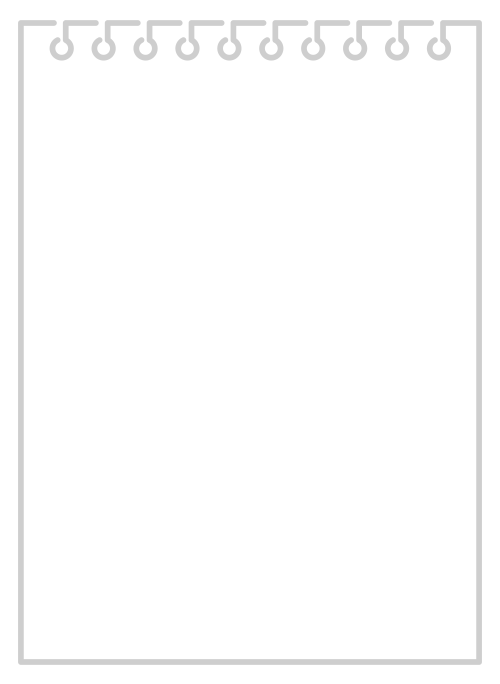文文堂には、この自転車も通れない狭くて湿っぽい路地を通らないと行けない。
なにが楽しくて祖父の代からこんなところに通い詰めないと行けないのか。
こんなにしかめ面で歩いていて顔の皺が増えでもしたら、間違いなくこの文文堂通いの習慣のせいだーーと、神矢潔(かみやいさぎ)は思う。
ガラスの嵌った引き戸を開け閉めする度に、この建物はそろそろ倒壊するのではないかと潔は案じていた。建物や文文堂の主、勘解由小路文藏(かでのこうじぶんぞう)の心配をしているのではなく、うっかり文藏と心中してしまいかねない自分の心配をしているのだ。
「おーい、文藏。いるのか」
文文堂は骨董屋と名乗ってはいるが、潔には物置小屋にしか見えない。潔以外が見たって、そう思うに違いない。その帳場の裏側から小柄な禿頭がぬっと姿を現し、「なんだ、潔か」とため息混じりに言うと、また引っ込んだ。
そしてがちゃがちゃと割れ物がぶつかり合うような音がして、帳場の台のうえにどかんと置かれたのは、茶色に濁った液体の入った瓶だ。中で蛇がとぐろを巻いている。
「ほら、持ってけ」
文藏はぶっきらぼうに言い、潔も「ああ」とこれを仏頂面で受け取った。見ているだけでも独特の異臭が鼻を責めてくるようだ。
潔はこの液体……蛇焼酎が大嫌いである。怪我をしたところに塗るとよく効くとか言われても、嫌いなものは嫌いだ。幼い頃から人一倍怪我が多く、しょっちゅう塗られていたからかも知れない。
潔にとっては要らないものでも、家族に頼まれているからには取りに来なければならない。祖父が亡くなる前から、蛇焼酎の受け取りは潔の役割だった。生前のよしみで、文藏は蛇焼酎をタダでくれる。要らないのに。