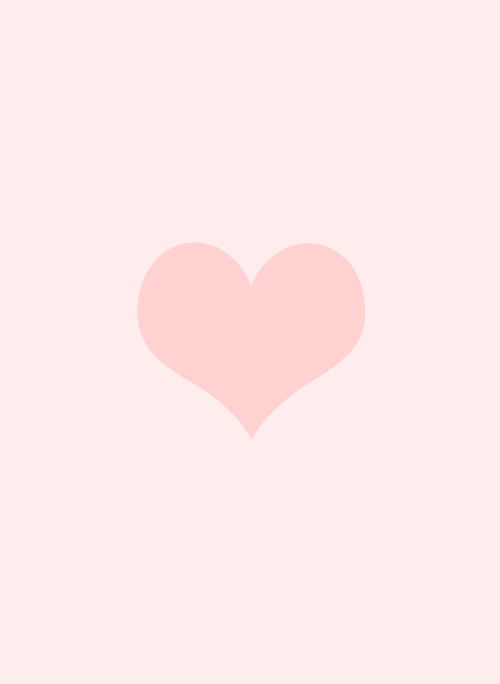「すみません、とても不愉快だったでしょう。
部屋に戻りますか?それとも何か飲み物を持ってきましょうか?」
冬真が心から心配しているのがわかる。
それが余計に朱音の涙を溢れさせた。
「・・・・・・嫌なら、突き飛ばして構いませんから」
真面目な声でそう言うと、冬真は朱音のすぐ横に座り朱音の肩を引き寄せ、ゆっくりと頭に手を伸ばし朱音の黒髪を撫でる。
朱音は驚き身を固くしたが、段々と何か押さえていたものが溢れ流れ出てきたのか、声を押し殺したように泣き出した朱音を冬真はただ優しく髪を撫でていた。
しばらくして落ち着いてきたのか顔を上げようとした朱音に冬真がハンカチを差し出すと、頷いてそれを受け取り顔に当てる。
「あと、で、洗って帰し、ます」
泣いてまだ呼吸が苦しいのか、途切れ途切れになりながらそんなことを言うと、
「あの」
身体を起こし座り直した朱音はそう声を出し、また俯いた。
「私の母が亡くなったことは、お話ししましたよね」
「えぇ、高校生の時ご病気でと」
「違うんです」
朱音は俯いたままで、冬真は何も答えずに疲れ切ったようにも見える朱音の横顔を見つめる。
「母がなくなった本当の理由は過労死です。
父が、その、私が中学の時リストラにあってなんとか転職したんですが給料が凄く減ったそうで、母はパートに出ました。
でもすぐに転職した会社も辞めてしまって、一時期は母のパート収入だけに頼ることもありました。
私は高校の進学も諦めようかと思いましたが、母が大学まで女の子でも行きなさいと。
自分が行きたくても行けず結局高卒だったのはその後とても苦労したからって言って後押しをしてくれ、私は公立の高校に進学しました。
父もまた再就職したとは言え給与はやはり厳しい額だったようで、私の高校はバイトが出来なかったので家事を私が担当して、母もパートを掛け持ちしている日々が続きそろそろ私が三年生になるときのことでした」
朱音は手に持っていたハンカチを強く握る。
「母が仕事先で倒れ、そのまま運ばれた病院で亡くなりました。
医師からは死因は心筋梗塞だが、あれだけの仕事をしていればその前に前兆があったはずだがと聞かれて、母は風邪気味だったとかそんな話しを私がしても父は一切口を開きませんでした。
無理も無いんです、ずっと私と母には顔もまともに会わさず会話もしていませんでしたから。
母の葬式でも周囲は母が必死に働いていたことを知っているので、何か言われるのが嫌だったのか最低限顔を出した後、父は家に籠もってしまいました。
母の死から父はおかしくなったと思います。
私に高校卒業までは待ってやるから卒業したらすぐに結婚しろと言ってきました。
お前の面倒なんて見たくない、と言っていましたが、母と声がよく似ている私とは一緒に居たくないのだとその頃は思っていました。
父が集めてきた見合いは、相手の顔も性格も二の次。
優先されるのは有名企業や収入でした。
そこで気が付いたんです、父は私に母と同じ苦労を味合わせたくは無いのかもしれない、と」