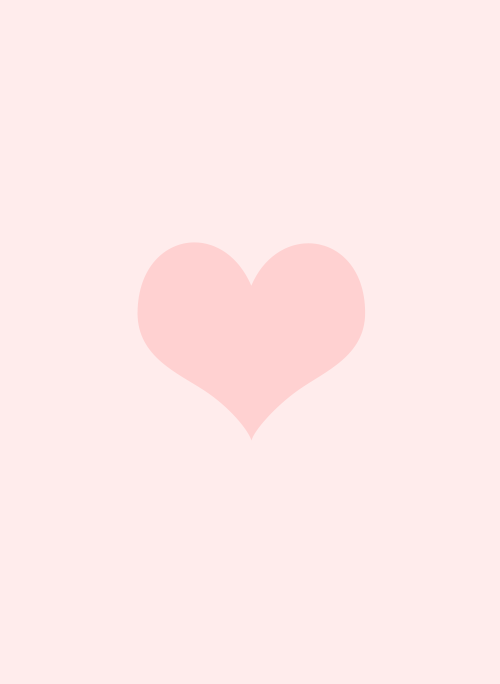「これ、ジェムなんですよね?お守りなんですよね?
ならトミーさんへのお守りにだってなるはずです」
「それはあなたのお守りです。彼のものでは無い」
「だったら大丈夫です」
冬真は朱音が確信したように言った意味がわからない。
再度柱に向き合い、一心に拳を、いやラブラドライトを叩きつけた。
その度に光の柱に朱音の血が流れ、時々ラブラドライトの破片なのか、キラキラしたものが空中に舞い散る。
冬真はただその小さな背中を見ていた。
彼女が何のためにそんな行為をしているのかわからない。
彼を助けようとしているのはわかる。
わかるが血が出るほど意味の無い行為をしていることが理解できなかった。
突然、ピシッとその壁にヒビが入り、冬真は目を見開く。
何も出来ないはずの柱にヒビが細く広がり朱音がそれに気が付かないまま再度叩きつけた瞬間まるでガラスが四散するかのように消え、するりと魔方陣の中に倒れ込んだ。
トミーを掴んでいた無数の手が新たな獲物がきたとばかりにトミーの横に倒れ込んだ朱音の手と足を掴みはじめ、手が身体を掴むたび身体に痛みが走る。
トミーは隣に倒れ込んだ朱音を見て我に返り、必死に朱音を起き上がらせようとするが足を無数の手に掴まれたまま動けない。
その様子が目の前で起きているのに冬真は動けずにいた。
何の知識も能力も無く空気を読んで踏み込んでくることをしなかった朱音が、自分に反抗してこんな行動を取ったことが信じられない。
この子はこんな子だったのだろうか。
「ぐぅっ」
激痛に朱音が思わず声を上げると冬真の横を黒いものが勢いよく横切り、朱音の身体を掴む無数の手に大きな口を開けて噛みついた。
朱音の目の前に現れた黒い大型犬はあのインカローズの時に助けてくれた犬。
その犬がまた現れた事に驚くと、今度は朱音の足を掴む手に青い石のついた小さなナイフが刺さり焼けるような音を立てて消えた。