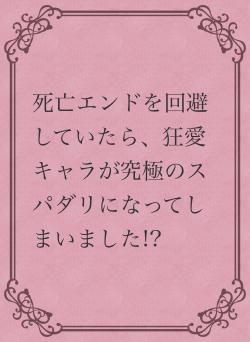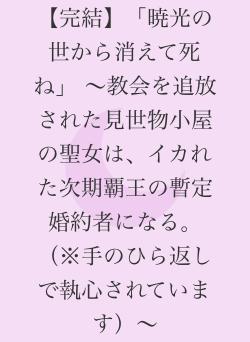その時、クリストファーの脳裏に浮かんだのはアリアの屈託ない笑顔だった。
「……っ」
「公爵様?」
目眩を伴う頭痛のあと、まるで黒いインクで塗り潰されるように、アリアの顔は頭から消えていく。
同時に記憶に蘇ってきたのは、涙で瞳を濡らした幼少期の無力な自分の姿である。
「どこかご気分でも……」
こめかみを強く押さえたクリストファーにジェイドが心配そうに尋ねる。
「なにもない。それより、さっさとこの書類を騎士団長へ渡してこい」
「あ、ちょっと、公爵様――」
そうしてジェイドの問いもうやむやにしたまま、クリストファーは執務室から彼を追い出した。
一人になったクリストファーは、静かに息をついて窓に目を向ける。
「…………」
アリア・グランツフィル。
5年前、実の姉が命を落としてまで産んだ、クリストファーにとっては姪にあたる子供。
二人が実の親子ではないと知っているのは、補佐役のジェイドと、公爵邸に古くから仕える執事長のみ。
ほかの者はアリアがクリストファーの子供だと思っているのだろう。
(…………気分が悪い)
産声をあげるアリアを目にしたとき、何よりも先に忌々しい感情が湧き上がった。
それから5年。
アリアを公爵邸の別館に住まわせてはいたが、それだけだった。
必要な手配はすべてジェイドに任せていたし、一度だって関わることはなかったというのに。