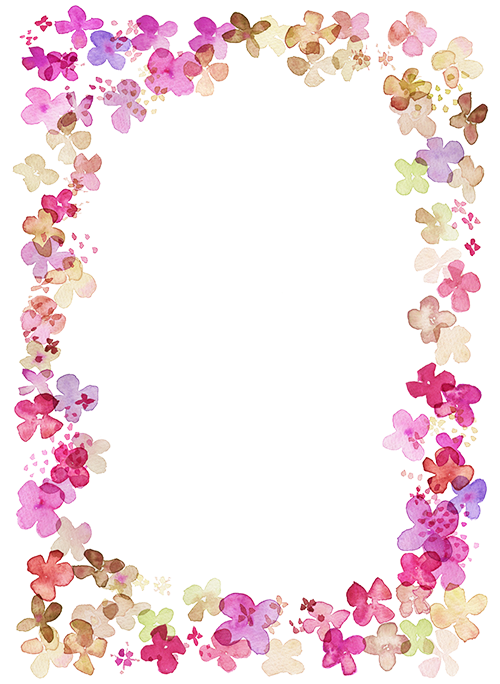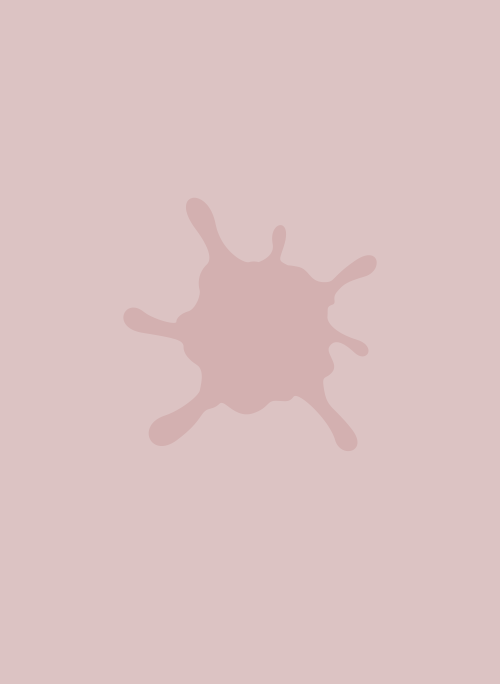「これ使って」
「ありがとう」
玄関で濡れた靴を脱ぐと、賢人が持ってきてくれた大判のバスタオルで髪を拭った。
そのとき、リビングの方から丸まると太った猫が私の足元までやってきてすりすりと顔を押しつけた。
「可愛い~!前写真見せてくれた子だよね?」
「そうそう」
「あはは、すごい人懐っこいね。よしよし、いいこだね」
顎の下をかいてあげると気持ちよさそうにゴロゴロと喉を鳴らしていたのに、しばらくすると飽きたのか再びリビングの方へ歩いて行ってしまった。
自由な猫にほっこりと温かい気持ちにしてもらったあと部屋に案内される。
賢人の部屋は二階の南側の6畳ほどの角部屋だった。
部屋を開けた瞬間、自分の部屋とは違う匂いがした。たまに賢人からする甘い匂いだ。
ドキドキしているのを悟られないようにキョロキョロと部屋の中を見渡す。
「すごい綺麗にしてるね。賢人ってA型でしょ?」
「O型。片付けめんどくさいから何にも置いてないだけ」
「なるほど。ちなみに私もOです」
「ははっ、そんな感じする。おおざっぱのOな」
「失礼な!」
クスクス笑う賢人をチラリと睨む。
それにしても白を基調とした壁紙とウッド調の床。部屋の中はいたってシンプルで余計な物がひとつもない。
その一角に所狭しとおかれているメダルやトロフィー。
「これってサッカーの?」
「ああ。幼稚園の時からだから置ききれなくて結構困ってる」
「すごいね。そんな前からサッカーやってるんだもんね」
「何度か辞めようと思ったんだけど、父親が5年前に亡くなってから母親に『アンタのサッカーの応援が私の生きがい』って言われてから辞めらんなくなった」
12歳の時にお父さんを病気で亡くし、今はお母さんと妹さんとの三人暮らしだと前に言っていた。
賢人は部屋のウォークインクローゼットを開けると、中からスポーツブランドのTシャツとズボンを取り出して私に差し出した。
「これ、着替え。このままじゃ風邪ひく」
「うん」
私が受け取ると、賢人は自分の着替えを持って部屋を出て行く。
着替えを済ませて少しすると、賢人が部屋に戻ってきた。
その格好を見て私はブッと吹き出した。
「あはははは。ペアルックだ!」
「あー、だな」
私が白で賢人が黒色のTシャツを着ているという以外私達が着ているものは色もデザインも全くだった。
それに気が付いた賢人もつられて笑う。
「なんか腹減らない?」
もう13時を回っているのに、お昼を食べていなかったことを思い出す。
私は賢人に促されて階段を降りてキッチンへ向かった。
「っていっても俺料理できないわ。愛依は?」
冷蔵庫の中を覗き込みながら尋ねる賢人。
「あ、はい。私もです」
こういう時、デキる女子なら冷蔵庫の中にあるもので適当に作るよとか簡単に言えちゃうんだろうけど私には無理。
普段はお母さんに任せっきりで包丁を握ったのは中学の時の調理実習が最後だ。
「だよな。なかなか料理なんて作らないし。あ、これ食べれる?」
冷凍庫の中にあったカルボナーラとたらこスパゲッティを引っ張り出す賢人はどっちがいいと私に差し出した。
「じゃあ、カルボナーラ」
「よし、決まりだ」
私達はああでもないこうでもないと言い合いながら一緒にスパゲティを作った。
といっても電子レンジ温めるだけど、苦戦して作ったスパゲティは頬が落ちそうなほど美味しかった。
「ありがとう」
玄関で濡れた靴を脱ぐと、賢人が持ってきてくれた大判のバスタオルで髪を拭った。
そのとき、リビングの方から丸まると太った猫が私の足元までやってきてすりすりと顔を押しつけた。
「可愛い~!前写真見せてくれた子だよね?」
「そうそう」
「あはは、すごい人懐っこいね。よしよし、いいこだね」
顎の下をかいてあげると気持ちよさそうにゴロゴロと喉を鳴らしていたのに、しばらくすると飽きたのか再びリビングの方へ歩いて行ってしまった。
自由な猫にほっこりと温かい気持ちにしてもらったあと部屋に案内される。
賢人の部屋は二階の南側の6畳ほどの角部屋だった。
部屋を開けた瞬間、自分の部屋とは違う匂いがした。たまに賢人からする甘い匂いだ。
ドキドキしているのを悟られないようにキョロキョロと部屋の中を見渡す。
「すごい綺麗にしてるね。賢人ってA型でしょ?」
「O型。片付けめんどくさいから何にも置いてないだけ」
「なるほど。ちなみに私もOです」
「ははっ、そんな感じする。おおざっぱのOな」
「失礼な!」
クスクス笑う賢人をチラリと睨む。
それにしても白を基調とした壁紙とウッド調の床。部屋の中はいたってシンプルで余計な物がひとつもない。
その一角に所狭しとおかれているメダルやトロフィー。
「これってサッカーの?」
「ああ。幼稚園の時からだから置ききれなくて結構困ってる」
「すごいね。そんな前からサッカーやってるんだもんね」
「何度か辞めようと思ったんだけど、父親が5年前に亡くなってから母親に『アンタのサッカーの応援が私の生きがい』って言われてから辞めらんなくなった」
12歳の時にお父さんを病気で亡くし、今はお母さんと妹さんとの三人暮らしだと前に言っていた。
賢人は部屋のウォークインクローゼットを開けると、中からスポーツブランドのTシャツとズボンを取り出して私に差し出した。
「これ、着替え。このままじゃ風邪ひく」
「うん」
私が受け取ると、賢人は自分の着替えを持って部屋を出て行く。
着替えを済ませて少しすると、賢人が部屋に戻ってきた。
その格好を見て私はブッと吹き出した。
「あはははは。ペアルックだ!」
「あー、だな」
私が白で賢人が黒色のTシャツを着ているという以外私達が着ているものは色もデザインも全くだった。
それに気が付いた賢人もつられて笑う。
「なんか腹減らない?」
もう13時を回っているのに、お昼を食べていなかったことを思い出す。
私は賢人に促されて階段を降りてキッチンへ向かった。
「っていっても俺料理できないわ。愛依は?」
冷蔵庫の中を覗き込みながら尋ねる賢人。
「あ、はい。私もです」
こういう時、デキる女子なら冷蔵庫の中にあるもので適当に作るよとか簡単に言えちゃうんだろうけど私には無理。
普段はお母さんに任せっきりで包丁を握ったのは中学の時の調理実習が最後だ。
「だよな。なかなか料理なんて作らないし。あ、これ食べれる?」
冷凍庫の中にあったカルボナーラとたらこスパゲッティを引っ張り出す賢人はどっちがいいと私に差し出した。
「じゃあ、カルボナーラ」
「よし、決まりだ」
私達はああでもないこうでもないと言い合いながら一緒にスパゲティを作った。
といっても電子レンジ温めるだけど、苦戦して作ったスパゲティは頬が落ちそうなほど美味しかった。