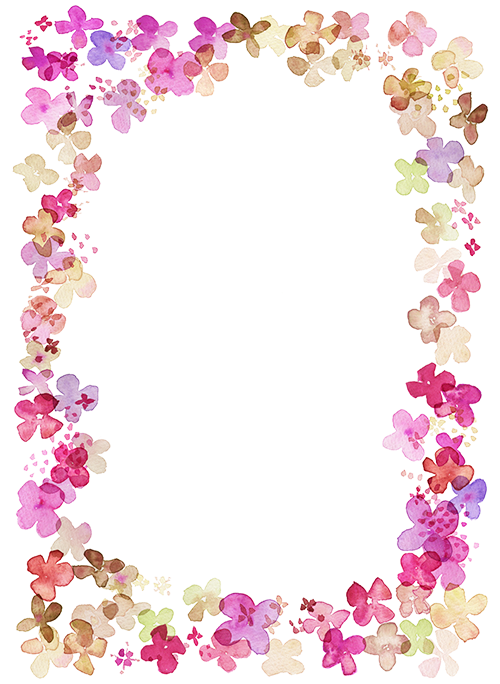九条賢人side
修学旅行から帰ってきた後、俺はこれまで以上に部活漬けの毎日を送っていた。
それでも頑張れたのは春野との花火大会の予定があるからだ。
約束の日まで残り2週間。俺はその日に春野へ自分の想いを伝える決心を固めていた。
部活の休憩時間になり日陰に座り込みスポーツドリンクを飲んでいると、俺の隣にチームメイトの岸がドカッと腰かけた。
「マジ疲れた~。帰りてー」
おでこの汗をタオルで拭っている岸の元へマネージャーの白石が歩み寄り無言でボトルを差し出した。
「……どーも」
二人とも互いに目を合わさず素っ気ない態度だ。
不思議に思っていると白石が俺に微笑みかけた。
「九条君、タオル忘れたでしょ?」
「ありがとう」
白石は背中を向けて俺達から離れていく。
チラリと岸に視線を向けると、受け取ったボトルを複雑そうな表情でジッと眺めていた。
「お前らなんかあったの?」
二人は中学の時から付き合っていて、岸のサポートをするために白石は同じ高校に入りマネージャーになったと噂で聞いた。
「ちょっと前に別れた」
「は?なんで?お前らすげぇラブラブだったじゃん」
驚いて聞き返すと、岸は困ったように笑った。
「そうでもないんだって。実は俺達って中学んときから別れたり付き合ったり繰り返してんの。別にお互い嫌いになったとかじゃないんだけど、やっぱもう無理だなって」
「嫌いになったんじゃないならやり直せるだろ」
「できねぇーよ。やり直してもずっと同じことの繰り返しだからさ」
「お前はもう白石のこと好きじゃないのか?」
「好きだよ。長く付き合ってたから情もあるし。でも、好きだけじゃ続けらんねぇこともあるんだって」
岸はポンッと俺の肩を叩いた。
「俺はしばらく恋とかそういうのはいいかな。……お前は頑張れよ」
「なにが?」
「お前のことずっと見てる」
すると、岸が顎でくいっと何かを指した。
「春野……?」
グラウンドのそばに立っていた春野がこちらを見ていた。
春野は俺と目が合うと、遠慮がちに手を振ってそのまま校門の方まで歩いていく。
「早くいってやれよ。さっきからお前のこと見てたよ」
背中を押されて俺は慌てて立ち上がると春野の元へ駆け出した。