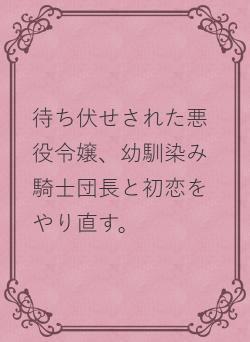あんなとんでもなくみっともない出来事が、他でもないこの身に起こったと思えば。どうしても真っ黒で鬱々とした気持ちに満たされたりは、する。
ベッドの上で温かなで柔らかな毛布に包まれ猫のように丸くなり思い出すのは、いくつかの良かったはずの思い出と、それを上から真っ黒にして塗り潰すようなひどい真実。
止めようもない涙がどれだけだらだらと身体の中から流れていっても、それはどうしても心の中から消せなかった。
何日も何日も。今がいつだったかも、わからなくなるほどに。
ライバルへの嫌がらせに一年を使うという意味のわからない最低な元彼のお陰で、ただのだしに使われた私は衝撃を受け流せずに自室に篭もり切りになった。
気が利く従姉妹のラウィーニアが何かしら良いように言ってくれたんだとは思うけれど、末子の私に甘い父母も何かと口うるさい心配性の兄も部屋には顔を見せない。
もうそれで、良かった。
きっと、皆これを聞いてしまえば心配はしてくれているだろう。城で文官を務める頭脳派の兄は、まともに剣を扱ったことも無いのに、この顛末を知れば、クレメントに決闘を挑みに行くかもしれない。
彼にあっさりと、瞬殺されてしまいそうだけれど。
私は大きな傷を負って、外敵から身を隠し巣の中でじっと身を潜める野生の動物のように。何もかもを、遮断していたかった。
何か優しくいたわるようなことを言われれば、その人が悪くないと頭ではわかっているのに。あなたに何がわかるのと、八つ当たりをして傷つけてしまいそうで。
誰にも会いたくなかった。誰にも。
ベッドの上で温かなで柔らかな毛布に包まれ猫のように丸くなり思い出すのは、いくつかの良かったはずの思い出と、それを上から真っ黒にして塗り潰すようなひどい真実。
止めようもない涙がどれだけだらだらと身体の中から流れていっても、それはどうしても心の中から消せなかった。
何日も何日も。今がいつだったかも、わからなくなるほどに。
ライバルへの嫌がらせに一年を使うという意味のわからない最低な元彼のお陰で、ただのだしに使われた私は衝撃を受け流せずに自室に篭もり切りになった。
気が利く従姉妹のラウィーニアが何かしら良いように言ってくれたんだとは思うけれど、末子の私に甘い父母も何かと口うるさい心配性の兄も部屋には顔を見せない。
もうそれで、良かった。
きっと、皆これを聞いてしまえば心配はしてくれているだろう。城で文官を務める頭脳派の兄は、まともに剣を扱ったことも無いのに、この顛末を知れば、クレメントに決闘を挑みに行くかもしれない。
彼にあっさりと、瞬殺されてしまいそうだけれど。
私は大きな傷を負って、外敵から身を隠し巣の中でじっと身を潜める野生の動物のように。何もかもを、遮断していたかった。
何か優しくいたわるようなことを言われれば、その人が悪くないと頭ではわかっているのに。あなたに何がわかるのと、八つ当たりをして傷つけてしまいそうで。
誰にも会いたくなかった。誰にも。