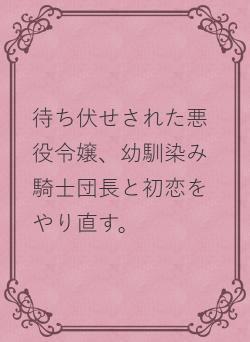「ねえ。ディアーヌ。この水色のドレス、良いんじゃない? ランスロット・グラディスの、あの氷のような水色の目に良く似ているわ。きっと彼の隣に居れば、引き立つわよ」
早速ラウィーニアは週末の夜会に向けて準備をしようと意気込んで立ち上がり、気の向かない私を早く早くと急かして勝手知ったる衣裳部屋を漁り始めた。
ラウィーニアが機嫌良く示した水色のドレスを見て、浮かない顔のままで首を横に振った。
「それは、前にクレメントが一緒に出席する夜会用に贈ってくれたものなの。もう着れないわ。そうだった……あの人に貰った物は、全部整理してから捨てなきゃ」
元彼から贈られた物を身に付けて、未婚者にとっては出会いを求める意味合いもある夜会になんか絶対出たくない。
とは言っても、クレメントは決して付き合っていた私へはケチることはなく、高価で豪華な贈り物は沢山貰ってはいる。今は物に溢れている衣装部屋は、近い内にかなりの数を処分してからスッキリとすることになりそう。
「何言ってるの。元彼に貰ったからって、物には罪はないわよ。このドレスだって凄く良い生地だし、形も可愛くてディアーヌに似合っているわ。他の男性とは……ランスロットに会う時には、違うドレスを着れば良いんだし。別に気にせずに自分が気に入った物は、捨てずに置いておけば? 向こうも付き合っていた恋人に貢いでいた物を返せとは、言わないでしょ。もし、そう言って来たとしたら我が国に仕える騎士の風上にも置けないから、投獄してやるわ」
ラウィーニアは、先ほど口にした物騒な言葉に似合わないにっこりとした良い笑顔を見せた。
早速ラウィーニアは週末の夜会に向けて準備をしようと意気込んで立ち上がり、気の向かない私を早く早くと急かして勝手知ったる衣裳部屋を漁り始めた。
ラウィーニアが機嫌良く示した水色のドレスを見て、浮かない顔のままで首を横に振った。
「それは、前にクレメントが一緒に出席する夜会用に贈ってくれたものなの。もう着れないわ。そうだった……あの人に貰った物は、全部整理してから捨てなきゃ」
元彼から贈られた物を身に付けて、未婚者にとっては出会いを求める意味合いもある夜会になんか絶対出たくない。
とは言っても、クレメントは決して付き合っていた私へはケチることはなく、高価で豪華な贈り物は沢山貰ってはいる。今は物に溢れている衣装部屋は、近い内にかなりの数を処分してからスッキリとすることになりそう。
「何言ってるの。元彼に貰ったからって、物には罪はないわよ。このドレスだって凄く良い生地だし、形も可愛くてディアーヌに似合っているわ。他の男性とは……ランスロットに会う時には、違うドレスを着れば良いんだし。別に気にせずに自分が気に入った物は、捨てずに置いておけば? 向こうも付き合っていた恋人に貢いでいた物を返せとは、言わないでしょ。もし、そう言って来たとしたら我が国に仕える騎士の風上にも置けないから、投獄してやるわ」
ラウィーニアは、先ほど口にした物騒な言葉に似合わないにっこりとした良い笑顔を見せた。