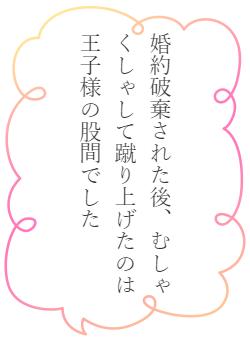「もう……」
毎度のことなので慣れてしまったレティシアは、そんな侍女を咎めることなく後ろ姿を見送った。そして足音が完全に消えたタイミングを見計らい、小さく咳払いをしたレティシアは、すすっと壁際の鏡の前に移動する。
のぞき込めば、中からは赤い髪に湖水のような青い瞳をした、少し勝ち気そうな少女がこちらを見ていた。もう、これまでに何度も見たなじみ深い——自分の顔だ。
つり目がちの瞳、少し低めの鼻——形の良い唇だけは気に入っているが、それ以外はもう少しどうにかならなかったのかと嘆きたくなる、そんな顔だ。
——特に、この目……。
鏡に映る自分に手を伸ばし、その目元にそっと触れる。薄い水色をしたこの瞳は、父と同じ色だ。冷徹な宰相と呼ばれる、父と。
——本当、お父様とそっくり……目つきまで。
このつり目のせいで、レティシアはよく「怒っている」だの「機嫌が悪い」などと誤解され、周囲に人が寄ってこない。十八歳の侯爵令嬢という立場でありながら、求婚者の一人もいないのは、おそらくこれが原因だろう、と自分では思っている。
——どうせなら、お母様に似たかったわ……。
社交界の花と呼ばれた母は、優しげな容姿の美しい女性だ。年齢を重ねた今も、その容色は衰えを見せていない。一部では、未だにファンクラブが存在しているとかいないとか。
その母に似た兄がうらやましい。
だが、今更嘆いたところでどうにもなるものか。
はあ、ともう一度ため息をつくと、レティシアは軽く赤い髪を手ぐしでとかし、もう一度鏡をのぞき込んでから部屋を後にした。
毎度のことなので慣れてしまったレティシアは、そんな侍女を咎めることなく後ろ姿を見送った。そして足音が完全に消えたタイミングを見計らい、小さく咳払いをしたレティシアは、すすっと壁際の鏡の前に移動する。
のぞき込めば、中からは赤い髪に湖水のような青い瞳をした、少し勝ち気そうな少女がこちらを見ていた。もう、これまでに何度も見たなじみ深い——自分の顔だ。
つり目がちの瞳、少し低めの鼻——形の良い唇だけは気に入っているが、それ以外はもう少しどうにかならなかったのかと嘆きたくなる、そんな顔だ。
——特に、この目……。
鏡に映る自分に手を伸ばし、その目元にそっと触れる。薄い水色をしたこの瞳は、父と同じ色だ。冷徹な宰相と呼ばれる、父と。
——本当、お父様とそっくり……目つきまで。
このつり目のせいで、レティシアはよく「怒っている」だの「機嫌が悪い」などと誤解され、周囲に人が寄ってこない。十八歳の侯爵令嬢という立場でありながら、求婚者の一人もいないのは、おそらくこれが原因だろう、と自分では思っている。
——どうせなら、お母様に似たかったわ……。
社交界の花と呼ばれた母は、優しげな容姿の美しい女性だ。年齢を重ねた今も、その容色は衰えを見せていない。一部では、未だにファンクラブが存在しているとかいないとか。
その母に似た兄がうらやましい。
だが、今更嘆いたところでどうにもなるものか。
はあ、ともう一度ため息をつくと、レティシアは軽く赤い髪を手ぐしでとかし、もう一度鏡をのぞき込んでから部屋を後にした。