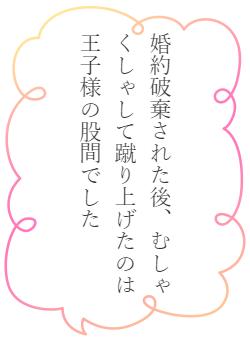まるで自分一人だけが取り残されているようで、彼のことになると全く素直になれない。そんな自分本位な自分のことも本当は嫌だった。
だけれど——そんな自分のことを、彼は愛していると言ってくれる。
「レティ、かわいい僕のレティ……」
そっと頬を撫でる手に拭われて、いつの間にか自分が泣いていることに気付く。唇が再び近づいて、今度はその涙を吸われた。
くすぐったさに身をよじるが、彼の力強い腕は離してくれない。
「僕と、結婚してくれるね」
「ええ……」
「や、やった……! レティ……!」
だめ押しのような一言に、レティシアはとうとう陥落した。
頷くと同時に、エルヴェが歓声をあげてぎゅっと抱きしめてくる。この腕の中では、もう素直になって良いのだ。胸板にぎゅっと顔を押しつけられながら、レティシアは陶然として目を閉じた。
だけれど——そんな自分のことを、彼は愛していると言ってくれる。
「レティ、かわいい僕のレティ……」
そっと頬を撫でる手に拭われて、いつの間にか自分が泣いていることに気付く。唇が再び近づいて、今度はその涙を吸われた。
くすぐったさに身をよじるが、彼の力強い腕は離してくれない。
「僕と、結婚してくれるね」
「ええ……」
「や、やった……! レティ……!」
だめ押しのような一言に、レティシアはとうとう陥落した。
頷くと同時に、エルヴェが歓声をあげてぎゅっと抱きしめてくる。この腕の中では、もう素直になって良いのだ。胸板にぎゅっと顔を押しつけられながら、レティシアは陶然として目を閉じた。