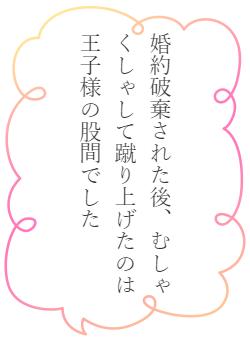「お嬢様、エルヴェ・グランジュ卿がお見えです」
「エルヴェが?」
侍女の口から出た年上の幼馴染の名に、レティシアは小さく首をかしげた。今日、彼がオービニエ家を——しかもレティシアの元を訪れる、という約束は特にしていなかったはずだ。
家族ぐるみの付き合いだというのに、毎度律儀に連絡をよこすエルヴェにしては珍しいことである。
不思議に思ったが、とにかく来ているというのならあまり待たせるわけにもいかない。読みかけの本をさっと閉じて机の上に置くと、レティシアは立ち上がりながら指示を出した。
「わかった、今行くわ。エルヴェは……そうね、庭のテラス席にでも案内しておいて。お茶はいつもの……そう、青い缶の。新しいのがあったわよね? それと……」
ちらりと時計を確認すると、もう午後二時を過ぎている。レティシアは少し考えると、続けて軽食を用意するよう侍女に命じた。
「まったくあの男、良い時間を選んできたものね」
ふん、と鼻を鳴らしてそう付け加えると、侍女が肩を震わせる。その様子に、レティシアは鼻の頭にしわを寄せた。
「何笑っているの!」
「も、申し訳ございません……!」
口調こそ慇懃なものの、侍女の口元の笑みは完全には消えていない。だが、レティシアが口調を荒げるよりも前に、侍女は慣れた様子で「では」と一礼するとそそくさとその場を後にした。
「エルヴェが?」
侍女の口から出た年上の幼馴染の名に、レティシアは小さく首をかしげた。今日、彼がオービニエ家を——しかもレティシアの元を訪れる、という約束は特にしていなかったはずだ。
家族ぐるみの付き合いだというのに、毎度律儀に連絡をよこすエルヴェにしては珍しいことである。
不思議に思ったが、とにかく来ているというのならあまり待たせるわけにもいかない。読みかけの本をさっと閉じて机の上に置くと、レティシアは立ち上がりながら指示を出した。
「わかった、今行くわ。エルヴェは……そうね、庭のテラス席にでも案内しておいて。お茶はいつもの……そう、青い缶の。新しいのがあったわよね? それと……」
ちらりと時計を確認すると、もう午後二時を過ぎている。レティシアは少し考えると、続けて軽食を用意するよう侍女に命じた。
「まったくあの男、良い時間を選んできたものね」
ふん、と鼻を鳴らしてそう付け加えると、侍女が肩を震わせる。その様子に、レティシアは鼻の頭にしわを寄せた。
「何笑っているの!」
「も、申し訳ございません……!」
口調こそ慇懃なものの、侍女の口元の笑みは完全には消えていない。だが、レティシアが口調を荒げるよりも前に、侍女は慣れた様子で「では」と一礼するとそそくさとその場を後にした。