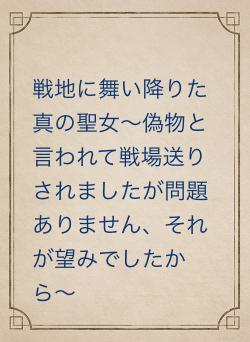「エリスはご両親の行方に当てはあるのかい?」
ガルニエが無事に駐屯地から人を呼び、外れた車輪の応急処置が済んだおかげで、私たちは今、荷物と一緒に幌馬車の中で揺られていた。
馬車に乗るのは村から王都に行く時が初めてで、追放された時、そして今回が三回目になる。
どれも思ったのは、揺れが激しく気持ちが悪くなるし、おしりも痛くて、あまり快適ではないということだった。
一応ワタの入った布が敷かれているけれど、大した効果があるとは言い難い。
そんな中で私はアベルと話をしていた。
初めは丁寧な言葉遣いだったアベルだけれど、私が要らないと言った途端気さくな話し方に変えてくれた。
「それが……何も無いのです。おそらく隣国へ向かった、ということくらいしか。もしかしたらもう既に……」
「大丈夫! こう見えても俺のハーミット商会は顔が広いんだ。きっと見つかるよ!」
アベルの話では自分の父親が会主をしているハーミット商会は、隣国のマルメリアではそこそこ大きい商会らしい。
正直なところ、村に来るのは個人の行商人くらいだった私にとって、商会というものがどういうものなのかいまいち理解できていなかった。
『どーすんのさ。エリス。居もしない両親を探させるなんて』
『うーん。困ったなぁ。街に着いたら、死んだことが分かったことにしようかな。じゃないと、ずっと探してくれそう……』
そんなことを考えながらアベルと話を続けた。
大体は私が聞き役だったけれど、色々と旅をしていて私より少し上なだけなのに経験が豊富なアベルの話は、面白くそして興味深いものばかりだった。
もう一つの理由は話が上手い、ということによるものだろう。
私が始めに思った通りの商人のアベルは、人の興味を引き出す話術に長けていた。
その話に、私もすっかり興味を惹かれてばかりいる。
『そんなこと言ってさぁ。アベルが格好いいからじゃないの? 本当は』
『もう! 茶化さないでよ! って言っても、格好いいのは否定しないけど……』
向かい合わせに座るアベルの顔をしっかりと見つめる。
顔立ちが端正なのもあるけれど、話す度にころころと表情を変えるのが見ていて飽きない。
「そうだ! エリスは薬師と言ったね? うちの商会でも色々と薬を扱っているんだけれど、なかなか品薄が続いていてさ。良い薬が作れるなら、是非ともうちと契約して欲しいんだけど」
「え? 契約? えーっと、それは……その……」
突然のアベルの発言に私はしどろもどろになってしまう。
なぜなら薬なんて、今まで村の人たちが自前で作っていた痛み止めや化膿止めの薬などしか知らないからだ。
私を見つめるアベルの顔付きは、先ほどの柔和なままだけれど、何やら真剣さを感じる。
きっと商売が絡むと出てくる顔なのだろう。
『ほら。嘘っていうのは吐くとどんどん自分を困らせるんだよ』
『そんなこと言ってもー。エア。さっき言ってた錬金術で薬って作れるの?』
『もちろん。多分下手な薬なんかよりずっと凄い物が作れるよ。何? エリス。まさか本当に錬金術師になるの?』
『もちろん隠すけどさ。でもやっぱり職は探さないと。商会と契約って、よく分からないけど凄いことなんでしょ?』
よし。決めた。
私はまだよくわからないけれど、その錬金術というのを使って、薬師として生きていこう。
「逆にどんな薬が必要ですか? 薬と言っても沢山あるので」
「ああ。そう言われてみればそうだね。まぁ一番需要が高いのは傷や怪我、それに病気を治す薬だね」
「分かりました。それじゃあ、いくつか当てがあるので、街に着いて落ち着いたら作ってみます。それを見てもらっていいですか?」
「それは良かった。ガルニエが、ずっと困ってた腰痛が無くなって調子がいいと言っていたよ。エリスの作る薬はすごい効能があるのかもしれないね」
こうして、私は隣国で薬師として暮らすことを決めた。
しかし、そう思っていたのは私だけで、作った薬のあまりの効果に、錬金術師だと直ぐにバレてしまうことになるのだけれど。
☆☆☆
~その頃王都では~
「ちょっと! サラマンダー!? 何処へ行ったというの!?」
ローザは最近見かけなくなってしまった、自分のパルであるサラマンダーを探して、城中を歩き回っていた。
見なくなったのは、ちょうど目障りな自分よりも数倍も強い光を放ったエリスを追い出し、悦に入っていた頃だ。
サラマンダーは気まぐれな性格で、今までにも時おり姿をくらますことがあった。
そのためローザは、今回もそのうち戻ってくるだろうと高を括っていた。
ところが――。
「もう! どこ行ったって言うのよ! あの子が居なきゃろくな力が出せないのに!!」
「きゃっ!?」
苛立ちながら目に付いた侍女に八つ当たりをする。
元々平民出のローザだったが、貴族の末娘であるこの侍女よりも、今は立場は大きく上だ。
王族に従える聖女、その立場は生来の清らかだった心を大きく蝕んでしまった。
素朴で誰にでも笑顔を振り撒いていた活発な少女はナリを潜め、代わりに表面を覆ったのは苛烈なまでの自尊心だった。
「とにかく! 早くサラマンダーを見つけないと! 今度は私が追放でもされたら洒落にならないわ」
長年連れ添ったパルを再び探すローザだったが、既に手遅れになっていたことを知るのはもう少し先の話だ。
原因はエリスに、いや、エリスのパルであるエアから話を聞いたサラマンダーにした仕打ちである。
人間界でもそうだが、精霊界ではそれとは比にならない程の明確な序列が存在した。
四大元素の一つである火の大精霊サラマンダーは、全ての火の精霊の上に立つ長である。
そんなサラマンダーがへりくだる存在。
その存在を、聞かれたわけでもなくわざわざサラマンダーから伝えたのにも関わらず、ローザはそれを無視した。
無視したどころか、その想い人であるエリスを辱めに合わせたのだ。
聖女という待遇に落ちぶれていくローザに、サラマンダーが愛想を尽かすのには十分過ぎるほどの出来事だった。
精霊力というのは人が持つ器の大きさによって行使できる量が決まるが、器だけでは用をなさない。
サラマンダーに愛想を尽かされたローザが今後、火の属性の精霊力を使うことは出来ないだろう。
そして、それは相性が元々良くない別の精霊においても同じことが言えた。
ローザはあの日、精霊から見れば実にくだらない理由によってもたらした自らの行いによって、聖女としての力を、永遠に放棄したのだった。
ガルニエが無事に駐屯地から人を呼び、外れた車輪の応急処置が済んだおかげで、私たちは今、荷物と一緒に幌馬車の中で揺られていた。
馬車に乗るのは村から王都に行く時が初めてで、追放された時、そして今回が三回目になる。
どれも思ったのは、揺れが激しく気持ちが悪くなるし、おしりも痛くて、あまり快適ではないということだった。
一応ワタの入った布が敷かれているけれど、大した効果があるとは言い難い。
そんな中で私はアベルと話をしていた。
初めは丁寧な言葉遣いだったアベルだけれど、私が要らないと言った途端気さくな話し方に変えてくれた。
「それが……何も無いのです。おそらく隣国へ向かった、ということくらいしか。もしかしたらもう既に……」
「大丈夫! こう見えても俺のハーミット商会は顔が広いんだ。きっと見つかるよ!」
アベルの話では自分の父親が会主をしているハーミット商会は、隣国のマルメリアではそこそこ大きい商会らしい。
正直なところ、村に来るのは個人の行商人くらいだった私にとって、商会というものがどういうものなのかいまいち理解できていなかった。
『どーすんのさ。エリス。居もしない両親を探させるなんて』
『うーん。困ったなぁ。街に着いたら、死んだことが分かったことにしようかな。じゃないと、ずっと探してくれそう……』
そんなことを考えながらアベルと話を続けた。
大体は私が聞き役だったけれど、色々と旅をしていて私より少し上なだけなのに経験が豊富なアベルの話は、面白くそして興味深いものばかりだった。
もう一つの理由は話が上手い、ということによるものだろう。
私が始めに思った通りの商人のアベルは、人の興味を引き出す話術に長けていた。
その話に、私もすっかり興味を惹かれてばかりいる。
『そんなこと言ってさぁ。アベルが格好いいからじゃないの? 本当は』
『もう! 茶化さないでよ! って言っても、格好いいのは否定しないけど……』
向かい合わせに座るアベルの顔をしっかりと見つめる。
顔立ちが端正なのもあるけれど、話す度にころころと表情を変えるのが見ていて飽きない。
「そうだ! エリスは薬師と言ったね? うちの商会でも色々と薬を扱っているんだけれど、なかなか品薄が続いていてさ。良い薬が作れるなら、是非ともうちと契約して欲しいんだけど」
「え? 契約? えーっと、それは……その……」
突然のアベルの発言に私はしどろもどろになってしまう。
なぜなら薬なんて、今まで村の人たちが自前で作っていた痛み止めや化膿止めの薬などしか知らないからだ。
私を見つめるアベルの顔付きは、先ほどの柔和なままだけれど、何やら真剣さを感じる。
きっと商売が絡むと出てくる顔なのだろう。
『ほら。嘘っていうのは吐くとどんどん自分を困らせるんだよ』
『そんなこと言ってもー。エア。さっき言ってた錬金術で薬って作れるの?』
『もちろん。多分下手な薬なんかよりずっと凄い物が作れるよ。何? エリス。まさか本当に錬金術師になるの?』
『もちろん隠すけどさ。でもやっぱり職は探さないと。商会と契約って、よく分からないけど凄いことなんでしょ?』
よし。決めた。
私はまだよくわからないけれど、その錬金術というのを使って、薬師として生きていこう。
「逆にどんな薬が必要ですか? 薬と言っても沢山あるので」
「ああ。そう言われてみればそうだね。まぁ一番需要が高いのは傷や怪我、それに病気を治す薬だね」
「分かりました。それじゃあ、いくつか当てがあるので、街に着いて落ち着いたら作ってみます。それを見てもらっていいですか?」
「それは良かった。ガルニエが、ずっと困ってた腰痛が無くなって調子がいいと言っていたよ。エリスの作る薬はすごい効能があるのかもしれないね」
こうして、私は隣国で薬師として暮らすことを決めた。
しかし、そう思っていたのは私だけで、作った薬のあまりの効果に、錬金術師だと直ぐにバレてしまうことになるのだけれど。
☆☆☆
~その頃王都では~
「ちょっと! サラマンダー!? 何処へ行ったというの!?」
ローザは最近見かけなくなってしまった、自分のパルであるサラマンダーを探して、城中を歩き回っていた。
見なくなったのは、ちょうど目障りな自分よりも数倍も強い光を放ったエリスを追い出し、悦に入っていた頃だ。
サラマンダーは気まぐれな性格で、今までにも時おり姿をくらますことがあった。
そのためローザは、今回もそのうち戻ってくるだろうと高を括っていた。
ところが――。
「もう! どこ行ったって言うのよ! あの子が居なきゃろくな力が出せないのに!!」
「きゃっ!?」
苛立ちながら目に付いた侍女に八つ当たりをする。
元々平民出のローザだったが、貴族の末娘であるこの侍女よりも、今は立場は大きく上だ。
王族に従える聖女、その立場は生来の清らかだった心を大きく蝕んでしまった。
素朴で誰にでも笑顔を振り撒いていた活発な少女はナリを潜め、代わりに表面を覆ったのは苛烈なまでの自尊心だった。
「とにかく! 早くサラマンダーを見つけないと! 今度は私が追放でもされたら洒落にならないわ」
長年連れ添ったパルを再び探すローザだったが、既に手遅れになっていたことを知るのはもう少し先の話だ。
原因はエリスに、いや、エリスのパルであるエアから話を聞いたサラマンダーにした仕打ちである。
人間界でもそうだが、精霊界ではそれとは比にならない程の明確な序列が存在した。
四大元素の一つである火の大精霊サラマンダーは、全ての火の精霊の上に立つ長である。
そんなサラマンダーがへりくだる存在。
その存在を、聞かれたわけでもなくわざわざサラマンダーから伝えたのにも関わらず、ローザはそれを無視した。
無視したどころか、その想い人であるエリスを辱めに合わせたのだ。
聖女という待遇に落ちぶれていくローザに、サラマンダーが愛想を尽かすのには十分過ぎるほどの出来事だった。
精霊力というのは人が持つ器の大きさによって行使できる量が決まるが、器だけでは用をなさない。
サラマンダーに愛想を尽かされたローザが今後、火の属性の精霊力を使うことは出来ないだろう。
そして、それは相性が元々良くない別の精霊においても同じことが言えた。
ローザはあの日、精霊から見れば実にくだらない理由によってもたらした自らの行いによって、聖女としての力を、永遠に放棄したのだった。