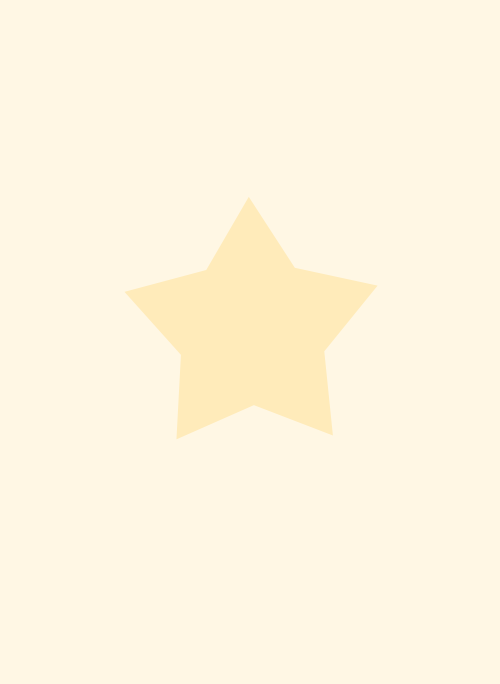「……カエティス君は本当にカーテリーズそっくりだよ。自分でどうにかしようと考える。私が反対しても勝手に動く。まぁ、そこが彼女に惚れた一つなんだけどね」
説得を諦めたようにベルナートは溜め息を吐いた。
「君の気持ちは分かったよ。カエティス君のしたいようにしなさい。但し、無茶をしないこと。いいね?」
「はい、分かりました。それにしても、司祭様も王様も無茶するなって、俺、そんなに無茶してるように見えますか?」
「カエティス君、お父さんと呼びなさい。お父さんと。君は本当にカーテリーズそっくりで、無茶しているのに無茶してないって言い張るんだよ」
困ったように笑い、ベルナートはカエティスの頭を小さな子供にするように撫でる。
「だから、こちらは冷や汗ばかりだよ。五歳の時は二泊三日でちょっと出掛けたカーテリーズの帰りを寝ずに待つし、追い掛けようとするし」
「…………」
懐かしそうに思い出すベルナートの言葉を聞き、カエティスはばつが悪そうに目を逸らす。
「あの、俺、聖堂の中庭で結界張って来ます」
居たたまれなくなったカエティスは、話を変えるように扉の取っ手を掴む。