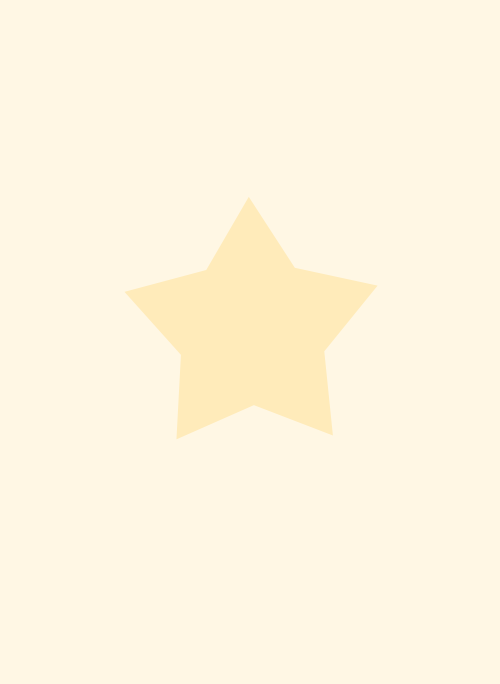「幼い頃からあの方を知っているが、いつも必死だった。そんなあの方を見ていると私が支えないと、と思ったこともある。だが、無理だった。逆に助けられてばかりだった」
小さく息を吐き、トイウォースは力なく笑う。
「……今回の祖父のことで、私ではあの方を支えられる力がないと思い知らされたよ。そんな時、君がふらっとやって来た。君の何処かのんびりな雰囲気を感じて、君ならネレヴェーユ様を支えられると思った。それが理由だ」
「……何だか人任せな考えだね」
困ったように頬を掻き、カエティスは呟く。
「だが、まんざらでもないのだろう? 君の本音はどうなのだ、カエティス?」
「……どうって、そりゃあ、良い人だし、反応が可愛いよ。俺のような人間にも手を差し延べてくれる人だし……でも」
そこで、カエティスは悲しげな表情で言葉を止める。
怪訝な顔をして、トイウォースはカエティスを見る。
「……でも、俺では彼女を幸せには出来ない」
「どうして、そう後ろ向きな理由を言うかな、君は」
「元々の考え方が後ろ向きなんだよ、俺は」
「拗ねて良いような年齢ではないだろう、カエティス。まぁ、私も似たようなことをクレハに言われるが」
嬉しさを隠し切れずにトイウォースは頭を何度も縦に動かす。