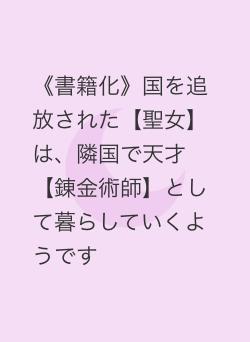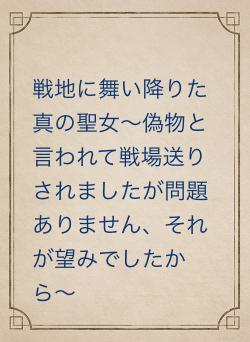「だから、シャルロット! 君はあんな奴と結婚するべきじゃないんだ! このまま結婚したら、君は酷い目に遭う!」
私の名前を恥ずかしげもなく大声で発しながら、私の幼馴染、ノールが大袈裟な身振りをする。
話題に上がっているあんな奴というのは、私の婚約者であるウィルフリッド第一王子。
彼との婚約は、私が生まれて間もなく、公爵である父と国王によって決められたものだった。
ウィルはもうすぐ立太子を承り、正式に王太子となる。
王太子であるウィルと、諸外国にも影響力を持っている公爵家の私が結婚すれば、この国はより一層盤石のものになるというのが父たちの考えだ。
私は黙って、ノールの続く言葉を真面目な顔で聞く。
「信じて! そうだ! 僕は実は未来からタイムリープしてきたんだ! だから、このままいけば、君が大変な目に遭うって知っているんだ!」
「未来からタイムリープ? ねぇ。それって、王家に伝わる伝説でしょ? 王城の時計台の裏に隠されている宝石の」
「そ、そうだよ! なんだ、シャルロット。君は知っていたのか……とにかく! 君はさっさとウィルフリッドと別れた方がいい!」
別れた方がいいとノールは熱弁するけれど、私の意思ではどうしようもないのだ。
公爵と国王が決めた婚約を、国の繁栄のために為された政略を、いったい誰が破棄などできるだろうか。
「別れた方がいいって言っても、私がどうにかできる話ではないのはノールが良く知っているはずでしょう?」
「ウィルフリッドに、こ……婚約破棄を宣言させるってのはどうかな……?」
「今度は婚約破棄? それはこの間、ノールが巷で流行っているって手に入れた恋物語に出てくるものよね? 現実で考えてたら、そんな馬鹿なことをする人なんていないわ。だって、いくら第一王子だろうが、王太子になろうが。そんなことを一方的に宣言できるはずなんてないんですもの」
「う……ところで、自分でいうのもなんだけど。シャルロットは僕がタイムリープしたって言っても、おかしいとか、どういうことか? とか言わないんだね?」
「あら? ノールが言い出したんでしょう? それとも否定して欲しいの? 嘘を言っているって」
「あ、いや……そんなことないけど……」
「そうだ! あなたを信じる手っ取り早い方法があるわ。一緒に時計台の裏へ行きましょう! そうしたらノールがタイムリープしたかどうか、すぐに分かるでしょう?」
「え!?」
未来から記憶を持ったまま過去に戻るタイムリープ。
おとぎ話のような伝説だが、この国の者たちはそれがただの作り話ではないと信じている。
今から何代も前の国王が、実際にタイプリープを経験したという公式の記録が、残っているのだ。
王城の西にそびえたつ、時計台。
いつ建てられたのかも定かでないが、この王国の歴史を休むことなく刻んでいる。
その時計の裏側に存在する小部屋に、伝説の『時を駆ける水晶』は置かれている。
「この先に国を救った英雄王の話に出てくる伝説の水晶があるんでしょう? そんな不思議な宝石が実際にあるなんて、私、どうしても見てみたくて!」
私は年相応の陽気な声を上げながら、公爵である父の手を引く。
父の後ろには国王も一緒だ。
私に向かって、国王は笑顔で私に向かって話しかけてきた。
「ははは。シャルロット嬢は物知りだな。それじゃあ、英雄王の話もきちんと知っているんだね?」
「ええ! 今からはるか昔の国王が、未来に起こる様々な災害を予見して、未然に防いだってお話よね? 英雄王が未来を予見できたのは、災害で潰えそうになった未来から、水晶の力で過去に戻ったからだって」
「その通り。だが、その後、多くの者が試してみたけれど、残念ながら過去に戻れたという記録は、一切残っていない」
「でも、誰かが伝説を騙って、未来から来たって言い出したら?」
私の問いに、国王はより一層笑みを深くし、私の頭を優しく撫でた。
「シャルロット嬢は物知りなだけじゃなく思慮深い。確かに過去に戻ったと言い出した者は少なからずいた。だが、全員が嘘をついているとすぐに見破られたんだ」
「どうしてかしら?」
「うん。それは『時を駆ける水晶』の不思議な性質にある。一般には知られていないが、この水晶を使い過去に戻った者が水晶の部屋に同室すると、なんと水晶がきれいさっぱり姿を消すのだ。英雄王は未来を予見するだけではなく、そうやって人々に説明したと、王家に代々伝わる歴史書に書かれている」
「さぁ、着いたよ。ここが水晶の部屋だ」
小さな扉の前に辿り着き、父がそう言った。
国王は懐から鍵を取り出し、幾重にもかけられた錠を外していく。
「これで最後だ。さて。シャルロット嬢。お先にお入り。ノールも。その後に私たちも続こう」
「はい……」
「うふふ。楽しみだわ」
私、ノール。続いて父と国王が順に水晶の部屋へと入っていく。
水晶の部屋の入口はとても背が低く、子供が通っても、後続の者が中を覗けないほどだ。
大人が入るとなると、身を屈めないといけない。
入口の割に、部屋の中はそれなりに広く、天井も大人がぶつからない程度には高い。
私の後に入ってきたノールは、部屋の中をきょろきょろと見渡している。
「どうだい? 美しいだろう。私も久しぶりにお目にかかるよ」
ノールの次に部屋に入ってきた父が、楽しそうな声を上げた。
私はすかさず言葉を返す。
「お父様? どこに伝説の水晶が置かれていますの?」
「どこって部屋の中央の台座の上に……なっ!?」
「どうした? 何をそんなに驚いておる」
最後に入ってきた国王が、父の発した声に訝し気に尋ねた。
そして、すぐに事態を理解し、目を丸くする。
「お父様。陛下。私には何も置かれていない台座しか見えません。あなたもそうなの? ノール?」
「え? あ、ああ……」
「こんなことが……すまんが一旦みんな出てくれ。わし一人だけでもう一度入る。まさかとは思うが……」
「え、ええ。じゃ、じゃあ。皆出よう」
父に促され、入ってきたのと逆の順番で水晶の部屋を出て行く。
全員が出たことを確認した国王は、私たちの方を見渡して、真剣な眼差しで問うた。
「わしがここの錠を確かに開けた。つまり、それまでは誰も入れなかったはずだ。そうだな?」
「ええ。私見てました。陛下がたくさんの鍵をお使いになるところを」
「うむ。そうだな。『時を駆ける水晶』は国宝。もしもわしの代で盗まれたとなったら、未来永劫の笑い者だ。しかし。もう一つだけ可能性がある」
そう言い切ると、国王は一人で再び水晶の部屋へと入っていった。
ほどなくして、部屋の中から国王の叫び声が漏れ聞こえた。
国王の父を呼ぶ声に、父は慌てた様子で中へ入っていく。
父も国王同様驚きの声を叫んでいた。
すぐに部屋から飛び出してきた二人が私たちに興奮した様子で、見てきたことを口々に話す。
「あった! あったのだ! 水晶が確かに台座の上に!」
「ええ。陛下! 私もこの目でしかと見ました! 先ほどは確かになかったはずなのに!」
「陛下。お父様。実は、ここへ来たいと言ったのには訳があるのです。ノールが、未来からタイムリープしたと言い出して」
「なんだと? ノールが?」
「ええ。しかも、私の婚約者。ウィルと私が一緒になると、災いが起こると言っていました」
「なに!? ノール! それは真か!?」
「は、はい……たしかに……言いました……」
父と国王は互いに顔を見合わせる。
そして唸りながら私とウィルフリッドの婚約を考え直す話を互いにし始めた。
「正直なところ、英雄王と水晶の話は、嘘ばかりではないだろうが後世の者が考えた作り話だと思っていた。しかし、実際にこの目で見たからには信じる他あるまい。そのノールが二人の婚約が災いをもたらすと言ったのならば……」
「ええ。陛下。今まで英雄王一人しか過去に戻った記録がないため、真偽のほどは不明ですが、一説によれば国が大きく傾いた時しか、水晶の力は発揮されないとも……」
「うむ。いずれにしろ、婚約の件はこのまま野放しにしておくわけにはいかないな。ノールの話をよく聞き、信憑性が高いとなればその時は」
「ええ。残念ですが、婚約を破棄せざるをえませんな」
不安そうに私の目をじっと見つめるノールに、私は小さな声で「大丈夫よ」と言いながら片目をつぶった。
***
ノールは大小さまざまな国内の問題を予見し、未来を経験し過去へ戻ってきたという評価は揺るぎないものになっていた。
その間にノールの進言により、私の婚約は破棄され、ウィルフリッド第一王子の立太子は保留になった。
そして月日が流れ、ノールはすでに自分の知る未来とは大きく異なる、平和な歴史を歩んでいると宣言するに至る。
国民はノールマン第二王子を英雄王の再来だと崇め、彼こそが王太子に相応しいとこぞって噂した。
一方のウィルフリッドは生来の性格も災いし、数々の問題を起こしたせいで王に相応しくないと国中が騒いでいた。
立太子式の前日、ノールが私に話を切り出した。
タイムリープしたと私に言ったあの日の彼に比べると、背は随分と伸び、凛々しい顔立ちになっている。
「シャルロット。いつか、君に確かめなくてはと思って、今まで聞けなかったことがある。なんのことだか、分かってると思うけど」
「あら。何かしら。ノール」
「あの日。幼い僕が口から出まかせを言ったことに、君は気付いていたんだろう? それに、その後は君の言う通りに父上、陛下に進言した。君の言うことはその通りになった」
「全て、ではないわ。外れたこともあるでしょう? それに、歴史は繰り返すものよ。ノール」
柔らかな微笑みを携えたまま、ノールは私の目をしっかりと見つめる。
「僕はタイムリープなんてしていない。だから、今でも水晶を見ることが出来るんだ。実はこっそり一人で見に行ってきたんだ。思ったよりもずっと小さいものだった。そう、子供でも隠せそうなくらいね」
「何が言いたいのかしら?」
「シャルロット。思えば、君は昔から驚くほど聡い女性だった。そして勉強家だ。君は凄惨な未来から、歴史を変えるために戻ってきたのかい? それとも……」
「ノール。私が未来から来たかどうかなんて重要なことかしら? 重要なのは今じゃない? それとも、私と歩む未来は嫌なのかしら?」
私はいたずらな笑みをノールに返す。
破顔一笑。
ノールはたくましく成長した腕で、私を軽々と持ち上げた。
「まさか! 最高に素晴らしい未来だよ! わが姫!」
国王となったノールは良く国を治め、私はその傍らで夫である彼を支えながら幸せに暮らした。
この国の歴史書には、未来から過去へと戻り災害から守った二人の英雄王の話が記されている。
私の名前を恥ずかしげもなく大声で発しながら、私の幼馴染、ノールが大袈裟な身振りをする。
話題に上がっているあんな奴というのは、私の婚約者であるウィルフリッド第一王子。
彼との婚約は、私が生まれて間もなく、公爵である父と国王によって決められたものだった。
ウィルはもうすぐ立太子を承り、正式に王太子となる。
王太子であるウィルと、諸外国にも影響力を持っている公爵家の私が結婚すれば、この国はより一層盤石のものになるというのが父たちの考えだ。
私は黙って、ノールの続く言葉を真面目な顔で聞く。
「信じて! そうだ! 僕は実は未来からタイムリープしてきたんだ! だから、このままいけば、君が大変な目に遭うって知っているんだ!」
「未来からタイムリープ? ねぇ。それって、王家に伝わる伝説でしょ? 王城の時計台の裏に隠されている宝石の」
「そ、そうだよ! なんだ、シャルロット。君は知っていたのか……とにかく! 君はさっさとウィルフリッドと別れた方がいい!」
別れた方がいいとノールは熱弁するけれど、私の意思ではどうしようもないのだ。
公爵と国王が決めた婚約を、国の繁栄のために為された政略を、いったい誰が破棄などできるだろうか。
「別れた方がいいって言っても、私がどうにかできる話ではないのはノールが良く知っているはずでしょう?」
「ウィルフリッドに、こ……婚約破棄を宣言させるってのはどうかな……?」
「今度は婚約破棄? それはこの間、ノールが巷で流行っているって手に入れた恋物語に出てくるものよね? 現実で考えてたら、そんな馬鹿なことをする人なんていないわ。だって、いくら第一王子だろうが、王太子になろうが。そんなことを一方的に宣言できるはずなんてないんですもの」
「う……ところで、自分でいうのもなんだけど。シャルロットは僕がタイムリープしたって言っても、おかしいとか、どういうことか? とか言わないんだね?」
「あら? ノールが言い出したんでしょう? それとも否定して欲しいの? 嘘を言っているって」
「あ、いや……そんなことないけど……」
「そうだ! あなたを信じる手っ取り早い方法があるわ。一緒に時計台の裏へ行きましょう! そうしたらノールがタイムリープしたかどうか、すぐに分かるでしょう?」
「え!?」
未来から記憶を持ったまま過去に戻るタイムリープ。
おとぎ話のような伝説だが、この国の者たちはそれがただの作り話ではないと信じている。
今から何代も前の国王が、実際にタイプリープを経験したという公式の記録が、残っているのだ。
王城の西にそびえたつ、時計台。
いつ建てられたのかも定かでないが、この王国の歴史を休むことなく刻んでいる。
その時計の裏側に存在する小部屋に、伝説の『時を駆ける水晶』は置かれている。
「この先に国を救った英雄王の話に出てくる伝説の水晶があるんでしょう? そんな不思議な宝石が実際にあるなんて、私、どうしても見てみたくて!」
私は年相応の陽気な声を上げながら、公爵である父の手を引く。
父の後ろには国王も一緒だ。
私に向かって、国王は笑顔で私に向かって話しかけてきた。
「ははは。シャルロット嬢は物知りだな。それじゃあ、英雄王の話もきちんと知っているんだね?」
「ええ! 今からはるか昔の国王が、未来に起こる様々な災害を予見して、未然に防いだってお話よね? 英雄王が未来を予見できたのは、災害で潰えそうになった未来から、水晶の力で過去に戻ったからだって」
「その通り。だが、その後、多くの者が試してみたけれど、残念ながら過去に戻れたという記録は、一切残っていない」
「でも、誰かが伝説を騙って、未来から来たって言い出したら?」
私の問いに、国王はより一層笑みを深くし、私の頭を優しく撫でた。
「シャルロット嬢は物知りなだけじゃなく思慮深い。確かに過去に戻ったと言い出した者は少なからずいた。だが、全員が嘘をついているとすぐに見破られたんだ」
「どうしてかしら?」
「うん。それは『時を駆ける水晶』の不思議な性質にある。一般には知られていないが、この水晶を使い過去に戻った者が水晶の部屋に同室すると、なんと水晶がきれいさっぱり姿を消すのだ。英雄王は未来を予見するだけではなく、そうやって人々に説明したと、王家に代々伝わる歴史書に書かれている」
「さぁ、着いたよ。ここが水晶の部屋だ」
小さな扉の前に辿り着き、父がそう言った。
国王は懐から鍵を取り出し、幾重にもかけられた錠を外していく。
「これで最後だ。さて。シャルロット嬢。お先にお入り。ノールも。その後に私たちも続こう」
「はい……」
「うふふ。楽しみだわ」
私、ノール。続いて父と国王が順に水晶の部屋へと入っていく。
水晶の部屋の入口はとても背が低く、子供が通っても、後続の者が中を覗けないほどだ。
大人が入るとなると、身を屈めないといけない。
入口の割に、部屋の中はそれなりに広く、天井も大人がぶつからない程度には高い。
私の後に入ってきたノールは、部屋の中をきょろきょろと見渡している。
「どうだい? 美しいだろう。私も久しぶりにお目にかかるよ」
ノールの次に部屋に入ってきた父が、楽しそうな声を上げた。
私はすかさず言葉を返す。
「お父様? どこに伝説の水晶が置かれていますの?」
「どこって部屋の中央の台座の上に……なっ!?」
「どうした? 何をそんなに驚いておる」
最後に入ってきた国王が、父の発した声に訝し気に尋ねた。
そして、すぐに事態を理解し、目を丸くする。
「お父様。陛下。私には何も置かれていない台座しか見えません。あなたもそうなの? ノール?」
「え? あ、ああ……」
「こんなことが……すまんが一旦みんな出てくれ。わし一人だけでもう一度入る。まさかとは思うが……」
「え、ええ。じゃ、じゃあ。皆出よう」
父に促され、入ってきたのと逆の順番で水晶の部屋を出て行く。
全員が出たことを確認した国王は、私たちの方を見渡して、真剣な眼差しで問うた。
「わしがここの錠を確かに開けた。つまり、それまでは誰も入れなかったはずだ。そうだな?」
「ええ。私見てました。陛下がたくさんの鍵をお使いになるところを」
「うむ。そうだな。『時を駆ける水晶』は国宝。もしもわしの代で盗まれたとなったら、未来永劫の笑い者だ。しかし。もう一つだけ可能性がある」
そう言い切ると、国王は一人で再び水晶の部屋へと入っていった。
ほどなくして、部屋の中から国王の叫び声が漏れ聞こえた。
国王の父を呼ぶ声に、父は慌てた様子で中へ入っていく。
父も国王同様驚きの声を叫んでいた。
すぐに部屋から飛び出してきた二人が私たちに興奮した様子で、見てきたことを口々に話す。
「あった! あったのだ! 水晶が確かに台座の上に!」
「ええ。陛下! 私もこの目でしかと見ました! 先ほどは確かになかったはずなのに!」
「陛下。お父様。実は、ここへ来たいと言ったのには訳があるのです。ノールが、未来からタイムリープしたと言い出して」
「なんだと? ノールが?」
「ええ。しかも、私の婚約者。ウィルと私が一緒になると、災いが起こると言っていました」
「なに!? ノール! それは真か!?」
「は、はい……たしかに……言いました……」
父と国王は互いに顔を見合わせる。
そして唸りながら私とウィルフリッドの婚約を考え直す話を互いにし始めた。
「正直なところ、英雄王と水晶の話は、嘘ばかりではないだろうが後世の者が考えた作り話だと思っていた。しかし、実際にこの目で見たからには信じる他あるまい。そのノールが二人の婚約が災いをもたらすと言ったのならば……」
「ええ。陛下。今まで英雄王一人しか過去に戻った記録がないため、真偽のほどは不明ですが、一説によれば国が大きく傾いた時しか、水晶の力は発揮されないとも……」
「うむ。いずれにしろ、婚約の件はこのまま野放しにしておくわけにはいかないな。ノールの話をよく聞き、信憑性が高いとなればその時は」
「ええ。残念ですが、婚約を破棄せざるをえませんな」
不安そうに私の目をじっと見つめるノールに、私は小さな声で「大丈夫よ」と言いながら片目をつぶった。
***
ノールは大小さまざまな国内の問題を予見し、未来を経験し過去へ戻ってきたという評価は揺るぎないものになっていた。
その間にノールの進言により、私の婚約は破棄され、ウィルフリッド第一王子の立太子は保留になった。
そして月日が流れ、ノールはすでに自分の知る未来とは大きく異なる、平和な歴史を歩んでいると宣言するに至る。
国民はノールマン第二王子を英雄王の再来だと崇め、彼こそが王太子に相応しいとこぞって噂した。
一方のウィルフリッドは生来の性格も災いし、数々の問題を起こしたせいで王に相応しくないと国中が騒いでいた。
立太子式の前日、ノールが私に話を切り出した。
タイムリープしたと私に言ったあの日の彼に比べると、背は随分と伸び、凛々しい顔立ちになっている。
「シャルロット。いつか、君に確かめなくてはと思って、今まで聞けなかったことがある。なんのことだか、分かってると思うけど」
「あら。何かしら。ノール」
「あの日。幼い僕が口から出まかせを言ったことに、君は気付いていたんだろう? それに、その後は君の言う通りに父上、陛下に進言した。君の言うことはその通りになった」
「全て、ではないわ。外れたこともあるでしょう? それに、歴史は繰り返すものよ。ノール」
柔らかな微笑みを携えたまま、ノールは私の目をしっかりと見つめる。
「僕はタイムリープなんてしていない。だから、今でも水晶を見ることが出来るんだ。実はこっそり一人で見に行ってきたんだ。思ったよりもずっと小さいものだった。そう、子供でも隠せそうなくらいね」
「何が言いたいのかしら?」
「シャルロット。思えば、君は昔から驚くほど聡い女性だった。そして勉強家だ。君は凄惨な未来から、歴史を変えるために戻ってきたのかい? それとも……」
「ノール。私が未来から来たかどうかなんて重要なことかしら? 重要なのは今じゃない? それとも、私と歩む未来は嫌なのかしら?」
私はいたずらな笑みをノールに返す。
破顔一笑。
ノールはたくましく成長した腕で、私を軽々と持ち上げた。
「まさか! 最高に素晴らしい未来だよ! わが姫!」
国王となったノールは良く国を治め、私はその傍らで夫である彼を支えながら幸せに暮らした。
この国の歴史書には、未来から過去へと戻り災害から守った二人の英雄王の話が記されている。