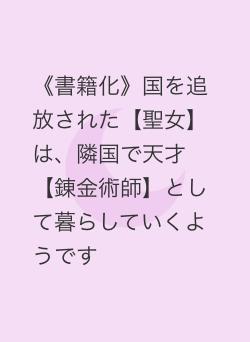「聖女様。この美しい花は?」
ある日、用事があり私の居室を訪れたデイジーが部屋に飾ってあるリラの花を見つけ聞いてきた。
それは自分で入れた記憶が無いのにも関わらず、気付くと居室にあった。
綺麗な紫色の花を咲かせるその木は、間違いなく私が育てたリラの花だ。
誰が持ってきて置いたのか知らないけれど、ここにある以上は世話をしている。
無視をして枯らすことなど考えもしなかった。
聖女に選ばれるために育てさせられたと今では知っていたけれど、この花自体に罪はない。
「それリラの花よ」
聖女に関することはわざわざ話す気になれず、素っ気なく私はそうとだけ答えた。
「素敵な色の花ですね。小さくても、色に深みがあって。凛として美しい」
「そうかしら。そう言ってもらえると嬉しいわ。ありがとう」
「私もこんな素敵な花育ててみたいなって思いました。私の方こそありがとうございます」
「あら。じゃあ、少し分けてあげるから、デイジーの部屋でも育ててみたら?」
私の申し出にデイジーは驚いた顔をする。
しかし、どうもその後の表情を見ると、よほど花が好きなのだろう、断ることがないということが既に分かった。
「本当ですか⁉ ありがとうございます‼ 大切に育てますね‼」
「ええ。少し育てるのが難しい木だけれど、丁寧に育ててあげればきれいな花が咲くと思うわ」
そう言って私は枝を数本切り落とし、デイジーに手渡す。
デイジーは嬉しそうにそれを受け取り、お礼を言って一度頭を下げてから部屋を出ていった。
「さて……デイジーはどの色の花を咲かせるかしら……」
そんなことを考えていたら一人の兵士が書簡を持ってやってきた。
厳重に封がされていて、持ってきた兵士も誰から送られてきたのか分からないという。
「変ね……普通は中身の検閲があるはずだと聞いているけれど……」
前線に送られるものも、前線から送るものも、ほとんどは中身に問題がないか確認されるはずだった。
しかし、封が切られていないということは、これは検閲を免れたということだ。
よほど権力のある人物からの書簡だと見て間違いはないだろう。
父からだろうか……そう思いながら、私は封を切る。
始めに、書かれている署名に目をやり、予想していなかった人物のものだと分かり驚愕する。
確かに、彼ならば検閲を免れるだろう。
「ベリル王子が私に手紙だなんて……」
この戦場に送る直接の原因となった人物の顔を思い浮かべる。
紅い目の兄のルチル王子とは異なり、思慮と慈愛に満ちた蒼色の瞳を始めに思い出す。
髪は兄弟揃って金色に輝き、柔らかな物腰ながらも王族としての威厳を醸し出す人物だ。
結果的にベリル王子のおかげで私は昔からの夢の実現へと邁進できていると言える。
ただ、直接何か関係を持った記憶は本当に一度しか思い浮かべられない。
そんなベリル王子が私に手紙などどういうことだろうか。
そこには私への労いの言葉と、そしてリラの花を運ばせたのがベリル王子だということが書かれていた。
さらに花の色は何色か定期的に手紙を送るようにとも。
「一体どういうつもりかしら。まぁ、嘘を言うつもりも、王子の命令に背くつもりもないけれど」
私は落ち着いたら家に手紙を書くために持ってきていた用紙を取り出し、ベリル王子に近況と花の色が紫色だと書いた。
封は手紙に同封されていた印を打つ。
手紙にはベリル王子への手紙は全てこの印を使って封をするようにと書かれていたからだ。
そしてそれを、手紙を持ってきた兵士に渡した。
数日経って、ベリル王子から返信が届いた。
この陣営から王都まではかなりの距離がある。
どんなに急いでも数日で往復できる距離ではない。
ということはベリル王子は王都を離れ、陣営の近くに来ているのだろうか。
「もしくは誰かのイタズラかしら。こんな手の込んだイタズラをする相手も、する理由も思いつかないけれど」
そんな独り言を言いながら、返信の封を切り中を確認する。
そこには『分かった』とだけ書かれていた。
「本当にどういうことかしら……定期的に手紙を送れば、いずれは何か分かるのかしら」
私は再び近況とリラの花の色を書き、手紙を送り返した。
☆
「やぁ。フローラ嬢。なかなかの活躍らしいじゃないか。まぁ、そこに座っておくれよ」
ある日、第五衛生兵部隊の部隊長であるアンバーが、私を自室に呼び出した。
随分と自由に動き回っていた自覚はあるので、そのお小言だろうか。
「それで、聖女様? だっけ。兵士たちは君のことをそんな名前で呼ばせているみたいだけど?」
「私から呼ばせた記憶はありません。勝手に呼び始め、あまりに多いので訂正ができない状況です」
私の言葉を聞いたアンバーは、こめかみを揉みほぐす仕草をしてからこう言った。
「困るんだよねぇ。君だって、聖女という意味を知らないわけじゃないだろう? ここだけで呼ばれるならまだいいけれど、ねぇ」
「それは私に呼ばれる度に否定しろと言う命令でしょうか? 先ほども言いましたが、数が多すぎて対処しきれません。私の預かり知らぬところで呼ぶ人たちもいます」
「とにかくさ。僕の立場も考えてよ。困るだろう? 誰とは言わないが、ある人の耳にこのことが入ったりしたら」
「分かりました。善処します」
ある人、というのはルチル王子のことだろう。
アンバーは見かけによらず情報通のようだ。
私がルチル王子に偽の聖女だと言われてここに送られてきていることを知っているらしい。
しかし、ここに来てからすでにある程度の日数が経つが、このアンバーという人物が何を考えているのかは分かりかねた。
いつも気だるそうに、やる気のなさを隠す素振りもせず、そのくせ笑顔を絶やさずに任に当たっている。
ただ、その発言や行動には何かを隠しているような不自然さが時折見え隠れしていた。
「ま、ということで、ひとつ頼むよ。それで――」
「大変です‼ 魔獣の群れが‼ この陣営に迫ってきています‼」
アンバーの言葉を遮るように、一人の兵士が司令室であるアンバーの部屋に入って急を告げた。
それを合図にするかのように、戦闘が始まったことが分かる騒音が外から聞こえてきた。
ある日、用事があり私の居室を訪れたデイジーが部屋に飾ってあるリラの花を見つけ聞いてきた。
それは自分で入れた記憶が無いのにも関わらず、気付くと居室にあった。
綺麗な紫色の花を咲かせるその木は、間違いなく私が育てたリラの花だ。
誰が持ってきて置いたのか知らないけれど、ここにある以上は世話をしている。
無視をして枯らすことなど考えもしなかった。
聖女に選ばれるために育てさせられたと今では知っていたけれど、この花自体に罪はない。
「それリラの花よ」
聖女に関することはわざわざ話す気になれず、素っ気なく私はそうとだけ答えた。
「素敵な色の花ですね。小さくても、色に深みがあって。凛として美しい」
「そうかしら。そう言ってもらえると嬉しいわ。ありがとう」
「私もこんな素敵な花育ててみたいなって思いました。私の方こそありがとうございます」
「あら。じゃあ、少し分けてあげるから、デイジーの部屋でも育ててみたら?」
私の申し出にデイジーは驚いた顔をする。
しかし、どうもその後の表情を見ると、よほど花が好きなのだろう、断ることがないということが既に分かった。
「本当ですか⁉ ありがとうございます‼ 大切に育てますね‼」
「ええ。少し育てるのが難しい木だけれど、丁寧に育ててあげればきれいな花が咲くと思うわ」
そう言って私は枝を数本切り落とし、デイジーに手渡す。
デイジーは嬉しそうにそれを受け取り、お礼を言って一度頭を下げてから部屋を出ていった。
「さて……デイジーはどの色の花を咲かせるかしら……」
そんなことを考えていたら一人の兵士が書簡を持ってやってきた。
厳重に封がされていて、持ってきた兵士も誰から送られてきたのか分からないという。
「変ね……普通は中身の検閲があるはずだと聞いているけれど……」
前線に送られるものも、前線から送るものも、ほとんどは中身に問題がないか確認されるはずだった。
しかし、封が切られていないということは、これは検閲を免れたということだ。
よほど権力のある人物からの書簡だと見て間違いはないだろう。
父からだろうか……そう思いながら、私は封を切る。
始めに、書かれている署名に目をやり、予想していなかった人物のものだと分かり驚愕する。
確かに、彼ならば検閲を免れるだろう。
「ベリル王子が私に手紙だなんて……」
この戦場に送る直接の原因となった人物の顔を思い浮かべる。
紅い目の兄のルチル王子とは異なり、思慮と慈愛に満ちた蒼色の瞳を始めに思い出す。
髪は兄弟揃って金色に輝き、柔らかな物腰ながらも王族としての威厳を醸し出す人物だ。
結果的にベリル王子のおかげで私は昔からの夢の実現へと邁進できていると言える。
ただ、直接何か関係を持った記憶は本当に一度しか思い浮かべられない。
そんなベリル王子が私に手紙などどういうことだろうか。
そこには私への労いの言葉と、そしてリラの花を運ばせたのがベリル王子だということが書かれていた。
さらに花の色は何色か定期的に手紙を送るようにとも。
「一体どういうつもりかしら。まぁ、嘘を言うつもりも、王子の命令に背くつもりもないけれど」
私は落ち着いたら家に手紙を書くために持ってきていた用紙を取り出し、ベリル王子に近況と花の色が紫色だと書いた。
封は手紙に同封されていた印を打つ。
手紙にはベリル王子への手紙は全てこの印を使って封をするようにと書かれていたからだ。
そしてそれを、手紙を持ってきた兵士に渡した。
数日経って、ベリル王子から返信が届いた。
この陣営から王都まではかなりの距離がある。
どんなに急いでも数日で往復できる距離ではない。
ということはベリル王子は王都を離れ、陣営の近くに来ているのだろうか。
「もしくは誰かのイタズラかしら。こんな手の込んだイタズラをする相手も、する理由も思いつかないけれど」
そんな独り言を言いながら、返信の封を切り中を確認する。
そこには『分かった』とだけ書かれていた。
「本当にどういうことかしら……定期的に手紙を送れば、いずれは何か分かるのかしら」
私は再び近況とリラの花の色を書き、手紙を送り返した。
☆
「やぁ。フローラ嬢。なかなかの活躍らしいじゃないか。まぁ、そこに座っておくれよ」
ある日、第五衛生兵部隊の部隊長であるアンバーが、私を自室に呼び出した。
随分と自由に動き回っていた自覚はあるので、そのお小言だろうか。
「それで、聖女様? だっけ。兵士たちは君のことをそんな名前で呼ばせているみたいだけど?」
「私から呼ばせた記憶はありません。勝手に呼び始め、あまりに多いので訂正ができない状況です」
私の言葉を聞いたアンバーは、こめかみを揉みほぐす仕草をしてからこう言った。
「困るんだよねぇ。君だって、聖女という意味を知らないわけじゃないだろう? ここだけで呼ばれるならまだいいけれど、ねぇ」
「それは私に呼ばれる度に否定しろと言う命令でしょうか? 先ほども言いましたが、数が多すぎて対処しきれません。私の預かり知らぬところで呼ぶ人たちもいます」
「とにかくさ。僕の立場も考えてよ。困るだろう? 誰とは言わないが、ある人の耳にこのことが入ったりしたら」
「分かりました。善処します」
ある人、というのはルチル王子のことだろう。
アンバーは見かけによらず情報通のようだ。
私がルチル王子に偽の聖女だと言われてここに送られてきていることを知っているらしい。
しかし、ここに来てからすでにある程度の日数が経つが、このアンバーという人物が何を考えているのかは分かりかねた。
いつも気だるそうに、やる気のなさを隠す素振りもせず、そのくせ笑顔を絶やさずに任に当たっている。
ただ、その発言や行動には何かを隠しているような不自然さが時折見え隠れしていた。
「ま、ということで、ひとつ頼むよ。それで――」
「大変です‼ 魔獣の群れが‼ この陣営に迫ってきています‼」
アンバーの言葉を遮るように、一人の兵士が司令室であるアンバーの部屋に入って急を告げた。
それを合図にするかのように、戦闘が始まったことが分かる騒音が外から聞こえてきた。